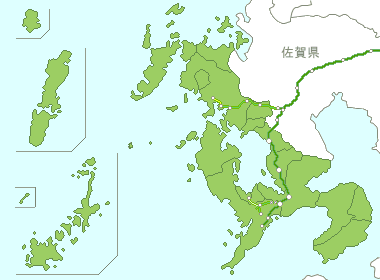神社・寺院・歴史 一覧

-
し 島原城

- [ 城 | 歴史 ]

-
島原市城内1-1183-1
別名、森岳城、高来城。
寛永元年(1624年)、築城の名手と讃えられた藩主・松倉重政が、7年の歳月をかけて完成させた城。この時領民
- [ 歴史的建造物 | 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
長崎市立山1
長崎県防空本部が置かれた被爆建造物。
太平洋戦争中に空襲警報が発令されると県知事ら要員が集まり、警備、救護などの指揮をした場所。壕内施設と通路の
-
は 原山支石墓群
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
南島原市北有馬町原山
「原山ドルメン」ともいわれ、日本最大級の支石墓群。
縄文時代晩期の共同墓地で、日本最大級の支石墓群で1972年(昭和47年)11月6日国の史跡に指定。支石墓は
-
は 原城跡
- [ 歴史 | 城 ]

-
南島原市南有馬町大江
天草四郎最後の舞台「原城跡」
別名「日暮城」。原城は島原城の築城によって廃城したものの、その当時起こった島原の乱で天草四郎が率いた一揆軍
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]

-
大村市古町1-63
大村藩歴代藩主墓碑群。
日蓮宗本経寺の境内南側の2000坪の敷地に藩主をはじめ、正室・側室・一族家臣など全78基の墓と、石灯籠48
-
か 勝本城跡
- [ 城 | 歴史 ]
-
壱岐市勝本町坂本触城ノ越757
豊臣秀吉の秀吉の朝鮮出兵(文禄の役)に際して急造された武末城の城跡公園。現在は石垣の遺が残るのみ。展望台か
-
き 旧島原藩薬園跡
- [ 歴史 ]
-
島原市小山町4703
日本三大薬園の一つ。
1846(弘化3)年、藩臣飯島義角を薬園主任として、雲仙岳眉山のふもとに薬園を開墾。現在薬草見本園として、
-
け 慶巌寺
- [ 寺院 ]
-
諫早市城見町15-19
筑紫琴六段の曲発祥の地、甲冑工芸史上の名作として有名。
江戸初期創建の浄土宗の寺。筑紫琴の名手、4代目住職玄恕に弟子入りした八橋検校が、修行後京都で作曲した『六段
-
た 高島秋帆旧宅
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
長崎市東小島町5-38
荻野流砲術および西洋砲術の研究をした、兵学者・高島秋帆の邸宅跡。
幕末の砲術家として知られる高島秋帆の住居跡。高島家は長崎の町年寄を務めた旧家。跡地は国の史跡指定後、原爆に
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット | 祭り・イベント ]

-
長崎市上西山町18-15
長崎くんちの舞台としても有名。
「おすわさん」の愛称で親しまれる長崎の総氏神。海の守護神を祀っていて、厄除けや縁結び祈願に多くの人が訪れる
-
ま 満明寺
- [ 寺院 ]
-
雲仙市小浜町雲仙321
大宝元年(701年)、僧・行基がこの地で温泉山を開山伝わる古い寺。
大宝元(701)年に聖僧行基によって開山したと伝わる真言宗の寺。釈迦堂の中には、5mの純金箔の雲仙大仏が鎮
-
わ 若宮稲荷神社
- [ 神社 | 稲荷 ]
-
長崎市伊良林2-10-2
坂本龍馬ゆかりの神社。
緑の木々の中、朱色の鳥居が鮮やかな神社。坂本龍馬をはじめ長崎に往来する志士等が当社に参拝し祈願したことで知
-
い 壱岐風土記の丘
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
壱岐市勝本町布気触324-1
古墳館も整備され、壱岐の古墳群散策を楽しむ玄関口
掛木古墳をはじめ点在する古墳をめぐりながら散策できる歴史公園。古民家園には壱岐独特の百姓武家建築を移築復元
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
大村市今富町586-1
大村市郊外にあるキリシタンの墓碑。
大村藩主純忠とともに洗礼を受けた重臣、一瀬越智相模栄正(おちさがみえしょう)の墓碑で、戒名が刻んであります
-
い 生月大魚籃観音
- [ 観音 B級スポット ]
-
平戸市生月町山田免570-1
ブロンズ像としては日本一の大きさです。
生月大橋から見える舘浦の小高い丘にそびえる大魚籃観音(生月観音堂‎)。ブロンズ像では日本屈指の
-
う 上野彦馬宅跡
- [ 歴史 ]
-
長崎市伊勢町4-14
彦馬はここで坂本龍馬を撮影したといわれる。
日本初のプロカメラマンとして知られる上野彦馬。この場所は、文久2(1862)年に創設した上野撮影局があった
-
し 春徳寺
- [ 寺院 ]
-
長崎市夫婦川町11-1
長崎初の教会トードス・オス・サントス教会が建てられた跡地に建つ寺院。
長崎で最初にできたトードス・オス・サントス教会の跡で、現在もキリシタン(切利支丹)井戸が残っています。山門
-
な 長与専斎旧宅
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
大村市久原2-1030-1
長与専斎の旧宅市指定史跡
初代衛生局長として近代医学の基礎を築き、「衛生」の用語をつくったことで有名有名長与専斎の旧宅。当時は片町の
-
り 龍馬通り
- [ 歴史街道 | 歴史 B級スポット ]
-
長崎市寺町
本龍馬をはじめ幕末の若き志士たちが往来した坂道。
長崎市寺町通りの禅林寺と深崇寺にはさまれた路地(長崎市寺町)から、亀山社中跡(亀山社中記念館)を経て風頭公
-
あ 安国寺
- [ 寺院 ]
-
壱岐市芦辺町深江栄触546
足利尊氏・直義兄弟が暦応年間(1338~42)に全国60余州に建てた安国禅寺の一つに数えられる。仏殿の床が
-
こ 興福寺(長崎市)
- [ 寺院 | 歴史 ]

-
長崎市寺町4-32
黄檗宗の開祖隠元禅師ゆかりの日本最古の唐寺。
元和6(1620)年建立の日本最古の唐寺。山門が朱塗りであるため、あか寺とも呼ばれる。崇福寺・福済寺ととも
-
さ 山王神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
長崎市坂本2丁目5-6
村社であった山王神社(日吉神社)と県社の皇大神宮とが合併(皇大神宮側に合祀)して創祀された神社で、浦上皇大
-
さ 坂本国際墓地
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
長崎市坂本1
明治21年に設けられた外人向け墓地。トーマス・グラバー夫妻、永井隆博士夫妻などの墓がある。
山王通りから山手に入った場所にある外人向け墓地。南側の入り口付近には、原爆で被爆しながらも医療活動を続けら
-
し 椎根の石屋根
- [ 歴史的建造物 ]
-
対馬市厳原町椎根
石屋根の家は日本では対馬だけで、対馬でもこの椎根(しいね)や上槻(こうつき)、久根浜(くねはま)、久根田舎
- [ 神社 ]
-
長崎市住吉町13-6
商売繁盛、安産守護の神様でもあり、多くの祈願が訪れる。
寛永11(1634)年に航海安全をつかさどる海の神様を祀って創建された神社。
-
ほ 方倉神社
- [ 神社 ]
-
平戸市生月町壱部2739
生月の方では「方倉さん」と呼ばれている方倉神社。
古くから生月の守り神として信仰されてきた神社。水天宮ともいいその昔九十九匹の河童が住み着いたと言う伝説があ
-
あ 青砂ヶ浦天主堂
- [ 教会 ]
-
南松浦郡新上五島町奈摩郷1241
「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」を構成する教会堂のひとつ。
五島列島の中通島北部、奈摩湾を望む高台に建つレンガ造りの教会堂。明治43(1910)年に教会堂建築士として
-
お 大浦教会
- [ 教会 ]

-
長崎市南山手町2-18
長崎大司教区が大浦天主堂の隣接地に建立した教会
国宝大浦天主堂が、観光客の増加に伴い、司牧のためには不都合となってきたため、昭和50年(1975)11月、
-
こ 江東寺
- [ 寺院 ]
-
島原市中堀町42
島原城築城主松倉重政の菩提寺。
1558(永禄元)年に創建された禅寺。日本最大ともいわれる涅槃像は境内の墓地にあり、全長約8.1m、高さ約
-
さ 塞神社
- [ 神社 | 珍スポット ]

-
壱岐市郷ノ浦町片原触112
日本書紀に登場する猿田彦の妻・猿女君が奉られている。塞神社由来によると、「神代の昔、天岩戸の裸踊りで知られ