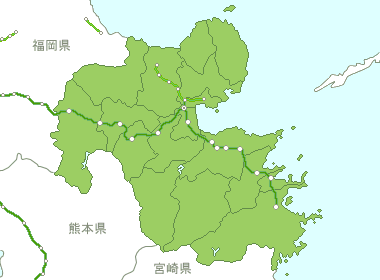神社・寺院・歴史 一覧

-
う 宇佐神宮

- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]

-
宇佐市南宇佐2859
神輿の起源は宇佐にあり。全国4万余社の八幡社の総本宮、宇佐神宮。
1400年前に創建された、全国に4万を超える八幡宮の総本社。通称として宇佐八幡・宇佐八幡宮とも呼ばれる。本
-
ら 羅漢寺(中津市)

- [ 寺院 | 初詣スポット | パワースポット B級スポット ]
-
中津市本耶馬渓町跡田1501
羅漢寺山の中腹に建つ羅漢寺は全国羅漢の総本山。
大化元(645)年にインドの僧、法道仙人が羅漢山の洞窟で修行したことから開基された寺。日本三大五百羅漢の一
-
は 白鹿山 妙覚寺
- [ 寺院 ]

-
豊後大野市千歳町柴山2230番地
石と芸術の里ちとせ
白鹿山山頂に石造の祠がある。白鹿のことが記されたのは古い昔のことという。『日本後紀』巻十に、「延暦二十一年
-
ふ 福沢諭吉旧居
- [ 歴史的建造物 ]

-
中津市留守居町586
福沢諭吉の生涯がわかる
福沢記念館に隣接。初中少年時代(1才6ヶ月から19才まで)をすごした住宅で母屋は木造茅葺平家造現在の大阪大
-
け 見星禅寺
- [ 寺院 ]

-
臼杵市臼杵277
臼杵市に位置する、臨済宗妙心寺派の禅寺。
創建は寛永十一年、時の城主、一通公が、駿府臨済宗より鉄山宗鈍禅師の法孫、一翁東二禅師を拝請され開山。境内に
-
こ 興禅院
- [ 寺院 ]
-
由布市湯布院町川南144-1
建徳元年に建立された曹洞宗の禅寺。
興禅院は、建徳元年(1370年)に無著(むちゃく)禅師により開山したと言われる、曹洞宗の禅寺。一時期教会が
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 | 博物館・資料館 | 公園 ]
-
大分市里646-1
国の史跡の亀塚古墳を中心とする公園。
5世紀初めに造られた、県下最大規模の前方後円墳である亀塚古墳(国指定史跡)と一体化したガイダンス施設で、出
- [ 寺院 | 珍スポット B級スポット ]
-
豊後高田市大字玉津字本丸1026
鬼子母尊神の大石像日本一の大きさ。
鬼子母神はインドから来た仏教の神様。鬼子母尊神の大石像は高さ4m・重さ5トンもあり、日本一の大きさ。城山鬼
-
は 八幡朝見神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
別府市朝見2-15-19
古代より速見の地に温泉があることは広く知られており、「朝見」も「熱海」が変化したものともいわれる。建久7年
-
え 英雄寺のボタン
- [ 寺院 | 花 ]
-
竹田市会々2033
数百の朝鮮ボタンが、毎年色鮮やかな花を咲かせます。
英雄寺は、中川二代久盛公が祖父佐久間玄蕃の菩提を弔うため、寛永21年(1644)建立。安産地蔵でも知られて
-
ふ 富貴寺

- [ 寺院 ]
-
豊後高田市田染蕗2395
718年(養老2)創建と伝えられる天台宗の古刹で、六郷満山[ろくごうまんざん]の本山末寺。大堂はカヤの木の
- [ 歴史 | 公園 ]

-
国東市国東町安国寺1639-2
弥生時代のムラにタイムスリップ
弥生時代のムラや環境を復元するとともに、体験を通して楽しく学べる施設を整備した史跡公園。4万3000平方メ
- [ 神社 | パワースポット ]
-
由布市湯布院町川上2220
「六所様」と呼ばれ親しまれている神社。
六所とは、奉祭する六柱の神々を表しています。広さ約2万平方メートルの境内には樹齢300年を超える杉の御神木
-
な 中津城

- [ 城 | 歴史 ]

-
中津市二ノ丁本丸
城下町中津を代表する観光名所。.
1588(天正16)年に黒田孝高(如水)が築城。水門より海水が入り、潮の干満で水が増減する水城で、高松城(
-
ふ 両子寺
- [ 寺院 | 紅葉 | パワースポット ]
-
国東市安岐町両子1548
 [ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]標高721m、両子山の中腹にある天台宗別格本山。
山門に続く石段の両脇には、江戸後期の作とされる国東半島最大級(総高245cm、像高230cm)の石造の仁王
-
お 岡城跡

- [ 城 | 歴史 | 桜 | 紅葉 ]

-
竹田市竹田
 [ 紅葉時期 11月上旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 11月上旬~11月下旬 ]名曲「荒城の月」のモチーフとなった城跡。春は桜、秋は紅葉の名所。
別名「臥牛城」。標高325mにあり、谷底との高低差は約100m、島津軍を退けた堅城として有名。文治元(11
-
ひ 日田往還
- [ 歴史街道 | 歴史 ]
-
日田市市ノ瀬町
日田から中津へ向う途中で山越えをするために整備された石畳の坂道。
天領時代に日田と豊前中津を結んでいた、かつての幹線で別名「石坂石畳道」。一部に石畳道が残り、文化庁「歴史の
-
も 籾山神社
- [ 神社 ]
-
竹田市直入町長湯
応神天皇を祀り、別名籾山八幡社ともいう。
神社境内には樹齢800年~1000年と推定される御神木「籾山八幡の大ケヤキ」が立っています。根回り約11m
-
じ 十宝山大乗院
- [ 寺院 | 珍スポット B級スポット ]
-
宇佐市四日市
身長約2メートル、三本指のミイラが眠る。
石段の麓には、鬼のミイラの来歴が書かれている。説明書の内容「この寺に安置されている鬼のミイラは、ある名家に
-
ぶ 佛山寺
- [ 寺院 ]
-
由布市湯布院町川上1879
座禅堂があり、予約すれば座禅や写経も体験できる。
杉と竹林の中に建つ古くから由布岳の山岳信仰の場として親しまれてきた臨済宗の寺。由布岳の山の神で、例年7月1
-
お 大分縣護國神社
- [ 神社 | 初詣スポット | 桜 | 梅 ]

-
大分市牧1371
大分市の中央部、小山、松栄山の中腹にある神社。
展望台からは大分市・別府湾が一望できる。大分県護国神社には多くの慰霊碑や西南戦争で亡くなった軍人や警官の墓
-
く 久家の大蔵
- [ 歴史的建造物 ]
-
臼杵市浜町
1868年(江戸時代末期)に棟上げされた古い蔵。
造り酒屋の『久家本店』がかつて貯蔵庫として使用していた酒蔵で、外壁や内部には、往時のキリシタン文化を彷佛と
-
ざ 財前家墓地
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
杵築市大田小野1609
国東の豪族「財前一族」の墓。
大小の国東塔、板碑、五輪塔等111基が散在。このあたりを治めた財前一族の墓地で、中央にある高さ3mの国東塔
- [ 歴史的建造物 | 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
中津市留守居町586
福澤諭吉が蘭学を学ぶために長崎へ行く19歳までを過ごした家。
中津が育んだ偉大なる福澤諭吉(慶應義塾の創始者)、起居した母屋と自ら改修し勉学に励んだ土蔵が残っています。
-
お 大迫磨崖仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
豊後大野市千歳町長峰1526
高さ3.2mもの大日如来石胎塑像が凝灰岩の壁に彫られている。
国道57号沿いに石灰岩でできた洞窟があり、浮き彫りの磨崖仏を見ることができる。高さ約3m、石芯塑像という珍
-
き キリシタン墓地
- [ 歴史 ]
-
由布市湯布院町川上716
大分県下では最大の墓碑群。
湯布院のキリシタンは、天正8(1580)年、奴留湯氏が領民2000人とともに洗礼を受けたのが最初で、この地
-
い 一心寺(大分市)
- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 ]
-
大分市廻栖野1305
 [ 紅葉時期 10月下旬~11月中旬 ]
[ 紅葉時期 10月下旬~11月中旬 ]1963年(昭和38年)に建立された寺。
本堂には1250(建長2)年の作とされる不動尊のほか、国宝級の仏像2体が安置され、身の丈20mという日本有
-
じ 自性寺大雅堂
- [ 寺院 ]
-
中津市新魚町3-1903
新魚町にある中津藩主・奥平氏の菩提寺。
藩主奥平家の菩提寺で、南画の大家・池大雅(いけのたいが)の書画約50点を展示。十代藩主・昌高公が「大雅堂」
-
つ 月隈公園
- [ 城 | 歴史 | 公園 ]
-
日田市丸山2-2-1
日田三丘(日隈・月隈・星隈)の一つで永山城跡。
古くは月隈山と呼ばれ、丸山や長山・永山とも呼ばれる。関ヶ原の戦いで手柄を立てた小川光氏が築いた永山城の跡。
-
き 旧竹田荘
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
竹田市竹田2069
江戸時代の文人画家、田能村竹田(たのむらちくでん)の邸宅。
江戸時代の文人画家、豊後南画の祖、田能村竹田の邸宅。田能村竹田は、岡藩の藩校由学館(ゆいがくかん)の学頭(