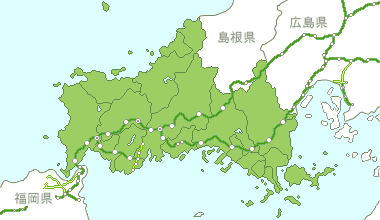神社・寺院・歴史 一覧

-
き 錦帯橋

- [ 歴史的建造物 | 橋 | 桜 ]

-
岩国市岩国
1673年(延宝元)、吉川広嘉によって架けられた、木造五連のアーチが美しい橋(名勝)。長さ193.3m、幅
-
る 瑠璃光寺五重塔

- [ 寺院 ]

-
山口市香山町7-1
日本三名塔に数えられる、国宝
25代大内義弘の菩提を弔うために弟の盛見が建立を計画し、1442(嘉吉2)年に竣工。国宝の五重塔は塔高31
-
い 岩国城

- [ 城 | 歴史 | 展望台 | 日の出 ]

-
岩国市横山
吉川広家によって築城。
吉香公園背後、標高200mの城山山頂にそびえる白亜の天守は、桃山風南蛮造で3層4階の上に物見を置く珍しいも
-
ろ 老僧岩
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 自然 | パワースポット ]
-
下関市勝山井田
地蔵菩薩が祀られた霊験道場。約650年前五百羅漢の一体がここに現われたと伝えられ、社の裏に大岩があり、その
-
き 旧目加田家住宅
- [ 歴史的建造物 ]

-
岩国市横山2
吉香公園にあり、江戸時代中期に建てられた入母屋造で一部2階建ての屋敷。中級武士の屋敷の数少ない遺構として、
-
ほ 防府天満宮

- [ 神社 | 初詣スポット | 桜 | 梅 | パワースポット ]

-
防府市松崎町14-1
日本で最初に創建された天神様
菅原道真を学問の神様として祭った天満宮。市街が一望できる高台にあり、梅と桜の名所。歴史館では重要文化財を展
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]
-
下関市一の宮住吉1-11-1
住吉神社は神功[じんぐう]皇后の創建と伝わる長門一の宮。
表筒男命・中筒男命・底筒男命の住吉三神などを祭る古寺。大内弘世創建の9間社流造りの本殿は国宝指定。毛利元成
-
き 北向地蔵尊
- [ 碑・像・塚・石仏群 | パワースポット ]

-
宇部市西岐波区上片倉
年間20万人もの参拝客があるという願掛け地蔵。
腰から下の病にご利益があるといわれる、ありがたいお地蔵様。地蔵の前に焚かれた線香の煙を、体の治したいところ
- [ 歴史的建造物 ]

-
萩市呉服町
維新の三傑木戸孝允(桂小五郎)旧宅
江戸屋横町にある、木戸孝允(桂小五郎)の生家。当時としては珍しい木造2階建て桟瓦葺きで、12室もの部屋があ
-
ま 麻羅観音
- [ 観音 | 珍スポット B級スポット ]
-
長門市俵山下安田
長門市にある男根奉納の寺。中国地方の太守、大内義隆公の遺児が女装して追っ手から逃れ、潜んでいたが、見つかっ
-
り 龍蔵寺
- [ 寺院 | 紅葉 | 花 ]
-
山口市吉敷1750
 [ 紅葉時期 11月中旬~12月上旬 ]
[ 紅葉時期 11月中旬~12月上旬 ]牡丹と紅葉が見事なお寺
湯田温泉街の北西約4kmの山あいに立つ、約1300年前に役行者[えんのぎょうじゃ]が開いたと伝わる古刹。宝
-
く 鞍掛城跡
- [ 城 | 歴史 ]
-
岩国市玖珂町鞍掛
中世末期の戦国武将、杉隆泰の居城跡。弘治元(1555)年、毛利軍に攻められ、隆泰以下城兵数千名が死に、落城
-
れ 歴史の道 萩往還

- [ 歴史街道 ]
-
萩市明木~佐々並
藩主毛利氏が江戸への参勤交代で通った道。
萩往還は、日本海側の萩(萩市)と瀬戸内海側の三田尻港(防府市)をほぼ直線で結び、全長はおよそ53km。高杉
-
ご 護国寺のショウブ
- [ 寺院 | 花 ]
-
防府市本橋町2-11
毎年シーズンになると、約2000本のショウブが咲く。
種田山頭火の墓所である護国寺では、毎年シーズンになると、約2000本のショウブが咲く。県指定の文化財、鎌倉
-
も 森田家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
萩市黒川503
名字帯刀を許され、庄屋を務めていた吉見家浪人森田対馬の屋敷跡。国の重要文化財。
- [ 寺院 ]
-
下関市豊北町神田肥中
肥中漁港を望む古寺は、一族の滅亡を夢で知らされた大内義隆夫人が建立。境内には新名木百選に選ばれたイブキ(高
-
く 口羽家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
萩市堀内
口羽家(禄高1018石余)では萩城下に残る上級武士の現存する屋敷として最も古く、主屋は18世紀末から19世
-
ば 幕末維新村展示館
- [ 歴史 | テーマパーク・遊園地 | 博物館・資料館 | 見学 ]
-
下関市赤間町4-9
幕末の志士に関する資料館。
坂本龍馬や高杉晋作の愛用の品、ゆかりのスポットを再現した展示など、当時の様子を知ることができる。下関の名産
-
と 東光寺(萩市)
- [ 寺院 | 初詣スポット | 紅葉 | パワースポット ]

-
萩市椿東1647
 [ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]毛利の菩提寺東光寺
長州藩3代藩主、毛利吉就が1691(元禄4)年に創建した名刹。毛利家の菩提寺で、3代から11代の斉元まで奇
-
の 野山獄跡
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
萩市今古萩町
江戸時代の牢獄跡で、野山獄が上士[じょうし]、岩倉獄が下士[かし]用だった。
安政元(1854)年、海外渡航に失敗した吉田松陰が投じられた獄屋敷跡。松陰は投獄中も囚人たちに孟子を講じて
- [ 城 | 歴史 | 公園 | 桜 ]

-
萩市堀内
幕末を偲ぶ萩城跡
慶長9年(1604年)に毛利輝元が指月山麓に築城したことから、別名指月城(しづきじょう)とも呼ばれていた萩
-
ふ 普賢寺(光市)
- [ 寺院 ]
-
光市室積8-6-1
「海の守り菩薩」として広く信仰を集めている寺。
寛弘3(1006)年に創建。開基は播州書写山円教寺の性空上人。普賢堂に安置されている普賢菩薩は、海中から出
-
き 木戸孝允旧宅
- [ 歴史的建造物 | 歴史 | 庭園 ]
-
萩市呉服町2
明治維新の三傑の一人、木戸孝允、別名・桂小五郎の生家。萩藩医・和田昌景の長男として生まれた家だったので、患
-
は 萩の町並み
- [ 歴史街道 ]

-
萩市江向510
今も江戸時代に絵地図で歩ける町萩
慶長9年(1604年)、毛利輝元が萩城を築いてから13代260年にわたって栄えた城下町。上級武士が屋敷を構
-
す 末広稲荷神社
- [ 神社 | 稲荷 ]
-
下関市赤間町5
幕末の志士たちが闊歩したと言われる末広稲荷神社
高杉晋作や伊藤博文、坂本龍馬らも足を運んだといわれる繁華街「稲荷町」の面影が残る神社。参道には朱塗りの鳥居
-
に 二尊院(長門市)
- [ 寺院 B級スポット ]
-
長門市油谷向津具下3539
楊貴妃伝説のお寺。
楊貴妃伝説が語り継がれ、安産、子宝、縁結びの寺として多くの参拝がある。その昔、絶世の美女「楊貴妃」が難を逃
-
し 松陰神社(萩市)
- [ 神社 | パワースポット ]
-
萩市椿東松本
吉田松陰を祭る神社。
近代日本の幕開け、明治維新に尽力した吉田松陰を祀る神社。学問の神として庶民の信仰が厚く、本殿の北隣には門下
-
と 徳佐八幡宮
- [ 神社 | 桜 ]
-
山口市阿東徳佐中
1182年(平安時代末期)大内満盛が宇佐八幡宮より徳佐八幡宮を勧請する。1788年。毛利氏により現在の社殿
-
か 覚苑寺
- [ 桜 | 紅葉 | 梅 | 寺院 ]
-
下関市長府安養寺3-3-10
 [ 紅葉時期 11月中旬~12月中旬 ]
[ 紅葉時期 11月中旬~12月中旬 ]3代毛利藩主綱元が建てた黄檗宗の寺院。
功山寺・笑山寺とともに長府毛利家の菩提寺として知られています。境内には長府出身の歌人・生田蝶介の歌碑と共に
-
や 山口大神宮
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]
-
山口市滝町4-4
永正17年(1520年)、大内氏30代目の大内義興が伊勢神宮の神霊を勧請して創建し「西の伊勢神宮」ともよば