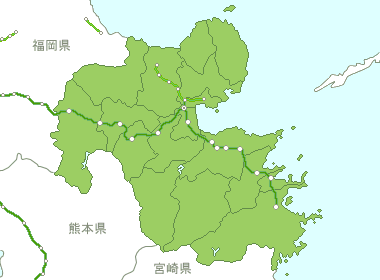神社・寺院・歴史 一覧

-
あ 愛染堂
- [ 寺院 | 歴史 ]
-
竹田市寺町八幡山1773
1635年(寛永12)、岡藩2代藩主・中川久盛が建立。
願成院の本堂として建てられた。堂宇は、軒下の四隅に天邪鬼[あまのじゃく]や人面の彫刻が施された木造宝形造り
- [ 歴史 | 公園 ]

-
国東市国東町安国寺1639-2
弥生時代のムラにタイムスリップ
弥生時代のムラや環境を復元するとともに、体験を通して楽しく学べる施設を整備した史跡公園。4万3000平方メ
-
い 磯矢邸
- [ 歴史的建造物 ]
-
杵築市杵築211-1
旧加藤与五右衛門の屋敷。
加藤与五右衛門の屋敷で大正5年に磯矢氏が買い取り、平成6年に杵築市に寄贈。藩主の休息所である御用屋敷の一部
-
い 岩戸寺
- [ 寺院 ]
-
国東市国東町岩戸寺1232
養老3(719)年に仁聞菩薩が開いたと伝えられる山寺。
旧正月7日に修正鬼会[しゅじょうおにえ]の祭礼が成仏寺と一年交替で行われる。本尊の薬師如来坐像は平安後期の
-
い 一心寺(大分市)
- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 ]
-
大分市廻栖野1305
 [ 紅葉時期 10月下旬~11月中旬 ]
[ 紅葉時期 10月下旬~11月中旬 ]1963年(昭和38年)に建立された寺。
本堂には1250(建長2)年の作とされる不動尊のほか、国宝級の仏像2体が安置され、身の丈20mという日本有
-
い 今市の石畳
- [ 歴史街道 | 歴史 ]
-
大分市今市
全長660m、道幅8mの未舗装道路の真ん中に幅2mの石畳が続いている。
昔肥後街道の宿場町として栄え肥後藩主細川氏と岡藩主中川氏の参勤交代に使われた道路で、本陣、脇本陣、茶屋、代
-
い 岩屋寺石仏
- [ 寺院 | 碑・像・塚・石仏群 ]
-
大分市古国府1-4
大分市古国府にある平安時代後期(11世紀中頃)の磨崖仏。
上野丘の中腹に刻まれている石仏。17体の仏像からなり、薬師如来座像を中尊とした薬師三尊像の左右に、釈迦三尊
-
う 臼杵城址
- [ 城 | 歴史 | 公園 | 桜 ]
-
臼杵市臼杵丹生島91-1
大友宗麟が臼杵湾に浮かぶ丹生島(にうじま)に築いた海城。
大友宗麟によって弘治2(1556)年に築かれていた臼杵城。島の形が亀に似ていたことから別名亀城(きじょう)
- [ 神社 | パワースポット ]
-
由布市湯布院町川上2220
「六所様」と呼ばれ親しまれている神社。
六所とは、奉祭する六柱の神々を表しています。広さ約2万平方メートルの境内には樹齢300年を超える杉の御神木
-
う 宇佐神宮

- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]

-
宇佐市南宇佐2859
神輿の起源は宇佐にあり。全国4万余社の八幡社の総本宮、宇佐神宮。
1400年前に創建された、全国に4万を超える八幡宮の総本社。通称として宇佐八幡・宇佐八幡宮とも呼ばれる。本
-
う 臼杵石仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 | パワースポット | 珍スポット ]

-
臼杵市深田
時をかける御仏の心(4群59体の磨崖仏)
深田の山肌に彫られた磨崖仏群。ホキ石仏第一群・第二群、山王山石仏、古園石仏の4群に大別される。平安時代後期
-
え 英雄寺のボタン
- [ 寺院 | 花 ]
-
竹田市会々2033
数百の朝鮮ボタンが、毎年色鮮やかな花を咲かせます。
英雄寺は、中川二代久盛公が祖父佐久間玄蕃の菩提を弔うため、寛永21年(1644)建立。安産地蔵でも知られて
-
お 小倉磨崖石塔
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
佐伯市弥生上小倉
磨崖面に、25mにわたって刻まれた石塔。
弥生地域の中心部にある石塔で鎌倉期から南北朝期の作とされる。宝塔8塔、五重塔34基の合計42基が、25mに
-
お 小鹿田焼窯元
- [ 歴史 ]
-
日田市源栄町皿山
江戸時代中期の1705(宝永2)年開窯の民陶の里。
きれいに揃った刷毛目や飛び鉋と呼ばれる独特の幾何学的紋様に特色がある。現在は10軒の窯元があるが、全てが開
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
豊後大野市緒方町久土知
向かって右山に宮迫東石仏、左山に西石仏がある。
いずれも熔結凝灰岩の露出した崖面に横長の仏龕を穿ち、その奥壁に仏躰を浮き彫りにし、仏龕の前面には覆屋を差し
-
お 大野老松天満社
- [ 神社 ]
-
日田市前津江町大野833
社伝では延久3年(1071)大蔵永季の創建で菅原道真を祀る。
延久3(1071)年創建の三間社流造りの古社で、津江山系に7つある老松天満の一つ。現在の建物は長享2(14
-
お 大迫磨崖仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
豊後大野市千歳町長峰1526
高さ3.2mもの大日如来石胎塑像が凝灰岩の壁に彫られている。
国道57号沿いに石灰岩でできた洞窟があり、浮き彫りの磨崖仏を見ることができる。高さ約3m、石芯塑像という珍
-
お 大分縣護國神社
- [ 神社 | 初詣スポット | 桜 | 梅 ]

-
大分市牧1371
大分市の中央部、小山、松栄山の中腹にある神社。
展望台からは大分市・別府湾が一望できる。大分県護国神社には多くの慰霊碑や西南戦争で亡くなった軍人や警官の墓
-
お 大分元町石仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
大分市元町4609
平安時代後期(11世紀中頃)の磨崖仏。
大分市中心部に位置する上野丘の北東端、崖っぷちに建つ薬師堂内にある。石仏群は凝灰岩に刻まれている。中心は、
-
お 温泉山 永福寺
- [ 寺院 ]
-
別府市風呂本1
一遍上人ゆかりの温泉山永福寺。
鉄輪温泉を開いたとされる一遍上人が開祖の寺院。秋のお彼岸に行なわれる湯あみ祭りは全国的にも珍しい。鉄輪にあ
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
大分市府内町2-2-1
大分銀行本店として大正2(1913)年に完成したもの。
大正2年(1913年)に旧第二十三国立銀行本店として建てられ、大分銀行本店となった後、現在は大分銀行ローン
-
お 大原邸
- [ 歴史的建造物 | 庭園 ]

-
杵築市杵築207番地
杵築そぞろは時間(とき)の旅こころがゆっくり遡る・・・
北台に立つ重臣屋敷の代表格で、その格式は杵築一と評される。松平藩の家老を勤めた大原氏の屋敷で、重厚な門構え
-
お 岡城跡

- [ 城 | 歴史 | 桜 | 紅葉 ]

-
竹田市竹田
 [ 紅葉時期 11月上旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 11月上旬~11月下旬 ]名曲「荒城の月」のモチーフとなった城跡。春は桜、秋は紅葉の名所。
別名「臥牛城」。標高325mにあり、谷底との高低差は約100m、島津軍を退けた堅城として有名。文治元(11
-
か 観音寺の十六羅漢
- [ 寺院 | 碑・像・塚・石仏群 ]
-
竹田市寺町八幡山1782
観音寺への参道の石段の右側、自然石の上に石造十六羅漢が並んでいます。
十六羅漢が並ぶ坂道を上ったところに観音寺がある。十六羅漢は仏法を守ることを誓った16人の仏弟子を指すといわ
-
か 咸宜園跡
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
日田市淡窓2-2-13
江戸時代・広瀬淡窓によって、天領であった(現日田市)に文化2年(1805年)創立した全寮制の私塾。
文化4年(1807年)に桂林荘塾舎(桂林園・現在の桂林荘公園)を設置した後、淡窓は、文化14年(1817年
-
か 神尾家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
中津市山国町守実120
1771年(明和8)に建築された九州最古の木造住宅。
江戸時代に組頭をつとめた旧家で、明和8(1771)年に建てられたとの記録があり、年代のわかる九州最古の民家
-
か 川中不動・天念寺
- [ 寺院 | 不動 ]
-
豊後高田市長岩屋1149-1152
長岩屋川の中にある巨岩に刻まれた不動三尊。
天念寺岩峰と呼ばれる奇岩を背に寺が建つ。養老2(718)年に開かれたと伝えられ、藤原時代の仏像4体を安置。
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 | 博物館・資料館 | 公園 ]
-
大分市里646-1
国の史跡の亀塚古墳を中心とする公園。
5世紀初めに造られた、県下最大規模の前方後円墳である亀塚古墳(国指定史跡)と一体化したガイダンス施設で、出
- [ 教会 ]
-
別府市末広町1-14
1950年にサレジオ修道会によって建立され、運営。
聖フランシスコ・ザビエル渡来400年記念に際して、1950年12月17日に落成。フランスのルルドにある教会
-
き 旧丸毛家住宅
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
臼杵市海添本了13
臼杵藩時代稲葉氏の家臣として代々仕えた丸毛氏の屋敷。
江戸後期の建築様式をとどめた上級武士の屋敷。建物内で「表玄関」と「内玄関」に分けられるなど、臼杵の武家屋敷