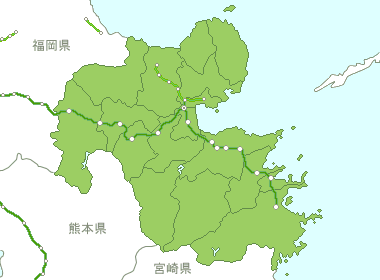神社・寺院・歴史 一覧

-
か 川中不動・天念寺
- [ 寺院 | 不動 ]
-
豊後高田市長岩屋1149-1152
長岩屋川の中にある巨岩に刻まれた不動三尊。
天念寺岩峰と呼ばれる奇岩を背に寺が建つ。養老2(718)年に開かれたと伝えられ、藤原時代の仏像4体を安置。
-
さ 佐野家
- [ 歴史的建造物 ]
-
杵築市杵築329-1
代々医師で藩医を務めた佐野家。
杵築の城下町の中で最も古い木造建築といわれる。代々藩医を勤めた家柄で、城へのぼるための駕籠が玄関に吊るされ
-
ぶ 豊前善光寺
- [ 寺院 ]
-
宇佐市下時枝237
天徳2年(958年)、空也によって開創という日本三善光寺の一つ。
「芝原善光寺」とも呼ばれ、信濃、甲府と並ぶ日本三善光寺の一つ。天徳2(958)年に空也上人が開いたと伝えら
-
り 竜岩寺
- [ 寺院 ]
-
宇佐市院内町大門287
746年(天平18)、行基が開基したと伝わる古刹。
奥の院の礼堂は懸崖造りで、堂内には行基が一晩で刻んだという阿弥陀如来、薬師如来、不動明王の3体を安置。素木
-
き 菊畑公園
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 公園 ]
-
由布市湯布院町湯平473-14
野菊が咲いていたことから名付けられた公園。
公園内には種田山頭火の句碑や菊池幽芳の歌碑、十三仏や八十八ヶ所仏、金比羅宮、修行太師や金比羅などがあり、全
-
く 熊野磨崖仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
豊後高田市田染平野2546
国東半島の地にある石肌に刻まれた不動明王像と大日如来像の二体の石仏
日本一雄大な石仏とも言われる石仏で、伝説上では718年に仁聞により造られたとされている。胎蔵寺から杉木立の
-
ま 真木大堂
- [ 寺院 | 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
豊後高田市田染真木1796
かつて六郷山寺院の学問所であった古刹伝乗寺の跡
六郷満山65ヶ寺のうち、本山本寺の一つとして最大寺院だった伝乗寺の跡。収蔵庫には大威徳明王像をはじめ、衰退
-
お 温泉山 永福寺
- [ 寺院 ]
-
別府市風呂本1
一遍上人ゆかりの温泉山永福寺。
鉄輪温泉を開いたとされる一遍上人が開祖の寺院。秋のお彼岸に行なわれる湯あみ祭りは全国的にも珍しい。鉄輪にあ
-
き 杵築城下町
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
杵築市杵築
日本唯一のサンドイッチ型城下町。
南北の高台に武士が住み、その谷あいに商人が住んだ段差のある日本唯一の「サンドイッチ型城下町」。酢屋の坂をは
-
な 中塚不動尊
- [ 不動 | 花 ]
-
玖珠郡玖珠町山下田能原
巨大な自然岩を御神体として祀っている。
中塚不動明王は商売繁盛、無病息災、交通安全、家内安全などの御利益があります。毎年6月中旬から7月中旬には、
-
ほ 帆足本家・富春館
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]

-
大分市中戸次4381
幕末から明治にかけて酒造業を営み繁栄した『帆足本家』
2000坪の敷地に、帆足本家が江戸末期から明治にかけて建築した建物が点在。かつて文化人たちで賑わったサロン
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
豊後大野市緒方町久土知
向かって右山に宮迫東石仏、左山に西石仏がある。
いずれも熔結凝灰岩の露出した崖面に横長の仏龕を穿ち、その奥壁に仏躰を浮き彫りにし、仏龕の前面には覆屋を差し
-
お 大分元町石仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
大分市元町4609
平安時代後期(11世紀中頃)の磨崖仏。
大分市中心部に位置する上野丘の北東端、崖っぷちに建つ薬師堂内にある。石仏群は凝灰岩に刻まれている。中心は、
-
ゆ 湯の花小屋
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
別府市明礬
湯の花を採取する小屋。
明礬温泉に並ぶ萱葺き屋根(湯のしずくが落ちるのを防ぐため)の小屋は、江戸時代から続く湯の花の採取所。温泉の
-
か 観音寺の十六羅漢
- [ 寺院 | 碑・像・塚・石仏群 ]
-
竹田市寺町八幡山1782
観音寺への参道の石段の右側、自然石の上に石造十六羅漢が並んでいます。
十六羅漢が並ぶ坂道を上ったところに観音寺がある。十六羅漢は仏法を守ることを誓った16人の仏弟子を指すといわ
-
き 旧矢羽田家住宅
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
日田市大山町西大山3603-3
江戸時代に建築された組頭の住宅。
江戸時代中期に熊本県北部から中部にかけて見られた二棟造りの農家を解体して大山文化センターの隣りに移築、復元
-
み 南台武家屋敷跡
- [ 歴史的建造物 ]
-
杵築市南台
塀などに往時の面影を残しています。
文久2(1862)年建築の家老中根源右衛門の屋敷とともに多くの土塀、門が残されています。裏丁周辺は、高い石
-
い 今市の石畳
- [ 歴史街道 | 歴史 ]
-
大分市今市
全長660m、道幅8mの未舗装道路の真ん中に幅2mの石畳が続いている。
昔肥後街道の宿場町として栄え肥後藩主細川氏と岡藩主中川氏の参勤交代に使われた道路で、本陣、脇本陣、茶屋、代
-
お 小鹿田焼窯元
- [ 歴史 ]
-
日田市源栄町皿山
江戸時代中期の1705(宝永2)年開窯の民陶の里。
きれいに揃った刷毛目や飛び鉋と呼ばれる独特の幾何学的紋様に特色がある。現在は10軒の窯元があるが、全てが開
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
臼杵市祇園洲6-6
臼杵の旧藩主である稲葉家の屋敷を一般公開。
明治35(1902)年に、東京に居を移した稲葉氏が里帰り用の住居として建てた。書院造りの屋敷内には、稲葉家
-
た 高瀬石仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
大分市高瀬901-1
大分市内で国の史跡に指定される代表的なもの。
大分市内を流れる大分川の支流、七瀬川南岸の丘陵地の洞窟内にある凝灰岩を掘り込んだ石窟の中に彫り出された石仏
-
さ 佐伯城址・鶴屋城
- [ 城 | 歴史 ]
-
佐伯市駅前2-6-30
国木田独歩の「源叔父」の舞台になった城跡。
1602年(慶長7年)から1606年(慶長11年)の6年の歳月をかけて、八幡山に築かれた山城跡。現在も「黒
-
く 草野本家
- [ 歴史的建造物 ]
-
日田市豆田町11-4
県内最古の商家分で大県の有形文化財に指定されている。
郡代御用達を務めた旧家で、ひなまつり、端午の節句、祇園祭、天領まつりの年4回だけ開放され、江戸時代の人形や
-
ま 豆田町
- [ 歴史的建造物 | 歴史街道 | 歴史 ]
-
日田市豆田町
天領日田の面影を残した白壁の町並み。
天領の町として栄えた日田市内隈町と豆田町には、往時の繁栄を偲ぶ町並みが残っていまする。町内には飲食店やみや
-
み 水掛け地蔵
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
由布市湯布院町湯平
湯平温泉街の石畳手前の橋を右へ渡り、正面の山道の階段を上ると川沿いに12体の地蔵があり、水をかけると願いが
-
よ 四日市横穴古墳群
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
宇佐市四日市
百数十穴もある古墳群で、一部分彩色壁画がある。
加賀山と呼ばれる丘陵の凝灰岩の斜面にあり、161基の横穴墓が確認されている。
-
か 咸宜園跡
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
日田市淡窓2-2-13
江戸時代・広瀬淡窓によって、天領であった(現日田市)に文化2年(1805年)創立した全寮制の私塾。
文化4年(1807年)に桂林荘塾舎(桂林園・現在の桂林荘公園)を設置した後、淡窓は、文化14年(1817年
-
し 松屋寺
- [ 寺院 ]
-
速見郡日出町1921
本堂の前庭には、日本一と名高い大蘇鉄がある。
曹洞宗の寺で、1607(慶長12)年に初代藩主延俊が建立した木下家の菩提寺。日出藩木下家の菩提寺である松屋
-
り 竜原寺
- [ 寺院 ]
-
臼杵市福良平清水134
慶長5(1600)年に稲葉初代藩主が建立。
境内には10年の歳月をかけ、安政5年(1858年)に竣工した県指定有形文化財の三重塔がある。聖徳太子像を安
-
よ 暘谷城趾
- [ 城 | 歴史 | 遊歩道 ]
-
速見郡日出町2610
1602年(慶長7)、木下延俊が築城。
慶長6(1601)年、秀吉の妻ねねの甥にあたる木下延俊が築城。現在、その姿は石垣を残すのみとなっている。城