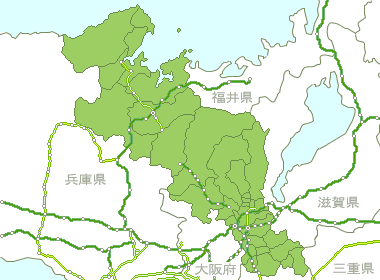神社・寺院・歴史 一覧

-
い 一言寺
- [ 寺院 ]
-
京都市伏見区醍醐一言寺裏町3
醍醐寺の塔頭で正しくは金剛王院。
阿波内侍の開基により創建されたと伝えらる。本尊の千手観音は、ひと言だけ念じて祈願すれば即座に叶うという言い
-
え 厭離庵
- [ 寺院 | 紅葉 ]
-
京都市右京区嵯峨二尊院門前善光寺山町2
「小倉百人一首」の藤原定家(ふじはらていか)ゆかりの非公開寺。
現在の本堂、茶室の時雨亭は明治になって、貴族院議員であった白木屋社長(大村彦太郎)によって建立されたもの。
-
お 愛宕念仏寺
- [ 寺院 | 紅葉 | 珍スポット ]
-
京都市右京区嵯峨鳥居本深谷町2-5
嵯峨野めぐりの始発点、愛宕山の参道のふもとにある寺院。
本尊は千手観音。平安朝の初め、鴨川の洪水で堂宇が流失したため、天台宗の僧「千観内供」により再興され、比叡山
-
か 桂離宮
- [ 歴史的建造物 | 庭園 ]
-
京都市西京区桂御園
回遊式の庭園は日本庭園の傑作。
八条宮家の智仁親王が、「瓜畠のかろき茶屋」と呼ぶ簡素な建物を営んだのに始まる。広大な庭園には、古書院、中書
- [ 神社 | 珍スポット B級スポット ]
-
京都市右京区太秦森ケ東町
日本で唯一の三方が正面となる三柱鳥居がある。
通称木嶋神社(このしまじんじゃ)。また、本殿東側に織物の始祖を祀る蚕養(こかい)神社があることから蚕の社(
-
さ 鷺森神社
- [ 神社 | 紅葉 ]
-
京都市左京区修学院宮ノ脇町16
比叡山山麓の七里の産土神。
貞観年間(859年-877年)の間に創建されたと伝わり、スサノオノミコトを祭神とする。西側の200mにも及
-
し 真如院
- [ 寺院 | 庭園 ]
-
京都市下京区猪熊通五条上ル
織田信長が、将軍足利義昭を本院に招くために作庭した庭だったものを、院の移築にともない庭も昭和三十六年に復元
- [ 神社 ]
-
京田辺市大住池平31
平城天皇が大同4年(809)の譲位後、宮殿を平安京から平城京へ遷さんとせられし時、造宮使がその途、大住山に
-
と 東福寺 方丈庭園
- [ 寺院 | 庭園 ]

-
京都市東山区本町15-778
庭園は1938(昭和13)年、重森三玲氏が作庭。
禅宗の方丈には数々の庭園が残されているが、方丈の四周に庭園(方丈南庭・方丈西庭・方丈北庭・方丈東庭)がある
-
と 東寺 観智院
- [ 寺院 ]

-
京都市南区八条通大宮西入ル九条町403
東寺の塔頭寺院で、別格本山となっている。
学僧であった杲宝(ごうほう)を1世として延文4年(1359年)に子院として創建された。観智院客殿(桃山時代
-
な 南陽院
- [ 寺院 ]
-
京都市左京区南禅寺福地町33
南禅寺の塔頭の一つ。
南禅寺南門の側にある。一般公開はしていない。
-
に 仁和寺

- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 ]

-
京都市右京区御室大内33
 [ 紅葉時期 11月上旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 11月上旬~11月下旬 ]宇多天皇が平安時代に創建した真言宗御室派の総本山。
国宝の金堂をはじめ、左右に金剛力士像を安置する仁王門、旧御室御所、五重塔など数多くの堂塔が立ち並ぶ。本尊は
-
の 野宮神社
- [ 神社 ]
-
京都市右京区嵯峨野宮町1
伊勢神宮へ赴く斎宮に選ばれた皇女が、3年間こもって心身を清めたという古社。鳥居は樹皮がついたままの「黒木の
-
ほ 宝厳院
- [ 寺院 | 庭園 | 紅葉 ]

-
京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町36
臨済宗天龍寺派の寺院で天龍寺の塔頭。
寛正2年(1461年)、細川頼之が聖仲永光を開山に招聘して創建。応仁の乱(1467年-1477年)に巻き込
-
み 壬生寺
- [ 寺院 | 初詣スポット ]

-
京都市中京区坊城通仏光寺上ル壬生梛ノ宮町31
園城寺(三井寺)の僧快賢が、991年(正暦2年)に自身の母のために建立したと伝わる。中世に寺を再興した円覚
-
お 大原の町並み
- [ 道・通り・街 | 歴史 ]
-
京都市左京区大原勝林院町、大原来迎院町
比叡山西麓高野川上流部に、茅葺き屋根の民家がまだ何軒も残るのどかな山里で、平安京(京都)と若狭湾を結ぶ若狭
-
か 首途八幡宮
- [ 神社 ]
-
京都市上京区智恵光院通今出川上ル桜井町
宇佐神宮(大分県宇佐市)から八幡大神を勧請したのが始まりと伝えられる。誉田別尊(応神天皇)・息長帯姫命(神
- [ 寺院 | 観音 | 桜 ]
-
京田辺市普賢寺下大門13
天武天皇の御代に創建された古刹
大御堂に安置している十一面観音立像は国宝に指定されている。天平時代の華やかさを伝える貴重なもの。桜の名所と
-
け 桂春院
- [ 寺院 | 庭園 ]
-
京都市右京区花園寺ノ中町11
1598(慶長3)年に創建された妙心寺の塔頭。
「清浄の庭」「思惟の庭」「真如の庭」「侘の庭」と呼ばれる4つの枯山水庭園がある。いずれも国の史跡、名勝に指
-
こ 弘源寺
- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 | 花 ]

-
京都市右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町65
臨済宗・天龍寺塔頭の小寺。
永享元年(1429年)室町幕府の官領であった細川右京太夫持之が、天龍寺開山である夢窓国師の法孫にあたる玉岫
-
ご 欣浄寺
- [ 寺院 ]
-
京都市伏見区西桝屋町1038
鎌倉時代の僧・道元ゆかりの地。
伏見大仏欣浄寺ともいわれる、清涼山と号する曹洞宗の寺院。道元の「深草閑居の史跡」ともいわれる。本尊は木像の
- [ 寺院 | パワースポット ]
-
京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町46
「融通念仏の道場」として知られている。
本尊で国宝でもある釈迦如来像は、若き日の釈迦の姿を彫ったものと伝えられ、一般に嵯峨釈迦堂の名で親しまれる浄
-
た 滝口寺
- [ 寺院 ]
-
京都市右京区嵯峨亀山町10-4
鎌倉時代創建の三宝寺の跡地に、法然の弟子念仏房良鎮が開創した浄土宗の寺。堂内に『平家物語』で知られる滝口入
-
だ 大将軍八神社
- [ 神社 ]

-
京都市上京区一条通御前西入ル西町48
素戔鳴尊を祭神とする神社。
祭神は大将軍(素戔鳴尊)・太歳神(天忍穂耳命)・大陰神(市杵嶋姫命)・歳刑神(田心媛命)・歳破神(湍津姫命
-
て 寺田屋
- [ 歴史 ]
-
京都市伏見区南浜町263
京橋付近に立つ伏見の船宿。
寺田屋騒動で知られ、宿の東に位置する寺田屋旧跡には、「薩摩九烈士遺跡碑」がある。この事件後には、坂本龍馬が
-
な 梨木神社
- [ 神社 | 名水 | 花 ]
-
京都市上京区寺町通広小路上ル染殿町680
幕末の公家、三條実万・実美を祀る社。
京都御苑の東に立つ三條実万・実美父子をまつる神社で、参道には500株の萩があり、京を代表する萩の名所境内に
-
ほ 法然院
- [ 寺院 ]
-
京都市左京区鹿ヶ谷御所ノ段町30
法然上人ゆかりの寺。
阿弥陀如来を本尊とし、境内に本堂、経蔵、書院、鐘楼などが立つ。墓地には谷崎潤一郎など著名人の墓がある。
-
り 龍源院
- [ 寺院 | 庭園 ]
-
京都市北区紫野大徳寺町82-1 大徳寺山内
臨済宗大本山大徳寺の塔頭。
文亀2年(1502年)に東渓宗牧を開山として、能登の畠山義元・豊後の大友義長らが創建。明治の初めに神仏分離
-
ろ 廬山寺
- [ 寺院 ]
-
京都市上京区寺町通広小路上ル
圓浄宗の本山で本尊は阿弥陀如来。
紫式部の邸宅跡と知られ『源氏物語』などの作品が書かれたとも伝わる古寺。本堂には紫式部関連の史料を展示してい
- [ 神社 ]
-
京都市右京区嵯峨愛宕町1
山城・丹波国境の愛宕山(標高924メートル)山頂にある神社。
全国約900社の愛宕神社の総本社。旧称阿多古神社、通称愛宕さん。祭神に火の神、迦倶土命を祀ることから、火伏