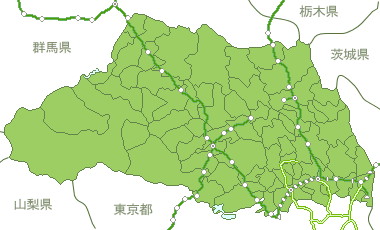神社・寺院・歴史 一覧

-
み 三峯神社
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]

-
秩父市三峰298-1
ヤマトタケル伝説やお犬様信仰など伝説が数多く残る
今から約1900年前、日本武尊の創建と伝えられており、寛文元(1661)年に建立された春日造りの本殿と、権
- [ 観音 | 歴史的建造物 | 歴史 | パワースポット B級スポット ]

-
所沢市上山口2203
弘法大師の開基といわれる真言宗の寺。
絵馬、天井一面の墨絵の竜、千手観音等が有名。他にも貴重な文化財が沢山ある。本尊の千手観音は秘仏で非公開。武
- [ 寺院 | 自然 | 紅葉 ]

-
新座市野火止3-1-1
 [ 紅葉時期 11月下旬~12月上旬 ]
[ 紅葉時期 11月下旬~12月上旬 ]関東地方でも名高い古刹。
平林寺の建造物を取り囲むように、約43haにも及ぶ国指定天然記念物「平林寺境内林」が広がっています。南北朝
-
ち 秩父神社

- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]

-
秩父市番場町1-1
秩父神社の例大祭「秩父夜祭」は、京都祇園祭、飛騨高山祭と共に日本三大曳山祭の1つ
秩父地方の総社で秩父三社(秩父神社・三峯神社・寳登山神社(宝登山神社))の一つ。八意思兼命(やごころおもい
-
か 川越氷川神社
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]

-
川越市宮下町2-11-3
太田道灌以来、川越の総鎮守とされ歴代川越藩主の篤い崇敬を受けた。
「縁結び」「家庭円満」の神様を祀る。『境内の小石を持ち帰り大切にすると良縁に恵まれる』との言い伝えがあり、
- [ 寺院 | 不動 ]

-
所沢市上山口2214
狭山不動尊の名で親しまれる天台宗の寺。
自然豊かな狭山丘陵に狭山山不動寺が開山したのは、昭和50(1975)年4月。桃山時代の多宝塔は県の有形文化
- [ 寺院 ]
-
秩父郡横瀬町横瀬2160
安産子育ての観音として有名。
建久2年(1191)明智禅師の開創と伝えられる札所9番の古刹。毎年1・8月の16日(縁日)は安産、子育て祈
-
せ 仙波東照宮
- [ 神社 ]

-
川越市小仙波町1-21-1
喜多院の南側に、元和3(1617)年に建立された。本殿には木像の家康公像が祀られている。日光東照宮・久能山
- [ 寺院 | 花 | 紅葉 ]

-
所沢市中富1501
祈願所・鎮守の宮として創建された真言宗の寺。本堂の本尊は大日如来、また毘沙門堂には、かつて武田信玄の守り本
- [ 神社 ]

-
所沢市中富1507
通称「富(とめ)の神明様」として親しまれている。近隣地域より神明社を含む後述の「合祀七神社」を勧請し、18
- [ 神社 ]

-
川越市小仙波町1-4
喜多院の鎮守社
平安時代の天長7年(830)、円仁(慈覚大師)が無量寿寺(後の喜多院)創建の際、その鎮守として比叡山坂本の
-
き 喜多院
- [ 寺院 | 初詣スポット | パワースポット ]

-
川越市小仙波町1-20-1
埼玉県川越市にある天台宗の寺院。山号は星野山(せいやさん)。
良源(慈恵大師、元三大師とも)を祀り川越大師の別名で知られ、境内にある五百羅漢の石像も有名である。徳川家康
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]

-
秩父郡長瀞町長瀞1828
神日本磐余彦尊(神武天皇)、大山祗神、火産霊神を祀る。縁起のいい名前「宝の山に登る」で、参拝者が絶えない。
-
と 時の鐘 岩槻
- [ 歴史的建造物 ]

-
さいたま市岩槻区本町6-229-1
毎日6時と18時に澄んだ音を響かせている。
埼玉県では川越の時の鐘が有名ですが岩槻にも時の鐘があります。岩槻城下の時の鐘は、寛文11年(1671)時の
-
か 川越城本丸御殿

- [ 城 | 歴史的建造物 | 歴史 ]

-
川越市郭町2-13-1
現存する本丸御殿は嘉永元(1848)年に時の藩主、松平斉典の17万石時代に建てられた入母屋造りで、豪壮な大
-
せ 浅間神社
- [ 神社 ]

-
所沢市荒幡748
富士信仰に基づいて富士山を神格化した浅間神を記紀神話に現れる木花咲耶姫命(このはなのさくやひめのみこと)と
-
さ さきたま古墳公園

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 公園 ]

-
行田市埼玉4834
県名「埼玉」はこの土地名に由来している。古墳群との調和の取れた観賞・保護、及び散策を目的とした公園の整備が
-
に 日光街道杉並木
- [ 歴史街道 ]

-
鶴ヶ島市大字高倉
杉並木と桜、散策道
日高市から鶴ヶ島市にかけての国道407号は「日光街道杉並木」という名称で杉並木が残っている。
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
入間郡毛呂山町大類535
鎌倉街道や流鏑馬祭りに関する郷土の資料を展示。
原始から近世までの毛呂山町の資料を展示。学習室や図書室も完備。
-
つ 調神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
さいたま市浦和区岸町3
地元では調宮(つきのみや)の愛称で親しまれている。
創建はおよそ2000年前といわれる。「ツキ」を「月」にかけたことによる月待信仰が古来よりあり、狛犬ならぬコ
-
こ 高麗山 聖天院
- [ 寺院 | 桜 | 花 ]

-
日高市新堀990-1
高麗郡初代郡長の高麗王を弔い草創したと伝える寺。
本尊は不動明王(胎内仏弘法大師作)。別に高句麗佛聖天尊を祀る。境内は、5つの池を配した庭園をはじめ、5千本
-
し 勝願寺
- [ 寺院 ]
-
鴻巣市本町8-2-31
徳川家康ゆかりの寺で現在でも仁王門などに、将軍家の家紋である三つ葉葵の紋を見ることができる。5月には「なん
-
て 天岑寺
- [ 寺院 ]
-
狭山市沢5-34
桃山時代に開山の曹洞宗寺院。
旗本小笠原太郎左衛門安勝が父小笠原摂津守安元の菩提を弔うために文禄3年(1594年)に開基し、道元禅師から
-
り 龍穏寺
- [ 寺院 ]
-
入間郡越生町龍ヶ谷452
曹洞宗関東三寺のひとつ。
1830~40年(天保年間)の建立。本堂左手の斜面を上がると、太田道真、道灌父子など太田一族の墓がある。
-
い 伊奈氏屋敷跡
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
北足立郡伊奈町小室丸山
代官頭、伊奈備前守忠次が築いた屋敷跡。
楕円形の独立丘陵で、表門、蔵屋敷、陣屋などから井戸や裏門まで、当時のまま民有地となった屋敷跡に現存。
- [ 歴史的建造物 ]
-
さいたま市見沼区片柳1266-2
名主坂東家の住宅と環境が復元されている。
かつての農家の環境を再現した、野外博物館。生きている民家をテーマに「季節の行事」やそれにちなんだ展示、体験
-
た 玉敷神社
- [ 神社 | 花 | パワースポット ]
-
加須市騎西552
飛鳥時代末期、東山道鎮撫使・多次比真人三宅磨によっての創建と伝えられる式内社。埼玉県の元荒川流域を中心に数
-
れ 蓮馨寺
- [ 寺院 | パワースポット ]

-
川越市連雀町7-1
天文18年(1549年)、川越城主(武蔵国河越城主)大道寺政繁の母・蓮馨によって開基。厄除け、安産子育て、
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
草加市住吉1-11-29
旧草加小学校西校舎を改修した資料館。
大正時代の鉄筋コンクリート造りで、国の登録有形文化財。農具、里神楽などの民俗資料、土器や板碑、縄文時代の丸
-
か 金鑚神社
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]
-
児玉郡神川町二ノ宮751
本殿がなく、背後に続く御室ヶ獄(御獄山)を御神体とする珍しい神社。
日本武尊が東征の帰途、伊勢神宮にて倭姫命(やまとひめのみこと)より賜った火鑽金を御室ヶ獄に鎮め、天照大神と