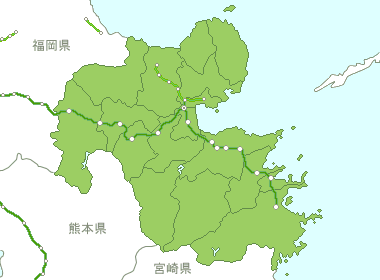神社・寺院・歴史 一覧

-
う 臼杵石仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 | パワースポット | 珍スポット ]

-
臼杵市深田
時をかける御仏の心(4群59体の磨崖仏)
深田の山肌に彫られた磨崖仏群。ホキ石仏第一群・第二群、山王山石仏、古園石仏の4群に大別される。平安時代後期
-
き 旧竹田荘
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
竹田市竹田2069
江戸時代の文人画家、田能村竹田(たのむらちくでん)の邸宅。
江戸時代の文人画家、豊後南画の祖、田能村竹田の邸宅。田能村竹田は、岡藩の藩校由学館(ゆいがくかん)の学頭(
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
中津市殿町1385
中津市にある歴史系の博物館。
昭和13(1938)年築の旧中津市立小幡記念図書館を利用した建物を利用する形で1992年(平成4年)6月に
-
も 文殊仙寺
- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 | パワースポット ]
-
国東市国東町大恩寺2432
 [ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]文殊山(617m)の中腹にある古刹。
日本三文殊のひとつに数えられていて、寺では「三人寄れば文殊の知恵」の発祥の地と称している。参道の入口には仁
-
う 臼杵城址
- [ 城 | 歴史 | 公園 | 桜 ]
-
臼杵市臼杵丹生島91-1
大友宗麟が臼杵湾に浮かぶ丹生島(にうじま)に築いた海城。
大友宗麟によって弘治2(1556)年に築かれていた臼杵城。島の形が亀に似ていたことから別名亀城(きじょう)
- [ 城 | 歴史 | 公園 | 桜 ]
-
大分市荷揚町74
1597年に石田三成の妹婿・福原直高が築城した城跡。
「府内」とは大分の別称。慶長2(1597)年に石田三成の妹婿福原直高12万石が築城を開始。天守閣のあった本
- [ 教会 ]
-
別府市末広町1-14
1950年にサレジオ修道会によって建立され、運営。
聖フランシスコ・ザビエル渡来400年記念に際して、1950年12月17日に落成。フランスのルルドにある教会
- [ 歴史 ]
-
竹田市竹田殿町2044
凝灰岩壁をノミでくりぬいて造った礼拝堂。
殿町武家屋敷の裏手に、岸壁をくりぬいてつくられた礼拝堂。幅、奥行きは3m、高さ3.5mほどで、外国人宣教師
-
き 北台武家屋敷跡
- [ 歴史的建造物 ]
-
杵築市北台
藩校・学習館の門、磯矢邸、家老屋敷の大原邸などがある。
北台には藩校「学習館」の正門がそのままの姿で現在の杵築小学校の門として残るほか、松平七代親賢の別館であった
-
ち 長安寺
- [ 寺院 | 花 ]
-
豊後高田市加礼川635
平安朝以来の天台宗の古刹で往時の六郷満山の総本山。
かつて六郷満山の総本山として栄えた天台宗の古刹で、花の寺として有名。収蔵庫にある藤原時代の秀作『太郎天像と
-
ゆ 柞原八幡宮
- [ 神社 | 初詣スポット ]

-
大分市八幡987
高崎山の裏山麓にある836年(承和3)、宇佐八幡宮の分霊を受けた由緒ある神社
樹齢3000年の天然記念物のクスが茂る深い森にある神社。本殿は貴重な八幡造りで、東宝殿、西宝殿、申殿、拝殿
-
に 二王座歴史の道
- [ 歴史街道 | 歴史 ]
-
臼杵市二王座
漆喰の壁と重厚感のある瓦屋根の武家屋敷、古い蔵やモダンな洋館などが立ち並ぶ。
二王座は臼杵城西南の大門櫓前から5分ほど歩いたところにある地域。格式の高い武家屋敷が多く残り、凝灰石の石畳
-
せ 清溪文庫
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
日田市大鶴町2299
清渓文庫(井上準之助の生家)
明治2年3月生れ。東大卒業後日本銀行に就職。日銀総裁と大蔵大臣を歴任し、昭和5(1930)年に金解禁を行っ
-
た 滝尾百穴
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
大分市羽田740
滝尾中学校の校庭に面した崖にある横穴群。
滝尾中学校のグラウンド北側にある丘陵地の崖は、上下3段にわたって大小総計84個もの横穴が口を開けている。6
-
や 八坂社・富来神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
国東市国東町富来857
八坂社(富来神社)は開運の神社といわれています。
本殿の裏にある開運運玉唐獅子像の抱く「運玉」をさわると、宝くじ運や子孫繁栄にご利益があるといわれる。「開運
- [ 歴史 | 庭園 | 桜 | 紅葉 ]
-
玖珠郡玖珠町森858
森藩ゆかりの史跡が点在。
森藩第八代藩主の久留島通嘉が築造させた陣屋跡。庭石と樹木が静かな調和をみせる久留島庭園を中心に、三島神社清
-
む 無動寺
- [ 寺院 ]
-
豊後高田市黒土1475
国東六郷満山中山本寺のひとつ。
奈良時代の創建という天台宗の名刹。本堂には本尊とともに「薬師如来坐像」「大日如来坐像」「十二神将」などの仏
-
ご 合元寺
- [ 寺院 ]
-
中津市寺町973
別名赤壁寺、宇都宮氏の家臣全員が討死したといわれる。
1587年(天正15)、黒田孝高[よしたか]によって建立。城主の黒田如水が地元の豪族・宇都宮鎮房[しげふさ
- [ 歴史的建造物 | 博物館・資料館 ]
-
国東市安岐町富清2507-1
大分を代表する哲学者三浦梅園の旧宅。
梅園自身が設計したという萱葺き寄棟造りの旧宅は国の史跡。隣の敷地には「梅園哲学」を大成した江戸中期の哲学者
-
お 小倉磨崖石塔
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
佐伯市弥生上小倉
磨崖面に、25mにわたって刻まれた石塔。
弥生地域の中心部にある石塔で鎌倉期から南北朝期の作とされる。宝塔8塔、五重塔34基の合計42基が、25mに
-
お 大野老松天満社
- [ 神社 ]
-
日田市前津江町大野833
社伝では延久3年(1071)大蔵永季の創建で菅原道真を祀る。
延久3(1071)年創建の三間社流造りの古社で、津江山系に7つある老松天満の一つ。現在の建物は長享2(14
-
き 旧丸毛家住宅
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
臼杵市海添本了13
臼杵藩時代稲葉氏の家臣として代々仕えた丸毛氏の屋敷。
江戸後期の建築様式をとどめた上級武士の屋敷。建物内で「表玄関」と「内玄関」に分けられるなど、臼杵の武家屋敷
-
き 杵築城
- [ 歴史 | 城 ]

-
杵築市杵築16番地1
一帯は城山公園として整備
市街の東端、守江湾に臨んで立つ。1394年(応永元年)、木付[きづき]氏4代頼直[よりなお]が築城、江戸時
-
つ 椿堂・遍照院
- [ 寺院 ]
-
豊後高田市黒土1400
弘法大師ゆかりの真言宗椿堂(遍照院)
宝暦10(1760)年建立、弘法大師を祀り、「椿大師」と親しまれる。奥の院に湧く霊水は万病に効くとされ、全
-
い 岩戸寺
- [ 寺院 ]
-
国東市国東町岩戸寺1232
養老3(719)年に仁聞菩薩が開いたと伝えられる山寺。
旧正月7日に修正鬼会[しゅじょうおにえ]の祭礼が成仏寺と一年交替で行われる。本尊の薬師如来坐像は平安後期の
-
い 岩屋寺石仏
- [ 寺院 | 碑・像・塚・石仏群 ]
-
大分市古国府1-4
大分市古国府にある平安時代後期(11世紀中頃)の磨崖仏。
上野丘の中腹に刻まれている石仏。17体の仏像からなり、薬師如来座像を中尊とした薬師三尊像の左右に、釈迦三尊
-
お 大原邸
- [ 歴史的建造物 | 庭園 ]

-
杵築市杵築207番地
杵築そぞろは時間(とき)の旅こころがゆっくり遡る・・・
北台に立つ重臣屋敷の代表格で、その格式は杵築一と評される。松平藩の家老を勤めた大原氏の屋敷で、重厚な門構え
-
ま 曲石仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
大分市曲
平安時代末期から鎌倉時代の作とされる。
大きな石窟は釈迦堂と言われていて、堂内の石窟正面異壁に像高3mの釈迦如来像、入口の両側に多聞天、持国天像を
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
大分市府内町2-2-1
大分銀行本店として大正2(1913)年に完成したもの。
大正2年(1913年)に旧第二十三国立銀行本店として建てられ、大分銀行本店となった後、現在は大分銀行ローン
-
か 神尾家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
中津市山国町守実120
1771年(明和8)に建築された九州最古の木造住宅。
江戸時代に組頭をつとめた旧家で、明和8(1771)年に建てられたとの記録があり、年代のわかる九州最古の民家