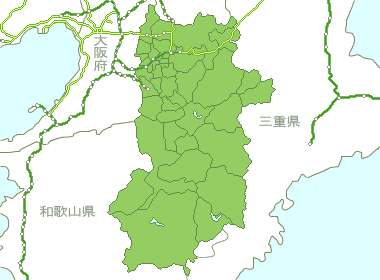神社・寺院・歴史 一覧

-
と 東大寺 南大門

- [ 寺院 | 歴史的建造物 ]

-
奈良市雑司町406
東大寺の正門。平安時代の応和2年(962年)8月に台風で倒壊後、鎌倉時代の正治元年(1199年)に復興され
-
ま 纒向遺跡
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
桜井市太田
御諸山(みもろやま)とも三室山(みむろやま)とも呼ばれる三輪山の北西麓一帯に広がる弥生時代末期から古墳時代
-
あ 飛鳥水落遺跡
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]

-
高市郡明日香村飛鳥
古代の漏刻跡とされる遺跡。
日本初の水時計「漏刻」の遺跡。かつては導水管や排水管がめぐらされ、一定の速度で水を流すことにより時間を計っ
-
え 栄山寺
- [ 寺院 ]
-
五條市小島町503
奈良時代の建築である八角堂(国宝)があることで知られる。
栄山寺は古くは前山寺(さきやまでら)と呼ばれ、藤原武智麻呂(むちまろ)が養老3年(719年)に創建したと伝
-
ほ 疱瘡地蔵
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
奈良市柳生町
3m近い岩に彫られた大磨崖仏で、正長の土一揆により徳政を勝ち取った百姓らが疱瘡よけを祈願して彫った物とされ
-
と 東大寺 法華堂
- [ 寺院 ]

-
奈良市雑司町406
三月堂(さんがつどう)の通称で知られる。日本の国宝に指定。東大寺に現存する数少ない奈良時代建築の1つであり
-
い 石舞台古墳
- [ 歴史 B級スポット ]

-
高市郡明日香村島庄
巨石を積み上げた横穴式石室古墳で日本最大級のもの。
埋葬者は4代の天皇に仕え、崇峻天皇暗殺の首謀者と目される蘇我馬子が有力視されてる。7世紀初頭の権力者で、大
-
ち 茶臼山古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
桜井市外山
古墳時代前期初頭の巨大な前方後円墳。
鳥見山の北麓にあり、自然丘陵を利用して築造された墳丘長207mの前方後円墳。前方が長く柄鏡の形をしていると
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
奈良市水門町100
貴重な寺宝が並ぶ待望の展示施設。
図書館・収蔵庫・寺史研究所・華厳学研究所・金鐘会館が入った複合施設。
-
き 吉田寺
- [ 寺院 ]
-
生駒郡斑鳩町小吉田1-1-23
天智天皇の勅願により創建されたとされ、近くには妹・間人皇女を葬る古墳がある。平安時代の永延元年(987年)
-
と 東大寺 転害門
- [ 寺院 ]

-
奈良市雑司町
境内西北、正倉院の西側にある八脚門。平重衡の兵火(1180年)、三好・松永の戦い(1567年)の2回の大火
-
と 東大寺 開山堂
- [ 寺院 ]

-
奈良市雑司町406
開山(初代住職)良弁の肖像を安置するための堂です。内陣は1200年(正治2年)、外陣は1250年(建長2年
-
あ 秋篠寺
- [ 寺院 ]

-
奈良市秋篠町757
本堂に立つ伎芸天立像は、伎芸天像としては日本唯一。
奈良時代の法相宗(南都六宗の1つ)の僧・善珠が創建したとされ、地元の豪族秋篠氏の氏寺とも言われているが、創
-
え 円成寺(奈良市)
- [ 寺院 ]

-
奈良市忍辱山町1273
平安中期の創建といわれ、国の名勝に指定された庭園は、舟遊式と浄土式をあわせた貴重な遺構。
奈良市街東方の柳生街道沿いに位置する古寺で、仏師・運慶のもっとも初期の作品である国宝・大日如来像を所蔵する
-
い 石位寺
- [ 寺院 ]
-
桜井市忍阪870
現存日本最古の三尊石仏(重要文化財)を安置することで知られる。
白鳳時代の石仏があることで名高い。高さ1.2m、底辺1.5m、厚さ約20cmのおにぎり形の砂岩に浮き彫りさ
-
あ 安倍文殊院

- [ 寺院 | パワースポット ]

-
桜井市阿部645
切戸文殊(京都府)・亀岡文殊(山形県)とともに日本三文殊に数えられる。
安倍倉梯麻呂が645(大化元)年に創建したという。本尊、高さ約7mの文殊菩薩騎獅像は日本三文殊の一つに数え
-
ほ 法隆寺 網封蔵
- [ 寺院 ]

-
生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1
聖霊院の東に建つ、奈良時代~平安初期の倉庫、国宝。二つの倉を左右に並べて一つの屋根で覆った形のものである。
-
た 高松塚古墳
- [ 歴史 ]

-
明日香村平田字高松
石室内の鮮やかな彩色壁画で非常に有名。
藤原京期(694年~710年)に築造された終末期古墳で、直径23m(下段)及び18m(上段)、高さ5mの二
-
ほ 法隆寺 中門
- [ 寺院 ]

-
生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1
法隆寺の謎・・、お寺の門は普通、出入りを邪魔する真ん中に柱はない。で、聖徳太子の怨霊を封じる為の寺なのでは
- [ 歴史 | 自然 ]

-
吉野郡吉野町吉野山
南明妙法殿や後醍醐天皇の碑などが立つ。
延元元年(1336年)に、吉水院に逃れた後醍醐天皇が実城寺を皇居とし、金輪王寺と改名。南朝没落後は衰退、明
-
じ 十輪院
- [ 寺院 ]
-
奈良市十輪院町27
本尊は石造の地蔵菩薩。開基(創立者)は朝野魚養(あさののなかい)と伝える。本堂(国宝)は背後の覆堂内に安置
-
ち 朝護孫子寺
- [ 寺院 | 日の出 | 紅葉 ]

-
生駒郡平群町信貴山2280-1
 [ 紅葉時期 10月中旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 10月中旬~11月下旬 ]「信貴山の毘沙門さん」として知られる。
信貴山中腹にあり、福徳開運の毘沙門天で親しまれている。大和七福神(朝護孫子寺、久米寺、子嶋寺、小房観音寺、
-
ほ 法隆寺 東院鐘楼
- [ 寺院 ]

-
生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1
袴腰(はかまごし)が付いたものでは現存最古の鐘楼
-
お 王竜寺
- [ 寺院 ]
-
奈良市二名6-1492
本堂は正月堂とも呼ばれる。
奈良時代に聖武天皇の勅願によって建立、江戸時代に梅谷和尚(黄檗宗の開祖・隠元禅師の孫弟子)を招いて菩提寺と
-
へ 平城京歴史館
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
奈良市二条大路南4-6-1
中国大陸、朝鮮半島をはじめ大陸との交流により発展した国づくりの歴史や往時の文化・暮らしに焦点を当てたテーマ
- [ 寺院 ]

-
生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1
東側は舎利殿と呼ばれ、聖徳太子が2才の春に東に向って合掌され、そしてその掌中から出現したという舎利(釈迦の
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
高市郡明日香村平田538
飛鳥歴史公園内にある歴史公園館。
国営飛鳥歴史公園4地区の施設や催し物の案内をはじめ、飛鳥地方の史跡や歴史を立体模型や映像を用いて紹介。立体
-
ほ 法隆寺伝法堂
- [ 寺院 ]

-
生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1
絵殿・舎利殿の吹き放しの廊下越しにみた伝法堂。法隆寺東院の講堂。聖武天皇夫人・橘夫人の住宅を改修・改造され
- [ 寺院 ]
-
香芝市良福寺361
吉田寺とともに「ぽっくり寺」として知られる寺。
「往生要集」を著し、多くの伝説がある恵心僧都源信ゆかりの寺。本尊の阿弥陀如来は源信が母の忌中に刻んだとされ
-
お 帯解寺
- [ 寺院 | パワースポット ]
-
奈良市今市町734
子授けや安産祈願の寺として知られる。
天安2年(858年)、文徳天皇の勅願により伽藍が建立された古刹。本尊の木造地蔵菩薩像は重要文化財。江戸時代