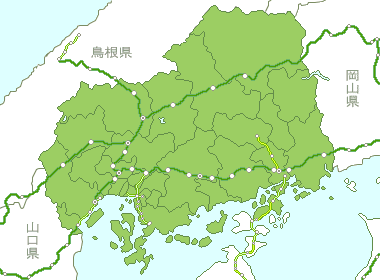神社・寺院・歴史 一覧

-
み 御年代古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
三原市本郷町南方
古墳時代終わり頃に造られたとされる巨大な横穴式石室。
7世紀中頃のものといわれている横穴式石室と内部の2つの家型石棺には、古墳時代終末期のすぐれた技術が用いられ
-
ぬ 沼名前神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
福山市鞆町後地1225
社伝では今から1800年以上前に創建された格式高い古社。
大綿津見命を主祭神とし、須佐之男命を相殿に祀る海の神様である。地元では「祇園さん」と呼ばれており、京都の八
-
み 明王院(福山市)
- [ 寺院 ]
-
福山市草戸町1473
和様建築の本堂と鮮やかな朱塗りの五重塔が美しい古刹。
明王院の前身である「常福寺」は807年(大同2年)に空海(弘法大師)によって創建と伝わる。中国三十三観音霊
-
れ 廉塾菅茶山旧宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
福山市神辺町川北635
菅茶山の私塾「廉塾」と寮舎。
菅茶山は、寛延元年(1748)、神辺宿に生まれ、教育者・漢詩人・漢学者として知られる。東本陣の向かい側にあ
-
と トンカラリン
- [ 歴史 ]
-
東広島市安芸津町三津信僧
山の畑の段差を利用して作られた石組みの穴。
19世紀頃に造られたと推定される棚田の導水施設。昭和51年に南繁が発見。竪穴と横穴を連結した高さ約75セン
-
み 御袖天満宮
- [ 神社 ]
-
尾道市長江1-11-16
学問の神様、菅原道真を祀る神社。
菅原道真が天神として祀るようになると、大山寺境内に道真の袖を神体として祠を建立し、後に「御袖天満宮」と呼ば
-
お 御茶屋本陣跡
- [ 歴史 ]
-
東広島市西条本町4-31
御茶屋と呼ばれる広島藩の本陣跡。
江戸時代、参勤交代の大名や長崎奉行らの役人が往来の際、宿泊や休憩をした本陣跡で広島藩領内9カ所のなかでも最
-
み 御調八幡宮
- [ 神社 | 初詣スポット | 桜 ]
-
三原市八幡町宮内21
社叢は、県の天然記念物に指定。
奈良時代に道鏡に対する宇佐八幡宮の神託事件によりこの地に流罪となった和気広虫(法均尼)が八幡神を祀ったのに
-
こ 向上寺
- [ 寺院 ]
-
尾道市瀬戸田町瀬戸田57
室町時代初期に建立された曹洞宗の禅刹。
1403年(応永10年)生口守平の開基、愚中周及の開山により臨済宗の寺院として創建されたのに始まり、向上庵
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
広島市中区中島町1-6
国立の被爆者を追悼する施設。
国立の施設としては初めて広島平和記念公園内に設置(2002年8月1日)された。原爆死没者慰霊碑や広島平和記
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 公園 ]
-
三次市小田幸町122
広島県三次市にある史跡公園。
1979年(昭和54年)4月に開園した円墳や方墳など176基の古墳が残る、中国地方最大級の史跡公園。国の史
-
お 音戸の古い町並み
- [ 道・通り・街 | 歴史街道 | 歴史 ]
-
呉市音戸町鰯浜
古い街並みから瀬戸内の歴史を感じることができる。
広島市の南東と便利な場所にある音戸の古い町並みはかつては銀行や商店、劇場、旅館などが並び、賑わっていた旧道
-
き 清盛塚(呉市)
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-
呉市呉市音戸町
平清盛公を祀る清盛塚
高さ8.5mの堂々とした石造十三重の塔で、福原遷都や日宋貿易を行った平清盛を供養する塚。北条貞時が建立した
- [ 城 | 歴史 ]
-
安芸高田市吉田町吉田
安芸国の戦国大名毛利氏の居城。
「毛利氏城跡郡山城跡」の名称で国の史跡に指定されている。築城初期は砦のような小規模な城であったが、毛利氏の
-
え 胡子神社
- [ 神社 ]

-
広島市中区胡町5-14
原爆にも負けず四百年以上、胡子大祭を守り続けてき広島胡子神社。
胡子神社の御祭神は蛭子(ひるこ)神・事代主神・大江広元公(毛利家の始祖)の三柱が三位一体となったえびす神と
-
き 清盛神社
- [ 神社 ]
-
廿日市市宮島町
平清盛を祭神とする神社で、厳島神社の末社。
宮島を今日の隆盛に導いた平清盛の偉績をたたえ、その霊を慰めるために昭和29年に建てられた神社です。清盛の命
-
ひ 百万一心碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
安芸高田市吉田町吉田
郡山城を修造した際、人柱をの代わりとして埋めた巨石。
毛利元就が郡山城を拡張する際に、れまでの風習であった人柱に代えて姫の丸壇の礎石に「百万一心」と彫らせて埋め
-
み 三原城跡
- [ 城 | 歴史 ]
-
三原市館町1
現存している天主台とその周りの内堀一帯が国の史跡に指定。
永禄10(1567)年、毛利元就の三男・小早川隆景が築いた平城の遺構。最盛期の構造は、天主台を北(陸側)に
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
三次市小田幸町122 みよし風土記の丘内
自然と文化の調和した美しい史跡公園。
国の史跡浄楽寺・七ッ塚古墳群を中心に、古代住居や古民家、資料館が整備さた史跡公園。県内各地の遺跡から出土し
-
う 艮神社
- [ 神社 | パワースポット ]

-
尾道市長江1-3-5
旧市内で最古の神社と伝わる。
大同元(806)年創建。天照大神、須佐之男命、伊邪那岐命、吉備津彦命を祀っている。境内に生えている楠は樹齢
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
福山市西町2-4-1
瀬戸内の歴史と文化に焦点をあてた資料を展示。
1989年11月3日開館。草戸千軒町遺跡出土品(国の重要文化財)を中心に瀬戸内地方の交通・交易や民衆生活に
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
福山市鞆町後地536-1
「潮待ちの館」の愛称をもつ資料館。
万葉の時代から栄えた鞆の浦を中心とする瀬戸内の歴史と文化を紹介する施設で、福島正則が築いたとされる鞆城跡(
-
ま 松阪邸
- [ 歴史的建造物 ]
-
竹原市本町3-9-22
江戸末期の重厚華麗な浜旦那の家として公開。
薪問屋・石炭問屋を業とし、塩田経営、廻船業、醸造業な豪商を営んでいた家で、町並み保存地区にある。公開してい
-
ほ 鳳源寺
- [ 寺院 | 庭園 | 桜 | 花 ]
-
三次市三次町1057
寛永10(1633)年建立の三次藩初代藩主・浅野長治が建立した浅野家の菩提寺。
境内には赤穂義士大石良雄が植えたと言われるしだれ桜や美しいスイレンの咲くことで知られる愚極泉(4代目愚極和
-
も 毛利元就の墓
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
安芸高田市吉田町吉田
郡山城跡山麓の洞春寺跡にある名将毛利元就の墓。
1571年(元亀2)、城麓の御里屋敷で75年の生涯を閉じた元就。墓標にははりいぶきが植えられている。境内に
-
へ 平和の灯
- [ 歴史 | その他 ]

-
広島市中区中島町1 平和記念公園内
核廃絶を願って、核兵器がなくなる日まで絶やすことなく燃やし続けている火。
火種は、全国12宗派からの「宗教の火」、全国の工場地帯からの「産業の火」から。その火種の一つに宮島弥山の「
-
か 海福寺
- [ 寺院 ]
-
尾道市西土堂町14-1
1328年(嘉暦三年)に遊行二祖、他阿上人の開基したといわれる時宗の寺。
境内には「三つ首様」と呼ばれる墓があり、「三ツ首様」伝説で知られる。伝説江戸時代末期の1828年(文政十一
-
じ 慈観寺
- [ 寺院 | 庭園 | 花 ]
-
尾道市長江1-4-7
ぼたん寺として親しまれている。
1348(貞和4)年に慈観上人が開いた時宗の寺。本尊は阿弥陀如来。本堂は法隆寺を模した二層屋根の風格ある建
-
き 旧木原家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
東広島市高屋町白市1046-1
豪商木原家の住宅
木原家は西条盆地の東方の白市に居住し、江戸時代初期から酒造業や塩田業を営み、安芸国有数の商家として栄えた。
-
と 鞆七卿落遺跡
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]

-
福山市鞆町
18世紀中頃から19世紀前期の建物群
明治維新前夜、尊皇攘夷を主張する三条実美ら7人の公家が、公武合体派に追われ長州に下る途中、寄港した港町・鞆