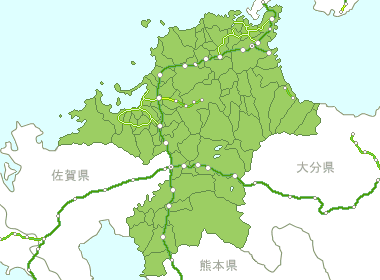神社・寺院・歴史 一覧

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
田川郡福智町弁城165-2
鎌倉時代の英彦山山伏の嶺入り修験を物語る貴重な資料として県の指定文化財に指定。
建武2(1335)年に法橋良密によって岩屋権現の大岩に金剛界四印会曼陀羅が刻まれた梵字曼荼羅。英彦山山伏の
-
こ 高良大社
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]
-
久留米市御井町1
筑後一の宮で、式内名神大社の正一位として古代より地域筆頭の格式を誇り、厄除け、延命長寿で篤い信仰がある。社
-
こ 恋木神社
- [ 神社 | デート | パワースポット ]

-
筑後市水田62-1
日本で唯一、「恋」という文字が入る神社で九州二大天満宮の1つ。
菅原道真を祭神とした歴史ある神社。また、天満宮奥には縁結びで有名な恋木神社もあります。良縁祈願に多くの人が
-
き 旧門司三井倶楽部
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]

-
北九州市門司区港町7-1
1921年(大正10年)に三井物産門司支店の社交クラブとして建築。
接客用の洋風の本館と、それと接続する和風の付属屋・倉庫からなる。1949年(昭和24年)から国鉄の所有とな
-
と 十日恵比須神社
- [ 神社 | 初詣スポット | 祭り・イベント ]

-
福岡市博多区東公園7-1
東公園にあるえびす様をお祀りする神社。
毎年、1月8~11日に行われる十日恵比須で知られる神社。祭神は事代主神(えびす様)と大国主神(だいこく様)
-
か 竈門神社
- [ 神社 | 桜 | 花 | 紅葉 | デート | パワースポット ]
-
太宰府市内山883
 [ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]縁結びの神社としても有名。
大宰府政庁を構築する際の鬼門よけとして造営されたのがはじまり。宝満山の山頂に上宮、山麓に下宮が鎮座し、縁結
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 | 公園 | 自然 ]
-
遠賀郡遠賀町島津574-9
前方後円墳1基、方墳1基、円墳3基で整備し、四季の草花とともに歴史自然公園として保存。
公園内にある島津・丸山古墳は、全長57m、前方部幅14m、高さ2m、後円部直径30m、高さ4.5mの前方後
-
だ 大分八幡宮
- [ 神社 | 見学 ]
-
飯塚市大分1272
福岡県飯塚市にある神社。旧社格は郷社。筥崎宮の元宮として知られる。
社伝によれば、神亀年間(724~729)に八幡神を奉祀したのがはじまりで、日本五所別宮の一つだったという。
-
た 橘塚古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 見学 ]
-
京都郡みやこ町勝山黒田橘塚850
黒田小学校の校庭にある巨岩を使った横穴式石室の古墳(円墳)で、その規模は全国有数。
6世紀後半につくられた円墳といわれる。巨岩を組んだ横穴式石室は規模が大きく、かつてこの地で権力をふるった豪
-
ひ 英彦山神宮
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]
-
田川郡添田町英彦山1
天忍穂耳命[あめのおしほみみのみこと]を祭る神社。
神宮の神域は英彦山全山。英彦山全体が神域で、上宮、中宮、下宮、奉幣殿、さらに摂社の高住神社、玉屋神社が点在
- [ 神社 ]
-
福岡市西区愛宕2-7-1
福岡県内随一の参拝者数を誇る神社。
創始は景行天皇2年(西暦72年)、鷲尾山に伊耶那岐尊・天忍穂耳尊を祀ったのが鷲尾神社(鷲尾権現)の始まりと
-
あ 秋月の町並み
- [ 歴史街道 ]

-
朝倉市秋月
筑前の小京都秋月
朝倉市の北部、古処山のふもとに城下町として栄えた秋月。今では「筑前の小京都」といわれ、秋月目鏡橋や秋月城跡
-
き 旧大阪商船
- [ 歴史的建造物 ]
-
北九州市門司区港町7-18
八角形の塔が特徴のレンガ風木造2階建てビル。
北九州市門司区港町にある歴史的建造物。国の登録有形文化財に登録されている。塔は港の見張り用だった塔屋の名残
-
な 並倉
- [ 歴史的建造物 ]
-
柳川市三橋町江曲216
川下り(お堀めぐり)の途中で見られる、3つ並んだ赤レンガ造りの倉。明治後期に建てられた柳川特産の味噌、しょ
-
お 大富神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
豊前市大字四郎丸256
現在は、大富神社と称するが、古来は宗像八幡社とも称され、大富神社神輿の古い鏡には大富ノ神とも宗像ノ神とも記
-
が 岩石城
- [ 歴史 | 城 ]

-
田川郡添田町添田1788-2
岩石山の中腹にある復元城。
平清盛が築いた。後世に大友氏、大内氏、豊臣秀吉の各大名の順に、攻め落とされては修復されると言う歴史を繰り返
-
ひ 平塚古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 見学 ]
-
糟屋郡粕屋町上大隈
弥生時代末期のものであると推定され、重要な史跡として県指定文化財になっている。
弥生時代から古墳時代への移行を伝える平塚古墳。県の史跡である箱式石棺は、長さ約2m、幅約70cm、深さ70
- [ 神社 | 見学 ]

-
北九州市小倉北区城内2-2
元和3(1617)年、細川忠興が小倉城の鎮守として城郭北西の鋳物師町に創建。昭和9(1934)年に現在地へ
-
き 旧松本家住宅
- [ 歴史的建造物 | 見学 ]
-
北九州市戸畑区一枝1-4-33
この建物は、明治専門学校(現在の九州工業大)を創立した、松本健次郎氏が、明治45年に住居と迎賓館を兼ねて建
九州産業界の重鎮、松本健次郎氏の住居兼迎賓館として、明治45(1912)年に建てられた木造西洋建築物。洋館
-
は 杷木神籠石
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
朝倉市杷木林田
神籠石は九州から瀬戸内地方にみられる構造物で、杷木神籠石は1967(昭和42)年に発見された。筑後川河岸を
-
ば 梅林寺
- [ 寺院 | 梅 ]
-
久留米市京町210
藩主有馬氏の菩提寺。臨済宗妙心寺派の古刹で、九州屈指の修業道場として知られる。
筑後川べりの丘に堂々たる伽藍を見せる臨済宗妙心寺派の禅寺。九州の代表的な禅の修行道場として知られ、久留米藩
- [ 寺院 | 紅葉 ]

-
糸島市雷山626
 [ 紅葉時期 11月上旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 11月上旬~11月下旬 ]雷山の中腹にある古刹で、清賀上人により開基されたと伝えられる。
本尊の木造十一面千手千眼観音像(像高463.6cm/鎌倉時代)は、国指定重要文化財に指定されています。秋に
-
う 宇美八幡宮
- [ 神社 | パワースポット ]
-
糟屋郡宇美町宇美1-1-1
神功皇后様安産伝承の地として今も安産、育児の崇敬をあつめる。
神功皇后が新羅遠征帰還の折に、この地で応神天皇を出産したと伝わり、神功皇后、応神天皇ほかを祀る。安産の神様
-
き 旧吉原家住宅
- [ 歴史的建造物 | 見学 ]
-
大川市小保136-17
旧吉原家住宅は、大規模で細部の意匠に優れ、建築年代も確実なものとして九州でも重要な民家として、国指定重要文
文政8(1825)年建築。柳河藩の小保町の別当職を代々つとめ、のちに蒲池組の大庄屋となった吉原家の居宅で、
-
れ 霊巌寺の奇岩
- [ 寺院 | 自然 | 自然地形 | 特産 ]
-
八女市黒木町笠原9731
日本三大奇岩の一つ
八女茶発祥の地、奥八女黒木の霊巌寺にそびえる浸食と風化によって形づくられた奇岩群は、日本三大奇岩の一つ。安
-
れ 鈴熊寺
- [ 寺院 ]
-
築上郡吉富町鈴熊233
国指定重要文化財の薬師如来産像がある
奈良時代に行基が建立したと伝えられる。境内には、涅槃仏を刻んだ高さ2m、幅3mの巨石、梵字で真言の聖句を刻
-
な 成田山不動寺
- [ 寺院 | 不動 | 見学 ]
-
遠賀郡岡垣町内浦885
千葉県成田市にある真言宗智山派の大本山成田山新勝寺より、不動明王をお迎えして開山した寺。
岡垣町の北西部にあり、境内からは晴れた日には響灘越しに山口県が見える。交通安全、商売繁盛、身代わりの不動尊
-
や 山野の石像群
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
嘉麻市山野1609
山野若八幡宮の上手、一段と高い丘の上に350体あまりの石仏が、緑深い樹々に囲まれ、木造の雨よけの下に立ち並
- [ 歴史的建造物 | 歴史 | 見学 ]
-
うきは市吉井町 国道210号沿い
白壁土蔵造りの町並みを保存するため観光MAPを配布しており、常時職員が案内の対応をしている
国道210号を中心に約80軒の白壁土蔵造りの家が並ぶ。昔、吉井は豊後街道の宿場町として栄え、度重なる火災を
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 | 公園 ]
-
朝倉市平塚444
多重環濠集落跡で国指定史跡。甘木インターの南側に位置し、特殊な建物がある中央集落や、濠で区切られた複数の小
弥生時代後期を中心に堅穴住居や掘立柱建物跡が発見された平塚川添遺跡。周辺を公園として整備し、発掘した遺跡の