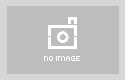甲斐善光寺 かいぜんこうじ

永禄元年(1558年)、甲斐国国主武田信玄が、川中島の合戦の折、信濃善光寺の焼失を恐れ、永禄元年(1558)、御本尊善光寺如来をはじめ、諸仏寺宝類を奉遷したことに始まる。
開山は信濃善光寺大本願三十七世の鏡空。
長野県長野市にある善光寺をはじめとする各地の善光寺と区別するため甲斐善光寺(かいぜんこうじ)と呼ばれることが多く、甲州善光寺(こうしゅうぜんこうじ)、甲府善光寺(こうふぜんこうじ)とも呼ばれている。
本堂と山門は国の重要文化財になっています。撞木(しゅもく)造りの本堂は、東西約38m、南北約23m、高さ約26mもある堂々としたもので、東日本最大級の木造建築物。
| 住所 | 甲府市善光寺3-36-1 |
| 営業時間 | 拝観受付時間 午前9時~午後4時30分 |
| 料金 | 拝観料:大人500円、小学生250円(30名以上で団体割引あり 大人400円、小学生200円) |
| 駐車場 | 普通乗用車30台 大型バス無料駐車場有 |
| アクセス 公共交通 | JR善光寺駅から徒歩8分 最寄駅 > 善光寺駅(JR)~980m |
| アクセス 車 | 中央自動車道の一宮御坂インターチェンジまたは甲府昭和インターチェンジ 最寄IC > 甲府昭和IC(中央自動車道)~8.067km |
| 公開サイト | www.kai-zenkoji.or.jp |
| 問い合わせ | 甲斐善光寺 |
| TEL | 055-233-7570 |
レポート
本堂は、東日本有数の木造建造物で、安置されている御本尊様が7年に一度の御開帳で見学することができました。
山門、寛政八年(1796)に再建。門の両脇には金剛力士(仁王)像が安置されています。
山門の説明。山門を背後から見た様子。山門をくぐり参道から金堂を望む。
参道の脇には、信玄餅で有名な「ききょうや」さんの直売所がありました。御開帳にあわせて記念品の販売もしていました。
香炉堂。線香(1束100円)をたいて自分の体の一部にあてると、悪い所に効くと云われています。手水舎。
金堂(寛政八年(1796)に再建)は、善光寺建築に特有の撞木造(しゅもくづくり)とよばれる形式で、総高27メートル、総奥行49メートルという、日本有数の木造建築として有名です。扁額の後方に御本尊様は安置されています。賓頭盧尊者(びんづるそんじゃ)様。
金堂内にある阿弥陀如来像(信州善光寺の前立本尊)が7年に一度の「御開帳」で、一般公開(拝観料は大人一人500円)されていました。堂中天井(吊り天井)には、巨大な龍が二匹描かれ、手をたたくと「鳴き龍」が低めの音でビュビュ〜と鳴きます。また、金堂下には、「心」の字をかたどる真っ暗な通路を通って鍵(真上の御本尊様と結ばれている)を探し、触れるこで御本尊と縁が結ばれ極楽浄土に行けるという戒壇廻り(かいだんめぐり)もありました。
金堂から外を眺めた様子。金堂を右手方向から望む。富士山が雲の中見えました。
境内にあった王子稲荷神社。
銅鐘。長野から甲府まで引きずって運んだという「引き摺りの鐘」で有名。善光寺銅鐘の説明。
宝物館。宝物殿前に鎮座する大仏。