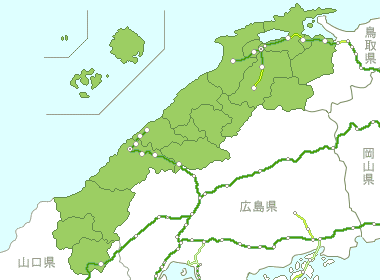神社・寺院・歴史 一覧

-
み 水若酢神社
- [ 神社 | 祭り・イベント ]
-
隠岐郡隠岐の島町郡
隠岐国一の宮。旧五箇村全村の信仰を集めた。本殿(国の重要文化財)は、寛政7年(1795年)の竣工で隠岐造り
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 公園 ]

-
松江市古曽志町562-1
宍道湖北岸の丘陵地にある史跡公園。島根県の特色ある歴史や文化遺産を紹介している。園内には、移築復元した古曽
-
た 玉若酢命神社
- [ 神社 ]
-
隠岐郡隠岐の島町下西
『延喜式』にも見られる由緒ある神社で、旧隠岐国の総社。古くは「若酢大明神」、「総社明神」と称した。隠岐造り
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
大田市大森町イ490
大森の町並みの中心にある旧大森区裁判所跡を復元して利用。展示室では町並みの関係資料や、石見銀山の歴史と暮ら
- [ 歴史 | 博物館・資料館 | 体験施設 ]
-
松江市玉湯町湯町1755-1
全国で唯一、出雲型勾玉を伝承する
出雲の伝統工芸品、メノウ細工をテーマにした施設。勾玉の歴史や製造法を紹介するミュージアムや熟練の技を間近で
-
い 井戸神社
- [ 神社 ]
-
大田市大森町イ1372
60歳の老齢で銀山代官となり、享保17(1732)年の大飢饉の際に、減税や官米放出、イモの栽培普及などに努
-
や 山辺神宮
- [ 神社 ]
-
江津市江津町
他の別名として江津祇園宮、御魂神社がある。
式内社でもある古社で、素盞鳴尊と奇稲田姫命を祀る。境内には四柱神社・白竜の霊石がある。4年に1度、7月に行
- [ 神社 ]

-
松江市和多見町81
出雲国風土記や延喜式に載る古社で湖都松江を代表する産土神。主祭神・速秋津比売神は水戸の神、祓え戸の神として
-
ま 松江歴史館
- [ 歴史 | 博物館・資料館 | 庭園 ]

-
松江市殿町279
松江開府400年を記念し建設された歴史館。敷地内には松江藩政の歴史や産業の発展を紹介する展示室、日本庭園を
-
や 八重垣神社
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]

-
松江市佐草町227
出雲國神仏霊場第十四番。
素盞嗚尊と櫛稲田姫の故事から縁結びの神様として知られており、素盞嗚尊と稲田姫命を祀っている。境内奥の鏡の池
-
さ 佐太神社
- [ 神社 | 歴史的建造物 | 歴史 | パワースポット ]
-
松江市鹿島町佐陀宮内72
出雲大社に次ぐ、二の宮として勢力を誇っていた古社。
『出雲國風土記』にも登場し出雲二ノ宮として古くから崇敬されてきた御社。荘厳な大社造り三殿並立の社殿は神社建
-
ゆ 由良比女神社
- [ 神社 ]
-
隠岐郡西ノ島町浦郷
創建は不詳。明治22年(1889年)以降、社殿・境内地が整備された。海上の守り神として漁師からの信仰があつ
- [ 寺院 ]
-
大田市大森町大森
宝暦年間(1751~1763)に月海淨印が、銀山で亡くなった人々の供養のため、五百羅漢を造営するとともに羅
-
し 清水谷製錬所跡
- [ 歴史 ]
-
大田市大森町
仙ノ山北側に位置するこの製錬所は、明治28(1895)年に完成したもので、当時の先端技術によって建設された
-
か 甘南備寺
- [ 寺院 ]
-
江津市桜江町坂本3842-1
この地方きっての古刹で、真言宗の寺院
天平18(746)年に開基された山岳仏教の中心的存在であった古刹。弘法大師巡錫の地で、石見観音第11番札所
- [ 寺院 | あじさい ]
-
松江市外中原町179
松江藩初代藩主・松平直政は生母の月照院の霊牌安置所として、1664年(寛文4年)に、再興された松平家の菩提
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
出雲市大社町杵築東99-4
出雲大社の東隣に、出雲大社を中心とした古代出雲についての展示を行っている。荒神谷遺跡で発掘された銅剣(国宝
-
い 石見銀山遺跡
- [ 歴史 ]

-
大田市大森町
江戸幕府の財政を支えた有名な銀山
2007年7月、世界遺産として新たに登録された『石見銀山遺跡』。戦国時代後期から江戸時代前期にかけて最盛期
-
か 上の宮
- [ 神社 ]
-
出雲市大社町杵築北
稲佐海岸の近くに建つ出雲大社の境外摂社。
神在の7日間、神々は出雲大社境内の十九社で寝起きをし、上の宮で会議をされると云われています。背後に緑豊かな
- [ 歴史 ]
-
大田市大森町
鎌倉時代の末期、周防の国守大内氏によって発見された石見銀山(根県中央部の大田市)。江戸時代には徳川幕府の直
- [ 道・通り・街 | 歴史 ]
-
出雲市大津町~今市町
高瀬川は市街地中心部を東西に流れる川で、大梶七兵衛が私財を投じて開削した灌漑用水路。河畔には、今も古い街並
-
お お湯かけ地蔵
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
松江市松江しんじ湖温泉
松江しんじ湖温泉のはずれにある蔵様。健康を祈ってお参りする人も多く市民に親しまれ、毎年8月24日にはお湯か
-
な 長浜神社
- [ 神社 ]
-
出雲市西園町上長浜4258
「出雲国風土記」の冒頭を飾る「国引き神話」の国引きの神「八束水臣津野命」を主祭神として祀っている。武道・ス
-
と 唐人屋敷跡
- [ 歴史 ]
-
大田市大森町
銀精錬の技術を伝えた「唐人」(渡来人の総称)の屋敷と伝えられる場所の跡。
-
き 城上神社
- [ 神社 ]
-
大田市大森町宮ノ前
永享6年(1434年)、大内氏によって仁摩町馬路の高山から大森町愛宕山に遷座、寛政の大火により類焼し、後文
-
ま 松江神社
- [ 神社 | デート ]
-
松江市殿町1-5
松江城の二の丸にあの神社。松江は縁結びの地として有名で松平家の猪の目の紋も逆さにすればハートの形、ハート型
- [ 神社 ]
-
大田市大森町銀山
永享6年(1434年)創建と伝えられる鉱山の守り神。製錬の神「金山彦命」を祀る神社。全国一の規模の山神社で
-
ぶ 武家屋敷旧河島家
- [ 歴史的建造物 ]
-
大田市大森町ハ118-1
1800年代初めに建築された大森代官所に勤めた役人の武家屋敷。平成2年に復元された主屋に当時の生活用品を展
-
が 鰐淵寺
- [ 紅葉 | 寺院 ]

-
出雲市別所町148
 [ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]推古天皇2(594)年の創建と伝えられる天台宗の古刹。
中国観音霊場第25番札所、出雲観音霊場第3番札所、出雲國神仏霊場第2番札所。イロハモミジが色づく紅葉の名所
-
き 清水寺(安来市)
- [ 寺院 | 桜 | パワースポット ]
-
安来市清水町528
用明天皇2年(587年)、尊隆上人により開かれたと伝わる山陰屈指の名刹。本堂をはじめ、三重塔や古門堂、光明