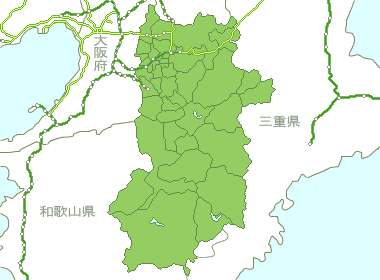神社・寺院・歴史 一覧

-
に 如意輪寺
- [ 寺院 ]
-
吉野郡吉野町吉野山1024
延喜年間(901年-922年)に日蔵上人により開かれたと伝わる。
南北朝時代、後醍醐天皇の勅願寺となった。裏山の松林には無念の思いで崩御した天皇の御陵が、京都に向かって築か
-
か 金屋の石仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-
桜井市金屋
コンクリート鉄格子戸の堂に安置された石仏。
金屋の家並みの中に高さ2.14m、幅83.5cm、厚さ21.2cmの2枚の岩に浮き彫りされた像は、右が釈迦
-
く 櫛山古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
天理市柳本町
古墳時代前期後半の古墳(双方中円墳)。
柳本古墳群の一つで、行燈山古墳の後円部に接して、より山側の高い位置にある。双方中円墳という日本では珍しい双
-
た 龍田神社
- [ 神社 | 紅葉 ]
-
生駒郡斑鳩町龍田1-5-3
崇神天皇の時代に創立され、法隆寺の鎮守とされていた。
伝承によれば、聖徳太子が法隆寺の建設地を探し求めていたときに、白髪の老人に化身した龍田大明神に逢い、「斑鳩
-
や 夜都伎神社
- [ 神社 ]
-
天理市乙木町765
水の神を祀る神社。
祭神は、武甕槌命・姫大神・経津主命・天児屋根命。春日大社との縁故が深く、江戸時代末期まで「蓮の御供」という
-
う 宇太水分神社
- [ 神社 ]
-
宇陀市菟田野古市場245
水分三座を祀る延喜式にもある大社。
国宝の本殿3棟は鎌倉時代の建物。3棟とも同形同大の一間社春日造りで、隅木入春日造で建立年代の明らかなものと
-
か 柿本神社
- [ 神社 ]
-
葛城市柿本187-3
柿本人麻呂ゆかりの地。
石見で死去した柿本人麻呂の遺骸を770(宝亀元)年にこの地に改葬し、社を建てたと伝わる。本堂には、紀僧正真
-
こ 弘仁寺
- [ 寺院 ]
-
奈良市虚空蔵町46
814(弘仁5)年に嵯峨天皇の勅願により、弘法大師が開基したと伝わる古刹。
通称、「高樋の虚空蔵さん」と呼ばれる。毎年4月13日の十三詣り(子供が数えで13になった時に智恵を授けても
- [ 神社 ]
-
奈良市薬師堂町24
元興寺五重塔跡の南西に鎮座する。
桓武天皇の御代、延暦十九年(800)に宇智郡霊安寺から勧請したもの。本殿には井上皇后(井上内親王)・橘逸勢
-
さ 狭井神社
- [ 神社 ]

-
桜井市三輪
第十一代垂仁天皇の御世(約二千年前)に創祀。荒魂をお祀りしている。正式名称は、狭井坐大神荒魂神社(さいにま
-
た 談山神社
- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 | パワースポット ]
-
桜井市多武峰319
 [ 紅葉時期 11月中旬~12月上旬 ]
[ 紅葉時期 11月中旬~12月上旬 ]木造では世界唯一の十三重塔をはじめとする重要文化財「社殿群」
鎌倉時代に成立した寺伝によると、藤原氏の祖である藤原鎌足の死後の天武天皇7年(678年)、長男で僧の定恵が
-
へ 平城宮跡
- [ 歴史 | 庭園 ]

-
奈良市佐紀町
平城京は710(和銅3)年に藤原京から遷都されて以来、74年間にわたり、日本の首都として栄えた場所。現在、
-
お 大野寺
- [ 寺院 | 桜 ]
-
宇陀市室生大野1680
宇陀川岸の自然岩に刻まれた弥勒磨崖仏があることで知られ、枝垂桜の名所としても知られる。
白鳳9年(681年)、役小角(役行者)によって草創され、天長元年(824年)に空海(弘法大師)が堂を建立し
-
に 丹生川上神社中社
- [ 神社 ]
-
吉野郡東吉野村小968
水を司る罔象女神を祀っている。
白鳳4年(675年)に罔象女神(相殿伊邪奈岐命・伊邪奈美命)を御手濯(みたらし)川(高見川)南岸の現摂社丹
-
ふ 不退寺
- [ 寺院 | 紅葉 ]

-
奈良市法蓮町517
法蓮町にある真言律宗の寺院。
大同4年(809年)、平城天皇が譲位してのち隠棲し「萱の御所」と称したのが始まりとされ、その後平城天皇の皇
-
め メスリ山古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
桜井市高田
古墳時代前期に築造されたと思われる全長224mの巨大な前方後円墳。別称は鉢巻山古墳、東出塚古墳などと呼称さ
-
あ 飛鳥坐神社
- [ 神社 ]
-
高市郡明日香村飛鳥707-1
鳥形山の森に鎮座する古社。
境内には、江戸時代に式内小社飛鳥山口坐神社(あすかやまぐちにますじんじゃ)が遷座している。大山津見命、久久
-
た 高山八幡宮
- [ 神社 ]

-
生駒市高山町12679-1
奈良時代(749年)、平城に宇佐八幡宮を移す際に仮に祀られたのが始まり伝わる。中世以降に地元の豪族・高山氏
-
あ 赤坂天王山古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
桜井市倉橋
後期古墳に属する方古墳。
南には横穴式石室が開いている。大きな石室で、巨大なくり抜き式の家形石棺が横たわっている。
-
な 奈良豆比古神社
- [ 神社 ]
-
奈良市奈良阪町2489
中殿に平城津比古大神(当地の産土神。奈良豆比古神とも)、左殿に春日宮天皇(施基親王、志貴皇子、田原天皇とも
-
な 中尾山古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
高市郡明日香村平田
終末期の八角墳。
天皇陵の特徴である八角形墳で、文武天皇の墓ではないかという説が有力だが、明らかではない。
-
ち 竹林院群芳園
- [ 寺院 | 庭園 | 桜 | 花 | 宿泊 ]
-
吉野郡吉野町吉野山2142
聖徳太子が創建した椿山寺の跡と伝えられる。
本堂には聖徳太子、役行者等の坐像を祀っている。庭園「群芳園」は、豊臣秀吉(豊太閤)が吉野山の桜の花見に際し
-
ち 長岳寺
- [ 寺院 | 紅葉 | 花 ]

-
天理市柳本町508
 [ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]824(天長元)年に弘法大師が創建。
天長元年(824年)に淳和天皇の勅願により空海(弘法大師)が大和神社(おおやまとじんじゃ)の神宮寺として創
-
か 橿原神宮
- [ 神社 | 初詣スポット ]

-
橿原市久米町934
橿原神宮創建の民間有志の請願に感銘を受けた明治天皇により、明治23年(1890年)4月2日に官幣大社として
-
ほ 法起寺
- [ 寺院 ]
-
生駒郡斑鳩町岡本1873
聖徳太子建立七大寺の一つに数えられることもあるが、寺の完成は太子が没して数十年後のことである。「法隆寺地域
- [ 寺院 ]
-
奈良市山町1312
斑鳩の中宮寺、佐保路の法華寺と共に大和三門跡と呼ばれる門跡寺院。
別名、山村御殿。後水尾天皇の皇女が営んだ寺で、山村御殿とも呼ばれる大和三門跡尼寺の一つ。非公開寺院のため拝
-
か 門僕神社
- [ 神社 ]

-
宇陀郡曽爾村今井733
雄略天皇の御代からあるという由緒ある古社。
通称、春日さんと呼ばれている神社。主神は天津児屋根命をお祀りしている。境内にある、葉にギンナンの実がなると
-
じ 浄安寺
- [ 寺院 ]
-
北葛城郡上牧町上牧335
開山は万治元年(1658)遷化の楽誉浄安大徳で、本堂は宝永5年(1708)に建立され、天保12年(1841
-
ま 松尾寺
- [ 寺院 | 花 ]

-
大和郡山市山田町683
境内にはバラ園があり、バラの名所としても知られる。
718(養老2)年に舎人親王(とねりしんのう)が厄除けを祈願して創建したと伝わる。日本最古の厄除け寺と称さ
-
や 山部赤人の墓
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
宇陀市榛原山辺三
奈良時代の歌人、三十六歌仙の一人の墓。
奈良時代万葉の歌人、山部赤人の墓で、五輪塔(高さ約156cm、石英粗面岩製)が、額井岳の東麓、東海自然歩道