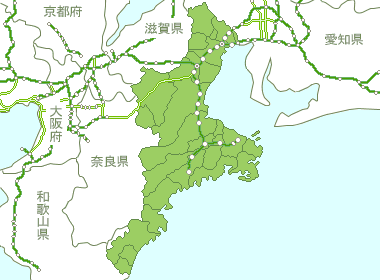神社・寺院・歴史 一覧

-
い 射和中万の町並み
- [ 歴史 ]
-
松阪市射和町・中万町
伊勢おしろいなどにより財を成した射和商人たちの邸が残る町並み。江戸末期の私設図書館「射和文庫」の竹川家、「
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]
-
伊勢市宇治浦田2-1-10
天孫降臨の際、その道案内をしたといわれる猿田彦大神と、その子孫の大田命を祭神とする神社。開運の神として信仰
- [ 神社 | パワースポット ]
-
鳥羽市相差町1237
神明神社には25柱の神が祀らている。石神さんは神明神社の参道にある社で、ご神体は神武天皇の母「玉依姫命(た
-
あ 汗かき地蔵
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-
志摩市大王町波切
その汗で吉凶を占うという伝説
昔、漁師の網にかかって引き上げられたといわれる波切の地蔵で、大漁や豊作の吉事の前には白い汗、反対に凶事の前
-
ひ 賓日館
- [ 歴史的建造物 ]

-
伊勢市二見町茶屋566-2
繊細な美しさをたたえる「賓日館」
明治20(1887)年に伊勢神宮に参拝する賓客の休憩・宿泊施設として建設された建物。貴賓の宿として幾多の華
-
れ 霊山寺(伊賀市)
- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 ]
-
伊賀市下柘植3252
伝教大師開基と伝える黄檗宗の寺。
最澄が開基したと伝えられる古刹。本尊は十一面観音世音菩薩で、像高1.8m、江戸時代初期のもの。参道周辺には
-
ま 松尾観音寺
- [ 寺院 | 観音 | パワースポット ]
-
伊勢市楠部町156-6
奈良時代(712年)の高僧行基による開基と伝わる古刹で、既成宗派に属さず檀家ももたない祈願寺。本尊「十一面
-
く 首切り地蔵
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
津市美杉町 飼坂峠
大和と伊勢を結ぶ伊勢本街道の一番の難所、飼坂峠の地蔵様で、けわしい峠越えの時に山賊などに襲われて犠牲になっ
-
つ 爪切不動尊
- [ 不動 ]
-
志摩市志摩町御座
金比羅山の麓にあり、弘法大師が真言密教を布教するための霊場といわれ、弘法大師自らの爪で自然石に不動明王像を
-
ら 来迎寺
- [ 寺院 ]
-
松阪市白粉町512
1500年代前半に松阪市松ヶ島に、北畠氏によって開創と伝える。蒲生氏郷の築城に伴い現在地に移転。長らく豪商
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
伊勢市神田久志本町1754-1
農林水産関係の標本・資料を展示。
神宮徴古館では伊勢神宮の祭や歴史・文化の資料を展示する。「式年遷宮」のご神宝類の展示は圧巻だ。農業館は人間
-
つ 椿大神社
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]

-
鈴鹿市山本町1871
別名を猿田彦大本宮、猿田彦大神を祀る神社の総本社。
天孫降臨の折りに神々の道案内をしたと伝わる。猿田彦大神を主神とする神社が全国に2000余りある中の総本宮。
-
み 美旗古墳群
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
名張市美旗町中1番、新田
伊賀地方を代表する古墳群で、県下最大の規模を誇る。全長140mはある前方後円墳の馬塚などを見ることができる
-
ゆ 結城神社
- [ 神社 | 梅 ]
-
津市藤方2341
白河結城氏の結城宗広を祀る建武中興十五社の一社。後醍醐天皇を奉じて「建武新政」の樹立に貢献した結城宗広公を
-
あ 愛洲の里
- [ 歴史的建造物 | 公園 ]
-
度会郡南伊勢町五ヶ所浦2366
五ケ所城跡周辺を整備した里公園
南北朝時代から戦国時代にかけて、南勢を中心に活躍した愛洲一族の城跡・居館跡をめぐる散策路が整備された公園。
-
た 多度大社
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]
-
桑名市多度町多度1681
「お伊勢参らばお多度をかけよ、お多度かけねば片参り」と謡われ、北伊勢大神宮と崇敬される神社。5月4・5日に
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 博物館・資料館 ]
-
松阪市飯南町粥見1125-1
茶の歴史と茶情報の発信の拠点。
伊勢茶の産地として有名な松阪市飯南町にある茶の資料館。実際に製茶できる35キロラインの製茶工場を併設してい
-
が 丸興山庫蔵寺
- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 ]
-
鳥羽市河内町539
825年(天長2)、弘法大師が朝熊山の金剛證寺を創建した際、奥の院として開創。子育ての寺として有名。本堂の
-
ふ 二見興玉神社
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]
-
伊勢市二見町江575
境内の磯合にある夫婦岩(めおといわ)で知られる。
夫婦岩の沖合約700mの海中に沈む、祭神・猿田彦大神縁の興玉神石を拝する神社。猿田彦大神は天孫降臨の際に高
-
き 近長谷寺
- [ 寺院 ]
-
多気郡多気町長谷
仁和元(855)年に伊勢の国の豪族「飯高宿禰諸氏」が建立した寺で、通称近長さん。御本尊十一面観音(国指定重
-
う 烏止野神社
- [ 神社 | 自然 ]
-
南牟婁郡紀宝町鵜殿104
慶長年間(1596~1615年)の創立と伝わる。明治末期、境内社の秋葉神社「諾、冉尊」、若宮神社「天照皇大
-
き 北畠氏館跡庭園
- [ 歴史 | 庭園 ]
-
津市美杉町上多気1148
北畠神社の境内にある日本三大武将庭園のひとつで国の名勝に指定されている。室町時代の見ごとな庭で、米字池、枯
-
う 浦神社
- [ 神社 ]
-
鳥羽市浦村町今浦
「浦の権現さん」と親しまれている浦村地区の氏神を祀る。境内にほとばしる岩清水が老眼や疲れ目によいという信仰
-
さ 斎宮跡
- [ 歴史 ]
-
多気郡明和町竹川
斎宮跡は、斎宮(斎王の居住した宮殿と、役所・斎宮寮)を中心とする遺跡。昭和54(1979)年に東西約2キロ
-
や 山田奉行所記念館
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
伊勢市御薗町上條1602
弘化2年(1845年)に、ほぼ全焼した山田奉行所を、翌弘化3年(1846)に新築したときの図面「新造小林役
-
じ 常安寺
- [ 寺院 | 遊歩道 ]
-
鳥羽市鳥羽2-12-3
樋ノ山の北麓にある寺で、九鬼水軍を率いて活躍した鳥羽藩初期の藩主・九鬼氏の菩提寺。本尊は釈迦如来坐像(室町
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
熊野市有馬町599
郷土のすぐれた民俗資料の収集と保存展示。古代遺跡から出土した縄文土器や、漁具、民具平ノート、郷土新聞など多
- [ 寺院 ]
-
伊賀市富永1238
1202年(建長2年)鎌倉時代、奈良東大寺再建大勧進の高僧、俊乗房重源上人が開いた真言宗の寺。本尊は盧舎那
- [ 歴史 | 体験施設 ]

-
多気郡明和町斎宮3046-25
斎宮がもっとも栄えたとされる平安文化や年中行事を体験できる。貴族女性の正装「十二単」や貴族男性の日常着「直
-
お 大馬神社
- [ 神社 ]
-
熊野市井戸町大馬
平安時代から祀られていると伝わる古刹。社殿脇に一枚岩から流れ落ちる大馬清滝がある。麓には、結婚式場をかねた