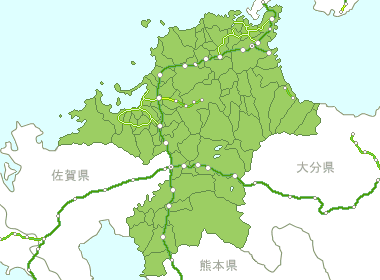神社・寺院・歴史 一覧

-
あ 有馬記念館
- [ 歴史的建造物 | 博物館・資料館 | 見学 ]
-
久留米市篠山町444
有馬家資料を中心とした久留米藩政資料を主に展示公開
久留米城跡が整備された当時、株式会社ブリヂストンの石橋正二郎氏から寄贈された記念館。久留米歴代藩主の武具、
-
あ 安国寺(嘉麻市)
- [ 寺院 ]
-
嘉麻市下山田288
足利尊氏の創建で、一国一所の勅願寺の一つ。
当初は七堂伽藍をそなえた大寺だったが、数度の火災により再建を繰り返して現在に至る。境内には筑前の刀工信国一
-
あ 綾塚古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 見学 ]
-
京都郡みやこ町勝山黒田綾塚
巨岩を使った横穴式石室は全国第3位の規模。景行天皇の妃、八坂入姫命を祠ってある。
九州自然歩道沿線にあり、6世紀後半につくられたと推定される円墳。横穴式石室には家型の石棺が安置されていて、
- [ 城 | 桜 | 紅葉 | 見学 ]
-
朝倉市秋月野鳥
1624(寛永元)年に黒田長政[くろだながまさ]の三男長興[ながおき]が秋月五万石を与えられて築城した
かつて通用門の役目をした大手門「黒門」「長屋門」周辺は、秋は紅葉の名所として有名で、モミジやイチョウが美し
- [ 神社 ]
-
福岡市西区愛宕2-7-1
福岡県内随一の参拝者数を誇る神社。
創始は景行天皇2年(西暦72年)、鷲尾山に伊耶那岐尊・天忍穂耳尊を祀ったのが鷲尾神社(鷲尾権現)の始まりと
-
あ 青木繁旧居
- [ 歴史 ]
-
久留米市荘島町431
青木繁に関する写真パネルや解説パネル、青木繁の作品の複製などを展示
日本近代美術史を語るうえで欠かせない著名な画家・青木繁の旧居を復元し、一般に公開。写真パネルや解説パネル、
-
あ 現人神社
- [ 神社 ]
-
筑紫郡那珂川町仲3-7-8
わが国で最も古い神社の一つ
神功皇后が海を渡って戦いに行く際に、航海と水の神様が皇后の前に姿をあらわし、船を守りながら目的地まで導いた
-
あ 秋月城跡
- [ 城 | 歴史 | 桜 | 紅葉 ]
-
朝倉市秋月野鳥
 [ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]昭和55年(1980年)、「秋月城跡」として県の史跡に指定
建仁3(1203)年に古処山城の麓にあった秋月氏の館跡を利用して築かれた平城で、福岡藩の支藩秋月藩の藩庁で
-
あ 秋月の町並み
- [ 歴史街道 ]

-
朝倉市秋月
筑前の小京都秋月
朝倉市の北部、古処山のふもとに城下町として栄えた秋月。今では「筑前の小京都」といわれ、秋月目鏡橋や秋月城跡
-
い 岩戸山古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
八女市吉田1396-1
北九州最大規模の前方後円墳。
全長約135メートル、後円部径約60メートル、前方部幅約90メートルの前方後円墳であり、北部九州地方最大で
-
い 岩屋神社
- [ 神社 | 自然地形 ]
-
朝倉郡東峰村宝珠山
天から飛来したと伝えらてる宝株石がご神体。
本殿の宝珠石は天から降ってきた石と伝えられ、地名の由来にもなっている。宝珠とは、仏教用語で「何でも願いが叶
-
い 岩屋城跡
- [ 城 | 歴史 | 公園 | 桜 ]
-
太宰府市四王寺山
四王寺山中腹の岩屋城跡からは、桜に囲まれて太宰府を一望することができる
四王寺山の中腹にある戦国時代の山城跡。天正14(1586)年に薩摩島津氏の大軍に攻められた大友宗麟の家臣高
-
い 伊都国歴史博物館
- [ 歴史 | 博物館・資料館 | 見学 ]
-
糸島市井原916
古代伊都国が栄えたといわれる、糸島地方に残る考古資料を一般公開。
魏志倭人伝に登場する「伊都国」の地と推定されている糸島市内で発掘された貴重な遺物や考古資料を多数公開してい
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
田川郡福智町弁城165-2
鎌倉時代の英彦山山伏の嶺入り修験を物語る貴重な資料として県の指定文化財に指定。
建武2(1335)年に法橋良密によって岩屋権現の大岩に金剛界四印会曼陀羅が刻まれた梵字曼荼羅。英彦山山伏の
-
い 五玉神社
- [ 神社 | 見学 ]
-
朝倉郡筑前町三箇山1144-1
彦山・宝満修験の入峯の道筋にあたり、山伏の修行の場だった神社。
安産と子宝に霊験あらたかな神社として知られている。5つの石殿がありそれぞれ大きな石の玉が安置されている。ま
-
い 伊野天照皇大神宮
- [ 神社 | 見学 ]

-
糟屋郡久山町猪野604
本殿から鳥居に至るまで伊勢神宮に模して造られている。
通称伊野神社と呼ばれる伊野天照皇大神宮は、九州の伊勢といわれ、神殿も伊勢神宮を模して築造している。境内には
-
い 板付遺跡
- [ 歴史的建造物 | 碑・像・塚・石仏群 | 見学 ]
-
福岡市博多区板付3-21-1
日本で最初に米作りをした弥生時代のムラで、最古の二重環濠集落。
日本最古の水田跡が発見された板付遺跡に、弥生時代の集落を再現。ガイダンス施設の弥生館内では、弥生時代の農具
-
い 居蔵の館
- [ 歴史的建造物 ]
-
うきは市吉井町1103-1
白壁が目を引く土蔵造りの屋敷「居蔵の館(旧松田家)」。
精蝋業で財をなした大地主の分家の住居として、明治末期に建造された主屋は入母屋の妻入り建物で、一部を除き白漆
-
い 石塚山古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 自然 | 見学 ]
-
京都郡苅田町富久町1
九州最大最古の定型化した典型的な畿内型前方後円墳。
全長約110mの古墳は九州最大規模で、最古クラスの畿内型前方後円墳。竪穴式石室からは、三角縁神獣鏡14面や
-
い 飯塚市歴史資料館
- [ 歴史 | 博物館・資料館 | 見学 ]
-
飯塚市柏の森959-1
「飯塚地方の歴史と文化」をテーマに、考古・歴史・民俗・石炭の資料などを展示。
飯塚市内で発見された立岩遺跡から出土した前漢鏡をはじめとする貝輪、鉄器などの考古資料、宿場町時代の道具など
-
う 宇美八幡宮
- [ 神社 | パワースポット ]
-
糟屋郡宇美町宇美1-1-1
神功皇后様安産伝承の地として今も安産、育児の崇敬をあつめる。
神功皇后が新羅遠征帰還の折に、この地で応神天皇を出産したと伝わり、神功皇后、応神天皇ほかを祀る。安産の神様
-
え 円清寺
- [ 寺院 ]
-
朝倉市杷木志波5276
黒田藩筆頭家老の栗山大膳の父利安が主君のため創建。
藩主黒田如水が死去した慶長9(1604)年にその冥福を祈るために栗山備後利安が建立。龍光山円清寺の山号寺号
-
え 恵蘇八幡宮
- [ 神社 ]
-
朝倉市山田151
『木の丸殿』跡と伝わる恵蘇八幡宮
斉明天皇と天智天皇を祀り、獅子唐をはじめ、数々の社宝をおさめる朝倉市の総社。恵蘇八幡宮の由来「恵蘇八幡宮・
-
え 永勝寺

- [ 寺院 | 紅葉 ]
-
久留米市山本町豊田2155
 [ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]創建680年。日本三大薬師の一つに数えられています。
皇后の病気を平癒するために祈願されたとされ、「出雲の一畑」「伊予の山田薬師」と共に日本三大薬師の一つに数え
-
お 大富神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
豊前市大字四郎丸256
現在は、大富神社と称するが、古来は宗像八幡社とも称され、大富神社神輿の古い鏡には大富ノ神とも宗像ノ神とも記
-
お 大中臣神社のフジ
- [ 神社 | 花 | 見学 ]
-
小郡市福童555
フジは、征西将軍宮懐良親王が1359年(正平14年)大保原合戦の折り負傷され、大中臣神社に祈り全快された記
約600年前に懐良親王が奉納したと伝えられる将軍藤が有名。およそ500平方メートルの藤棚にみごとな花房を付
-
お 大野城跡

- [ 城 | 碑・像・塚・石仏群 ]
-
糟屋郡宇美町四王寺、大野城市乙金、太宰府市大宰府ほか
市の北に、なだらかに広がる四王寺山頂にある山城。
宇美町、太宰府市、大野城市にまたがる四王寺山に、大和政権によって大宰府防衛のために築かれた朝鮮式山城。全周
- [ 歴史 | 博物館・資料館 | 見学 | 特産 ]

-
大牟田市宝坂町2-2-3
江戸時代に作られた雅を伝える「歌カルタ」や、当時の世相を反映した「いろはカルタ」など、約1万点の収蔵品の中
日本のカルタ発祥の地、大牟田にある国内唯一のカルタの資料館。日本のカルタはポルトガル人の影響を受け、16世
-
お お菊大明神
- [ 神社 ]
-
嘉麻市上臼井847-3
芝居や映画でおなじみの怪談の主人公であるお菊さんを祀っている。
その舞台となった皿屋敷跡や、お菊さんが身を投げたと伝えられる井戸などがある。腰から下の病気が治るというご利
-
お 大己貴神社
- [ 神社 | 見学 ]

-
朝倉郡筑前町弥永697-3
日本書紀巻九に記されている「大三輪社」であると云われる神社。
筑前町弥永にある神社で、通称「おんがさま」。社の起源は古く、神功皇后が三韓征伐で発願したといわれていて、日