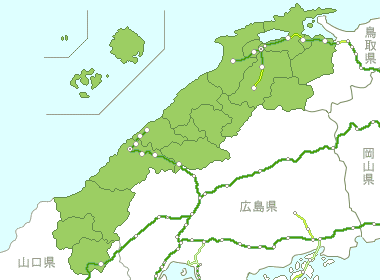神社・寺院・歴史 一覧

-
じ 乗光寺庭園
- [ 寺院 | 庭園 ]
-
松江市東出雲町上意東1919
乗光寺は高野山真言宗の寺。創建は平安時代末期と伝わり、古い歴史をもち、貴重な文献資料も数多く保有している。
- [ 歴史的建造物 | 歴史 | 庭園 ]
-
松江市北堀町305
江戸初期から松江藩中級藩士が屋敷替えによって入れ替り住んだ屋敷。庭園は飾りを排した素朴なつくりで、屋敷や長
-
や 山祇神社のツバキ
- [ 神社 | 花 ]
-
鹿足郡吉賀町真田
山祇神社の境内に21本の巨大なツバキ(県の天然記念物)が群生している。周囲2.8m、高さ10m、樹齢は60
-
ひ 日御碕神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
出雲市大社町日御碕455
下の本社は天暦2年(948年)、村上天皇勅命により祀り、上の本社は安寧天皇13年(紀元前536年)、勅命に
-
か 春日神社の黒松群

- [ 神社 ]
-
隠岐郡隠岐の島町布施
地区の氏神として信仰を集める神社の境内の横に、樹齢100年以上のクロマツ群がある。なかには樹齢350年以上
-
か 金屋子神社
- [ 神社 ]
-
安来市広瀬町西比田
金屋子神は、タタラ場や鍛冶屋で信仰されている神
中国地方を中心に関東、東北の一部まで広がっている金屋子神の総本社。境内には神木である桂の巨木がそびえ、荘厳
- [ 歴史的建造物 | 博物館・資料館 | 庭園 | 紅葉 ]

-
仁多郡奥出雲町上阿井1655
 [ 紅葉時期 10月下旬~11月中旬 ]
[ 紅葉時期 10月下旬~11月中旬 ]江戸時代にこの地で製鉄業を営んだ鉄山師頭取の屋敷としての風格を今に伝える国の重要文化財。
この庭は、享和3年(1803)、松江藩七代藩主松平治郷(不昧公)の御成の迎えたときに造られた。たたらの鉄師
-
は 浜田城跡
- [ 城 | 歴史 | 公園 | 桜 ]
-
浜田市殿町
浜田市街の亀山とよばれる小山が、かつての浜田城の跡
小高い丘にあり、元和6(1620)年の築城以来石見地方の政治の拠点となっていた。今は石垣だけが残る。幕末の
-
り 龍雲寺(浜田市)
- [ 寺院 ]
-
浜田市三隅町芦谷
1382年(永禄2年)三隅信兼の開基、無端祖環の開山により創建されたと伝えられ、以後三隅氏の菩提所となった
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]
-
松江市八雲町熊野2451
意宇川上流に鎮座する古社。出雲大社の祭神・大国主命の父にあたり、八岐の大蛇を退治したことでも有名な素戔嗚尊
-
ち 中間長屋
- [ 歴史的建造物 ]
-
大田市大森町宮ノ前
下級役人の武家屋敷「中間長屋」
銀を収納した蔵の番を担当するお金蔵番、銀山取締や夜警、役所と銀山の連絡係である御門番など大森陣屋に勤めた中
-
や 柳原家
- [ 歴史的建造物 ]
-
大田市大森町新町
代官所の銀山付同心遺宅
質素な中にも武家住宅の体裁が間取りや玄関に示されている。一見平屋のように見えるが、背面は2階建てとなってい
-
た 龍御前神社
- [ 神社 ]
-
大田市温泉津町温泉津
創建は1532年(天文元年)と伝えられる神社。
石見銀山華やかなりし頃、船の守り神として信仰を集めた神社。温泉街を見下ろす岩山にあり背後の「龍岩(tatu
-
さ 佐志武神社
- [ 神社 ]
-
出雲市湖陵町差海
「出雲国風土記」では、「佐志牟社」として記される古社。
出雲風土記に佐志牟の社として記されている。毎年、10月18・19日には佐志武神社例大祭神事華が行われる。例
- [ 神社 ]
-
邑智郡邑南町矢上
約1000年、荒れ地を開拓するために農耕を勧める神を、信州・諏訪神社から分霊し祭っている。樹齢約1000年
-
こ 荒神谷史跡公園
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 公園 ]
-
出雲市斐川町神庭873-8
昭和59(1984)年に大量の銅剣が、翌年には銅鐸と銅矛が発見され、一躍脚光を浴びた遺跡をそのまま、史跡公
-
さ 西楽寺
- [ 寺院 ]

-
大田市温泉津町温泉津イ727-1
大阪石山合戦への顕如上人からの依頼状が残されている寺院。
大永元(1521)年に開基した浄土真宗本願寺。大坂石山合戦への顕如上人からの依頼状が残されている。江戸時代
-
う 鵜丸城址
- [ 城 | 歴史 ]
-
大田市温泉津町温泉津
鵜丸城は中世の港湾として繁栄した沖泊の南側の丘陵突端に位置する標高59m(比高55m)の海城。
毛利氏によって元亀2年(1571に毛利水軍の拠点として約1か月で築城されたことが「児玉伝右衛門家文書」(萩
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
雲南市吉田町吉田4210-2
江戸時代、製鉄する場所を「高殿」、製鉄に従事していた人達の職場や、住んでいた地区を「山内」と呼ばれた。全国
-
と 富田八幡宮
- [ 神社 ]
-
安来市広瀬町広瀬
平家の武将が月山富田城を築城する際、月山にあった勝田神社をこの地に奉還した八幡宮。長い石段の奥に、楼門や本
-
お 岡田山古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
松江市大庭町
1号墳(前方後方墳)と2号墳(円墳)および5基の小規模な古墳からなる。1号墳から出土した銀の文字入り太刀や
- [ 歴史的建造物 | 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
鹿足郡津和野町後田ロ66甲
西周や森鴎外など多くの人材を輩出した藩校跡。
江戸時代に建てられた津和野藩の藩校。西周、森鴎外もここで学んだ。今は剣術道場、書庫などが残るのみ。剣術道場
-
ま 万福寺
- [ 寺院 | 庭園 ]

-
益田市東町25-33
本堂の裏に雪舟が文明年間(1469~87)に手がけた築山泉水庭の庭園がある古刹。本堂は鎌倉時代の手法を伝え
-
ろ ローソク岩観音岩
- [ 観音 | 自然地形 ]
-
隠岐郡西ノ島町浦郷
奇岩怪礁の中で細長くそびえたつ岩。日が沈むころには、ローソクに火を灯したように見え、百済観音の姿にも見える
-
お 大久保長安の墓
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
大田市大森町
江戸幕府勘定奉行、大久保長安の墓と、大久保長安(初代石見奉行)の銀山に対する功績をたたえた碑がある。大安寺
-
し 志都岩屋神社
- [ 神社 | 名水 ]
-
邑智郡邑南町岩屋
弥山(標高606m)にある志津岩屋神社境内の裏山では、鏡岩や行場岩、飛岩など巨岩が数多く見られる。巨大石の
-
ひ 比婆山久米神社
- [ 神社 ]
-
安来市伯太町横屋844-1
標高約280mの山上のある神社、熊野神社(比婆山久米神社)。『古事記』によると伊弉冉尊が祀られた場所とされ
-
み 彌久賀神社
- [ 神社 ]
-
出雲市湖陵町大池
出雲国風土記に「美久我社」、延喜式神名帳に「彌久賀神社」と記載されている古社。毎年10月17日には、神事華
-
や 弥栄神社
- [ 神社 ]
-
鹿足郡津和野町稲成丁
津和野大橋のたもとに大鳥居がある弥栄神社。正長元年(1428年)三本松城主吉見氏が祇園社の分霊を太鼓谷山に
-
い 岩屋寺跡横穴群
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
松江市玉湯町玉造
横穴は、古墳時代の墓制のひとつです。2つの穴が、凝灰質砂岩(来待石)の岩盤に掘り込まれてる。右の穴の中は2