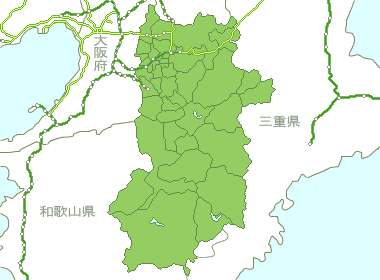神社・寺院・歴史 一覧

-
せ 船宿寺
- [ 寺院 | 桜 | 花 ]
-
御所市五百家484
四季折々の花を見ることができる花の寺。
神亀2年(725年)に行基菩薩がこの地で草庵を造り薬師瑠璃光如来を祀ったことが船宿寺のはじまりと伝わる。門
-
せ 青蓮寺
- [ 寺院 ]
-
宇陀市菟田野区宇賀志1439
中将姫が継母により捨てられた地。
浄土宗の尼寺で約1200年前、中将姫が建立したと伝えられる。寺宝に中将姫の画像や彫像、曼荼羅図などがある。
-
む 室生龍穴神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
宇陀市室生区室生1297
室生寺よりも歴史の古い神社(延喜式内の古社)
水の神、タカオカミ神(竜神)を祀る古社で、室生寺よりも古い歴史をもつ。巨大な杉に囲まれ、境内は厳粛な雰囲気
-
き 金勝寺
- [ 寺院 ]

-
生駒郡平群町椣原53
聖武天皇の御代、天平十八年(746年)、行基菩薩の発願のより創建と伝えられる古寺。たび重なる戦禍で焼失と再
-
ひ 檜原神社
- [ 神社 ]

-
桜井市三輪
大神神社の摂社で元伊勢の一つ、天照大御神を祀る。
御神体は磐座と神籬で本殿や拝殿はなく、独特の形をした三輪鳥居だけが立っている。香具山、畝傍山、耳成山をはじ
-
わ 和爾下神社
- [ 神社 ]
-
天理市櫟本町2430
前方後円墳の後円部に建てられた神社。
古代豪族の和爾氏の祖神を祭っている。桃山建築様式の本殿は重文で桃山時代の建築様式を残す。参道には、柿本人麻
-
し 聖林寺
- [ 寺院 ]

-
桜井市下692
藤原鎌足の長子、定慧が創建したと伝わる。
伝承では和銅5年(712年)に妙楽寺(現在の談山神社)の別院として藤原鎌足の長子・定慧(じょうえ)が創建し
-
す 水分神社
- [ 神社 | 自然 | 桜 | 紅葉 | 花 ]
-
吉野郡上北山村小橡
地元の氏神である水神を祀る。
祭神に天之水分(あめのみくまり)神と、国之水分神を祀り、1450年代(長禄年間)以前の創建と伝う。境内に植
-
だ 達磨寺
- [ 寺院 ]
-
北葛城郡王寺町本町2-1-40
聖徳太子が達磨像を刻み、祀ったのが始まると伝わる。
達磨寺の境内には達磨寺1号墳・2号墳・3号墳と称される3基の古墳(6世紀頃の築造)が存在し、このうちの3号
- [ 寺院 | 花 ]

-
高市郡高取町壺阪3
創建は大宝3年に元興寺の弁基上人により開かれたとされる。
京都の清水寺の北法華寺に対し南法華寺といい、長谷寺とともに古くから観音霊場として栄えた。本尊の十一面観音は
-
ほ 法起院
- [ 寺院 ]
-
桜井市初瀬776
天平7年(735年)、初瀬の道明上人の弟子、徳道上人が開いた長谷寺の開山堂。長谷寺に続く参道沿いに門を構え
- [ 寺院 ]

-
生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1
聖霊院は西院伽藍の東側に建つ、聖徳太子を祀る堂。鎌倉時代の建立。この建物は本来は東室の一部であったが、11
-
や 山田寺跡
- [ 寺院 | 歴史 ]
-
桜井市山田
蘇我石川麻呂がの発願により7世紀半ばに建て始められ、石川麻呂の自害(649年)の後に創建した。昭和57(1
-
あ 阿対の石仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
奈良市柳生町
室町時代に彫られた阿弥陀如来。
古くから、左側の地蔵に豆腐を供えると子宝に恵まれると言われている。願いが叶うと千個の数珠を作って供える習慣
-
き 金峯山寺
- [ 寺院 | パワースポット ]

-
吉野郡吉野町吉野山2498
吉野山のシンボルで世界遺産。
金峰山修験本宗(修験道)の本山。本尊は蔵王権現、開基(創立者)は7世紀に活動した伝説的な山林修行者・役小角
-
く 楠正勝の墓
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
吉野郡十津川村武蔵
滝バス停付近に大塔宮(護良親王)の御詠碑が建っている。
楠正成の孫で、楠正勝は弟とともに金剛山落城のあと南朝再起をはかって十津川で兵を募ったが、病に倒れこの地に葬
-
さ 西光寺(宇陀市)
- [ 寺院 | 桜 ]
-
宇陀市室生31
室生寺の西、小高い中腹に立つ融通念仏宗の寺。
この寺の城之山桜と呼ばれるコイトシダレは、樹齢約300年、大野寺の桜の親木だとも伝えられている。隠れた花見
-
す 菅原天満宮
- [ 神社 ]
-
奈良市菅原町518
菅家の祖廟であり、菅原家発祥の地。
祭神は天穂日命・野見宿禰・菅原道真。菅原道真が牛に乗って大宰府に流されたという故事にちなみ、境内には牛の像
-
し 称念寺
- [ 寺院 ]

-
橿原市今井町3-2-29
本願寺一家衆であった今井兵部豊寿を開基とする寺。
本尊は阿弥陀如来。今井御坊とも称される。大和五ヶ所御坊、十六大坊の1つで中本山に列する。称念寺本堂は200
-
し 四社神社
- [ 神社 ]
-
宇陀郡御杖村菅野2309
神殿は神明造四間社で、四社大明神とも称す。
四柱(天照大神・春日大神・八幡大神・熊野大神)を祀る神社で、伊勢街道を通る旅人が、お参りをしたという。社域
-
し 新薬師寺
- [ 寺院 ]

-
奈良市高畑町1352
国宝の本堂は奈良時代の創建。
奈良時代には南都十大寺の1つに数えられ、平安時代以降は規模縮小したが、国宝の本堂や奈良時代の十二神将像をは
-
お 大和神社
- [ 神社 ]

-
天理市新泉町306
崇神天皇時代の創建と伝わる古社。
十六社・二十二社の一社で、旧社格は官幣大社。中殿に日本大国魂大神、左殿に八千戈大神、右殿に御年大神を祀る。
-
か 葛城一言主神社
- [ 神社 ]
-
御所市森脇432
願い事を一言のみ叶えてくれると信仰を集めて「いちごん(じ)さん」と呼ばれ親しまれている。神宮寺として一言寺
-
こ 興福寺 三重塔
- [ 寺院 ]

-
奈良市登大路町48番地
境内の片隅に観光客もなくひっそりとたたずむ国宝。康治2年(1143年)、崇徳天皇の中宮・皇嘉門院により創建
- [ 寺院 ]
-
大和高田市内本町10-19
大和五ヶ所御坊の1つで高田御坊とも言われる。
1600年(慶長5年)、本願寺12世准如上人によって創建された浄土真宗の寺。本願寺直属の掛所御坊として寺内
-
り 霊山寺(奈良市)
- [ 寺院 | 花 ]
-
奈良市中町3879
736(天平8)年、聖武天皇の勅命で行基菩薩が建立したと伝わる。境内にある八体仏霊場では十二支と星座を組み
-
う 烏土塚古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
生駒郡平群町春日丘1-4
平群氏族長の墓といわれる前方後円墳。
墳丘長60.5m、前方部幅31m、後円部径35mの前方後円墳で平群谷最大規模の古墳。石棺の側壁に斜格子文様
-
か 上宮遺跡公園
- [ 歴史 | 公園 ]
-
生駒郡斑鳩町法隆寺南3
聖徳太子ゆかりの宮跡。
聖徳太子が住んでいたという言い伝えが残っている土地にある奈良時代の大規模な遺跡群跡を整備した公園。宮殿級の
-
か 鴨都波神社
- [ 神社 ]

-
御所市宮前町514
積羽八重事代主命(事代主)と下照姫命を主祭神とし、建御名方命を配祀する。葛城氏・鴨氏によって祀られた神社。
-
こ 金剛寺(吉野郡)
- [ 寺院 ]
-
吉野郡川上村神之谷212
後南朝の中心となった古刹。
天武天皇の白鳳時代に大峯山の開祖・役行者の開基と伝えられる。瓦葺き入母屋造りの本堂は前面二間が吹き通しにな