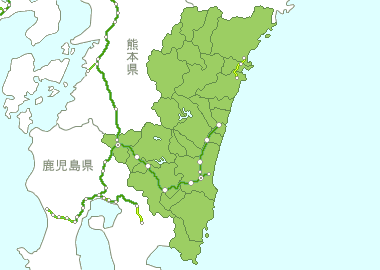神社・寺院・歴史 一覧

-
く くし触神社
- [ 神社 ]
-
西臼杵郡高千穂町三田井1037
瓊瓊杵尊が降り立ったといわれるくしふる岳の麓にある神社。本殿(高千穂町の有形文化財)は三間社流造銅板葺で、
-
く 黒水家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
児湯郡高鍋町上江1390
高鍋藩家老屋敷・黒水家の住宅
高鍋藩主秋月氏の家老職を務めた黒水家の住宅で、家老屋敷と呼ばれている。建築年代は、構造等から文化・文政頃(
-
そ 宗麟原供養塔
- [ 歴史 ]
-
児湯郡川南町川南1274
天正6年(1578年)11月12日に、島津氏・大友氏と間で繰り広げられた九州争覇戦「高城合戦(耳川の戦い)
-
ほ 法華岳薬師寺
- [ 寺院 ]
-
東諸県郡国富町深年4050
和泉式部が参籠したという伝説が残る古寺。宮崎県の重要文化財に指定されている本尊の薬師三尊像は天文15(15
-
み 都城島津邸
- [ 歴史的建造物 ]

-
都城市早鈴町18-5
日本でも有数の名家で、薩摩藩主として名高い島津家。
南北朝時代から都城の領主であった都城島津家の明治以降の邸宅。昭和48年小林市での全国植樹祭に出席された昭和
- [ 観音 | 浸かる | 公園 | 湖・沼・池 | 桜 | 花 ]
-
都城市高城町石山4305-10
園内には3000本の桜と5万本のツツジを植栽。ゴーカート、パターゴルフ、観覧車、スライダー、草スキー、流水
-
み 妙国寺庭園
- [ 寺院 | 庭園 ]
-
日向市細島373
妙国寺は薩摩阿闍梨日叡上人が康永年間(1342~1345)に開山したと伝えられる名刹。本堂南にある庭園は池
-
み 宮崎神宮

- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]

-
宮崎市神宮2丁目4-1
狭野杉[さのすぎ]で作られた神明流造の社殿には、神武天皇とその父母を祭る。
旧官幣大社、大正2年(1913)7月4日宮崎神宮と改称。東神苑には樹齢400年以上と推定される「オオシラフ
-
う 鵜戸神宮

- [ 神社 | 初詣スポット | 日の出 | パワースポット ]

-
日南市宮浦3232
日南海岸の景勝地
日向灘に面した自然の洞窟の中に朱塗りの本殿が建ち、神武天皇の父・鵜葺草葺不合命[うがやふきあえずのみこと]
-
か 神柱宮
- [ 神社 ]
-
都城市前田町1417-1
天照皇大神と豊受姫大神を主神とする神社。
島津荘の開拓のために大宰府より移住した平季基が、万寿3年(1026年)、天照皇大神の神託を受けて伊勢神宮よ
- [ 城 | 公園 | 自然 | 花 ]
-
延岡市東本小路178
延岡城の跡地を整備してつくられた公園。周辺に自生しているヤブツバキ群は、日本三大ヤブツバキ群の一つ。花色は
-
つ 鶴富屋敷
- [ 歴史的建造物 ]
-
東臼杵郡椎葉村下福良1818
平家落人伝説のヒロインとして民謡「ひえつき節」に唄われる鶴富姫が住んでいた那須家住宅(なすけじゅうたく)。
-
つ 都萬神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
西都市妻1
コノハナサクヤ姫を祀る神社。古くから妻万様の愛称で親しまれ、縁結びと安産の神様として名を広めている。日本酒
-
う 宇納間地蔵
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
東臼杵郡美郷町北郷区宇納間1
全長寺の仁王門を抜け、長い石段(365段)を上ると鉄城山頂。全長寺にに祀られている地蔵尊は防火のご利益があ
-
さ 狭野神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
西諸県郡高原町蒲牟田120
霧島六所権現の一社。神武天皇の生誕の地とされ、神武天皇の幼名、狭野尊を祀る。孝昭天皇の時代、神武天皇が誕生
-
だ 大雄寺の雲板
- [ 寺院 ]
-
東臼杵郡美郷町西郷区田代1431
大雄寺に伝わる銅製の宝具で、「明徳2年」(1391年)の銘が彫られている。修行僧の食事や起床などの合図に鳴
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
児湯郡西米良村村所2-5
資料館では国の重要有形民俗文化財の焼畑農耕用具や旧領主菊池家縁の品などを収蔵・展示。
-
は はにわ園
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 公園 ]
-
宮崎市下北方町越ヶ迫6146 平和台公園内
平和台公園の北側一角にあり、林の中の小道に沿って、色々な種類のはにわと土偶が400体ほど並ぶ。これらはすべ
-
み 神門神社
- [ 神社 ]
-
東臼杵郡美郷町南郷区神門69-2
養老2年(718年)奈良時代の創建とされる神社。重文の本殿には8柱の神と百済国から亡命した偵嘉王を合祀。社
-
あ 荒立神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
西臼杵郡高千穂町三田井宮尾野667
天孫降臨の神話に出てくる猿田彦命(さるたひこのみこと)と、天照大神が岩戸から出てくるのを願って踊った神様、
-
あ 綾城
- [ 城 ]
-
東諸県郡綾町北俣1012
築城は1331年~1334年で足利尊氏の家臣であった細川小四郎義門が築いたと言われる。別名・竜尾城現在の木
-
い 石神神社
- [ 神社 ]
-
西臼杵郡高千穂町岩戸8463
1674年(延宝2)古記録には牛神大明神(ウシガミダイミョウジン)とあり、十社大明神(現高千穂神社)の使牛
-
え 江田神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
宮崎市阿波岐原町産母127
国産み神話で知られる伊邪那岐命(イザナギノミコト)、伊邪那美命(イザナミノミコト)の両神を祀る縁結びや安産
- [ 歴史的建造物 ]
-
宮崎市佐土原町上田島1601-2
旧阪本家は江戸時代から続いた味噌・醤油醸造販売を営んでいた商家を一般公開している。木造瓦葺き2階建ての建物
-
じ 浄専寺のしだれ桜
- [ 寺院 | 桜 ]
-
西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所8701
浄専寺は江戸初期(1615年)の建立といわれる古寺。春に満開の花をつける樹齢およそ300年のしだれ桜があり
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
西臼杵郡高千穂町三田井1515
高千穂町の遺跡や伝説に関する資料など1万点を展示。旧石器時代から近代までの歴史、古代から伝わる夜神楽・方言
-
ほ 本庄古墳群
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
東諸県郡国富町町内本庄地区
前方後円墳17基、円墳37基、横穴墳2基、地下式横穴墳1基の57か所が国の史跡に指定されている。全長90m
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
宮崎市芳士2258-3
蓮ヶ池横穴群がある蓮ヶ池史跡公園内にある歴史文化館。宮崎の歴史、民俗芸能に関する資料や、蓮ヶ池横穴群に関す
-
や 八戸観音滝
- [ 観音 | 自然 | 川・滝・渓谷 ]
-
西臼杵郡日之影町八戸
2月の大祭では名物のだるまも売られ、多くの人でにぎわう。
落差45mの滝。滝の左岸に巨大な洞窟があり、その中に祀られている3体(聖観世音菩薩像・如意輪観世音菩薩・子
-
よ 榎原神社
- [ 神社 ]
-
日南市南郷町榎原甲1134-4
江戸時代初期の万治元年(1658年)に飫肥藩の鎮守として、鵜戸神宮から勧請し建立。祀神は天照大神で、縁結び