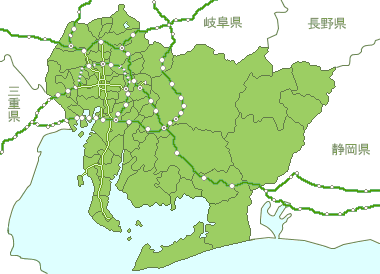神社・寺院・歴史 一覧

-
さ 三明寺
- [ 寺院 | 見学 ]
-
豊川市豊川町波通37
豊川弁天の名前で親しまれている曹洞宗の寺院
地元では弁天様として親しまれる古刹。緑豊かな境内は、四季折々の自然が美しい。本尊の弁財天は、平安時代に大江
-
す 嵩山の蛇穴
- [ 歴史 | 自然 ]
-
豊橋市嵩山町浅間下92
本坂トンネルのそばにある、国の史跡。
天然の石灰洞窟は、奧に入るにしたがって広くなっています。洞窟の深さは約75m。蛇穴という名前の由来は、大蛇
-
せ 赤岩寺
- [ 寺院 | 桜 ]
-
豊橋市多米町赤岩山4
聖武天皇の勅願により行基が神亀3年(726年)に創建。本尊は聖観音。参道の脇には桜の古木があり、春は美しい
-
ま 万葉の小径
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 見学 | 遊歩道 ]
-
蒲郡市西浦町稲村
西浦温泉東の小高い丘にある、稲村神社に通じる役500mほどの遊歩道。
西浦半島の先端、御前崎の山頂にある稲村神社へ続く約500mの万葉の小径と呼ばれる遊歩道沿いには、ところどこ
-
き 清洲公園
- [ 歴史的建造物 | 公園 | 桜 | 紅葉 | 見学 ]
-
清須市清洲3-7-1
大正11年(1922)清洲城跡に開園したもので、桜、つつじの名所として賑う
五条川を挟んで清洲城の対岸に位置する公園。豊かな緑に包まれた市民憩いの場所で、園内の一角には桶狭間の戦いに
-
こ 恋の水神社
- [ 神社 | デート | パワースポット | 珍スポット ]
-
知多郡美浜町奥田中白沢92-91
縁結びの神として若い女性の参拝客が絶えない。
無病息災の神として信仰を集めてきたが、恋人のために水を探した桜姫の伝説にちなんで、恋の水神社という名前が付
-
じ 城宝寺
- [ 寺院 | 見学 ]
-
田原市田原町稗田48
浄土宗。渡辺崋山の菩堤寺で東海七福神のひとつ。
渡辺崋山の菩提寺として名高い寺。霊牌堂の格天井には松林桂月画伯ほか日本有数の画家及び書家が執筆しており、そ
-
き 清洲古城跡
- [ 城 | 歴史 | 見学 ]
-
清須市清洲古城448
慶長15年(1610)の清洲越しの後も現在に至るまで清洲城城跡地として保存され、幕末の清洲城跡顕彰碑2基や
清洲越しにより廃城となった清洲城の跡地。静かな公園となっており、信長を祀る小社や石碑などが点在する。現在の
-
ざ 財賀寺
- [ 寺院 | 見学 ]

-
豊川市財賀町観音山3
真言宗。聖武天皇の勅願により僧行基が建立した道場。
聖武天皇の勅願により僧・行基が建立した。当時は七堂伽藍を配した無類の寺院であったが、応仁年中兵火にかかり2
-
に 西尾の町並み
- [ 歴史的建造物 | 歴史 | 見学 ]
-
西尾市
三河の小京都、西尾は歴史を身近に感じられる城下町。車が行き交う表通りから一歩入れば、板塀と石垣が続く細い路
-
な 長久手古戦場
- [ 歴史 ]

-
愛知郡長久手町武蔵塚204番地
羽柴秀吉(1586年、豊臣賜姓)陣営と織田信雄・徳川家康陣営の間で行われた戦役。
1584(天正12)年、豊臣秀吉と徳川家康・織田信雄の連合軍が戦った小牧長久手の戦いで有名な古戦場。古戦場
-
ほ 鳳来寺
- [ 寺院 | パワースポット ]

-
新城市門谷鳳来寺1
鳳来寺山の中腹にある寺で薬師信仰や山岳修験の霊山として信仰を集めた
大宝3(703)年、利修仙人によって創建されたいわれる真言宗の古刹。本堂は1425段の石段を登った上に立ち
-
く 鞍船遺跡
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 | 見学 ]
-
北設楽郡設楽町津具鞍船9
縄文時代前期(約6,000年前)の竪穴式住居跡で建物は日本最古の復原家屋である
縄文時代前期の竪穴式住居跡。家屋を復元したもの。1922(大正11)年に発見され、6墓発見されたうちの2墓
-
こ 弘法山金剛寺
- [ 寺院 ]

-
蒲郡市三谷町南山14
三河新四国の1つで真言宗。金剛寺のある弘法山の山頂には30メートルの高さを誇る子安弘法大師像が立つ。
昭和13(1938)年、篤信者の財閥が子授を願い、子安弘法大師像を建立。子授以外にも安産、子育、交通安全、
-
こ 小牧市歴史館
- [ 歴史 | 博物館・資料館 | 桜 | 見学 ]
-
小牧市堀の内1-1
小牧・長久手の合戦パノラマ、商家コーナー、小牧山コーナー等小牧市の郷土資料が展示され、4階は天望室になって
小牧山山頂にある小牧市歴史館(小牧城)。京都の西本願寺飛雲閣を模した鉄筋コンクリート造り、3層4階建ての建
-
ふ 二子古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 桜 | 見学 ]
-
安城市桜井町二夕子5-16
矢作川流域で最大規模を誇る桜井古墳群にあって、もっとも大きな墳丘を持つ古墳時代前期の前方後方墳。
三河を代表する前期古墳群である桜井古墳群。その古墳群において前方後円墳である二子古墳は全長68メートルで最
- [ 寺院 | あじさい | 見学 ]
-
額田郡幸田町深溝内山17
深溝松平氏の菩堤寺。別名「あじさい寺」とも呼ばれ、近県では屈指の紫陽花の名所となっている
約15種数万本のアジサイが咲く参道が有名。早春にはツバキや梅などが咲き誇る花の名所だ。世界の椿を集めた「三
-
ほ 本證寺
- [ 寺院 | 見学 ]
-
安城市野寺町野寺26
浄土真宗。鎌倉時代初期の創建といわれる。
戦国時代の城郭寺院の代表的な存在といわれる。広大な境内は二重の堀で囲まれ、正門、太鼓楼、鐘楼の基壇、本堂外
-
ま 曼陀羅寺
- [ 寺院 | 公園 | 花 | 見学 ]
-
江南市前飛保町寺町202
日輪山曼陀羅寺は西山浄土宗に属する寺院で、通称「飛保の曼陀羅寺」と呼ばれている。
後醍醐天皇が国家の安泰を願って創建した古刹。曼陀羅寺には8カ寺が位置し、国の重要文化財をはじめとして県・市
-
い 伊賀八幡宮
- [ 神社 | 歴史的建造物 | 見学 ]
-
岡崎市伊賀町東郷中86
松平四代・親忠が松平家の氏神として三重県の伊賀から迎え、武運長久・子孫繁栄を祈願するための八幡宮を祀ったも
徳川家の祖・松平家の氏神として四代親忠が伊賀から迎えた八幡宮。九代目にあたる家康も大きな合戦の際に戦勝祈願
- [ 城 | 博物館・資料館 ]
-
新城市長篠市場22-1
1575年(天正3)、武田勝頼と織田信長・徳川家康の連合軍が戦った長篠合戦の際、徳川軍の最前線となった長篠
武田勝頼軍1万5千の猛攻に耐えた城。織田・徳川軍の大勝利となった設楽原決戦の場所でもある。現在は土塁・内堀
-
ほ 布袋の大仏
- [ 寺院 | 珍スポット B級スポット ]
-
江南市木賀町大門132
線路から見えるコンクリートの大仏。
温顔の大仏は、名鉄犬山線の車窓からも見ることができる。春には桜が美しく咲き、大仏様を彩る。像は高さは18m
- [ 神社 ]

-
名古屋市中村区中村町茶ノ木
豊臣秀吉生誕の地
戦国時代の武将、豊臣秀吉の生誕地を記念して1885年(明治18)に建立されたのが、中村公園内にある豊国神社
- [ 神社 ]
-
清須市清洲2272
宝亀2年(771)、当地方で流行り病が蔓延した為、素盞嗚命と大己貴命の分霊を勧請し厄災退散の祈願を行ったの
-
ほ 堀田家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
津島市南門前町1-2-1
重要文化財に指定された民家。初代は福島正則に仕え、後に子孫が酒造業を営んで財をなし、さらに金融業や新田開発
-
ま 満光寺
- [ 寺院 | 見学 ]
-
新城市下吉田田中140
武田軍に追われた徳川家康がこの寺に宿をとり、朝、ニワトリがいつもより早く鳴いたため、武田軍の朝駆けを免れた
-
ふ 普門寺
- [ 寺院 | 自然 | 紅葉 | 見学 ]
-
豊橋市雲谷町ナべ山下7
真言宗。奈良時代、行基の開山と伝えられる。戦によって何度か火災にあったが、今川義元により再興された。
鎌倉街道が通っていたといわれる雲谷町に位置する古刹。国の重要文化財の木造阿弥陀如来坐像、木造釈迦如来坐像、
-
ふ 深川神社
- [ 神社 | 初詣スポット ]

-
瀬戸市深川町11
無病息災や子孫繁栄など、瀬戸市民を守護する神社。
鎌倉時代に宋で陶法を学び伝承した陶祖・加藤四郎左衛門景正が奉納した、重要文化財のこま犬がある。境内には加藤
-
す 洲崎神社
- [ 神社 | 見学 ]
-
名古屋市中区栄1-31-25
1912年(明治45年)それまで独立して奉祀されていた洲崎神社と石神神社が合祀されて「洲崎神社」となり、現
貞観年間(859~877)に創建されたと伝えられる古社。境内には、道祖神、石神鳥居があり、縁結びをはじめ、
- [ 寺院 | 庭園 | 花 ]
-
知立市八橋町
毎年4月下旬~5月中旬にかけて、約3万本のカキツバタが咲く。
平安時代の歌人、在原業平が「伊勢物語」に詠んだことで有名な八橋のカキツバタ。無量寿寺境内の心字池を中心とし