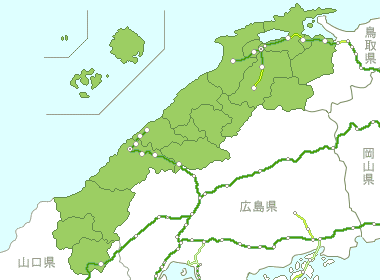神社・寺院・歴史 一覧

- [ 神社 ]
-
大田市温泉津町温泉津沖浦
県指定文化財の謎の梵鐘があることで知られています。
大久保長安(石見守)の逆修塚(生前に建てる墓)が残されている。大久保長安は、銀山の外港である温泉津港の振興
-
と 洞光寺(雲南市)
- [ 寺院 ]
-
雲南市木次町木次671
出雲七福神のひとつ、えびす様を祀り、商売繁盛にご利益のあることで知られる。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)
-
し 庄屋屋敷 内藤家
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
大田市温泉津町温泉津
龍御前神社の先ある豪商屋敷。
代々庄屋であった廻船問屋「梅田家」の屋敷。特徴ある『なまこ壁』、玄関にかけられた縄のれんなど当時の賑わいを
-
い 巌倉寺
- [ 寺院 ]
-
安来市広瀬町富田562
聖武天皇の神亀三年(726年)に建立されたと伝わる古刹。本尊の聖観音と毘沙門天像は国の重要文化財。境内には
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 公園 | アウトドア ]
-
松江市宍道町白石1405-1
古墳のある森を整備した公園。テニスコート、フィールドトリムコース、芝生広場などのほか、ログハウス風ケビンが
-
と 戸田柿本神社
- [ 神社 ]
-
益田市戸田町
柿本人麻呂生誕の地といわれる益田市郊外の戸田に8世紀頃建てられた神社。近くには遺髪を埋葬した墓、人麻呂碑文
-
つ 津和野城跡

- [ 城 | 歴史 | 展望台 ]
-
鹿足郡津和野町後田
鎌倉時代に吉見頼行が永仁3年(1295年)より29年かけて築城した城。別名「三本松城」とも呼ばれる。今は解
-
こ 光明寺(雲南市)
- [ 寺院 | 桜 ]
-
雲南市加茂町大竹292
曹洞宗の古刹。山中にあって四季折々の風情がすばらしい。南北朝時代に朝鮮から渡来した銅鐘は国の重要文化財に指
-
た 玉作湯神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
松江市玉湯町玉造508
『延喜式』・『出雲国風土記』にも登場する古社。玉造温泉を発見した少彦名命(温泉の神)、天照大神に八尺勾玉を
-
お 隠岐神社
- [ 神社 | 桜 ]
-
隠岐郡海士町海士
承久の乱(1221年)により海士に配流になり、在島19年、60歳で他界した後鳥羽天皇(配流時は法皇)を祀る
- [ 神社 | 公園 | 桜 ]
-
益田市七尾町
七尾城跡のそばにある神社。
境内が公園として整備され、周辺をソメイヨシノ約500本が彩る。サクラの他にも、ショウブやフジなどの花の名所
-
そ 染羽天石勝神社
- [ 神社 ]
-
益田市染羽町
神亀2(725)年の創建と伝えられる古社。朱塗りの本殿は、華麗な透かし彫りや細工を施した桃山時代を代表する
- [ 寺院 | 名水 ]

-
大田市大森町イ-804
1764年に開創された真言宗の古刹。名水「三百水」が湧く寺として有名。亡くなった銀山坑夫の霊を弔い造った五
-
け 華蔵寺(松江市)
- [ 寺院 ]
-
松江市枕木町205
華蔵寺は臨済宗南禅寺派の末寺で、標高456mの枕木山の上に位置する禅宗の古刹である
薬師堂に安置される薬師如来坐像は平安末期の作で国の重文。石造りでは大きさ日本一といわれる不動明王像が有る。
-
ひ 人丸神社
- [ 神社 ]
-
江津市島の星町
高角山の麓にある、江津市ゆかりの万葉歌人、柿本人麻呂を祀る神社。妻への想いを詠んだ「石見のや高角山の木の際
-
あ 浅原才市の銅像
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
大田市温泉津町温泉津
石だたみの広場の中央にある妙好人浅原才市の像。
浅原才市は、嘉永4年(1851)生まれ。昭和の妙好人といわれ、町の人々に慕われ尊敬されました。毎年安楽寺で
-
し 勝定寺
- [ 寺院 | 庭園 | ツツジ ]
-
出雲市馬木町59
16世紀創建の禅寺。本堂脇から入る庭園は、枯山水、心字池を擁する回遊式。前庭は安土桃山時代の豪華さを表現し
- [ 神社 | パワースポット ]

-
出雲市佐田町須佐730
須佐之男命を祀る古社。例大祭の「念仏踊」が有名。
『出雲国風土記』に記されている古社。須佐は須佐之男命の終焉の地といわれ、祭神も須佐之男命。そのために古来、
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
浜田市旭町本郷362-9
旭町で発掘された古墳を復元。竪穴住居が復元展示してあり、古代人の暮らしぶりが実感できる。記念館に出土品や資
-
い 医光寺
- [ 寺院 | 庭園 ]
-
益田市染羽町4-29
前身は天台宗の崇観寺という寺院で、貞治2年/正平8年(1363年)の創建と伝えられ、医光寺はその塔頭であっ
-
え 円通寺(雲南市)
- [ 寺院 ]
-
雲南市掛合町多根329
行基の創建といわれる天台宗の古刹。行基が作ったと伝えられる秘仏・如意輪観世音菩薩(にょいりんかんぜおんぼさ
-
か 観音滝
- [ 観音 | 自然 | 川・滝・渓谷 | 紅葉 ]
-
江津市桜江町鹿賀
鹿賀谷川に懸かる滝
観音滝県立自然公園の中にある高さ約50mの岸壁を滑り落ちる珍しい三段滝。3段目がもっとも落差があり、岩肌を
-
い 揖夜神社
- [ 神社 ]
-
松江市東出雲町揖屋2229
「出雲風土記」「日本書紀」に登場する神社。意宇六社の一つ。かつては黄泉国に縁の深い社として中央でも重視され
-
い 石見国分寺跡
- [ 寺院 | 歴史 ]
-
浜田市国分町
国重要文化財
天平13(741)年に聖武天皇の請によって建立されたもので、現在は金蔵寺の境内にある。当時は規模の大きさを
-
さ 西本寺
- [ 寺院 | 庭園 ]
-
大田市大森町ホ209
寛永8年に創建された寺。山吹城解体後、元山吹城にあった追手門が移築されており、寺内には、江戸中期につくられ
-
た 太皷谷稲成神社
- [ 神社 | 初詣スポット ]

-
鹿足郡津和野町後田409
通称「津和野おいなりさん」。全国で唯一「いなり」を「稲成」と表記する。
京都の伏見稲荷の神霊を移した神社。稲荷神社のなかでも「稲成」と表記するのはここだけ。大願成就の祈りが込めら
- [ 教会 ]
-
鹿足郡津和野町後田ロ66-7
昭和6(1931)年、ドイツ人シェーファによって建てられたゴシック建築の教会。武家屋敷が立ち並ぶ殿町にあり
-
さ 西念寺(大田市)
- [ 寺院 ]
-
大田市温泉津町温泉津イ787
毛利元就にゆかりの古刹。
毛利元就が九州の立花城を攻めた際に、手柄のあった然休上人を開基とした浄土宗の寺院。世界の銀産出の三分の一と
-
え 円成寺(松江市)
- [ 寺院 ]

-
松江市栄町792
松江開府の祖堀尾家をまつる寺
堀尾3代の菩提寺で,忠晴の木像をはじめ堀尾氏ゆかりの遺品がある。
-
く 熊谷家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
大田市大森町ハ63
熊谷家住宅は、寛政12年(1800)におこった町並みの大火後、享和元年(1801)に建築され以後、土蔵など