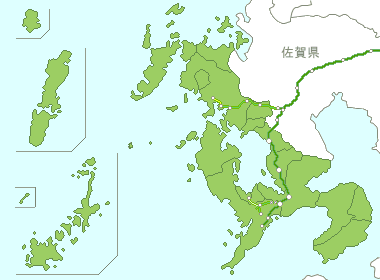神社・寺院・歴史 一覧

-
あ 天岩戸神社
- [ 神社 ]
-
西臼杵郡高千穂町岩戸1073番地1
岩戸川を挟んで東本宮と西本宮がある。戸川対岸の断崖中腹にある「天岩戸」と呼ばれる岩窟(跡)を神体とする。西
-
あ 安国寺
- [ 寺院 ]
-
壱岐市芦辺町深江栄触546
足利尊氏・直義兄弟が暦応年間(1338~42)に全国60余州に建てた安国禅寺の一つに数えられる。仏殿の床が
-
あ 青砂ヶ浦天主堂
- [ 教会 ]
-
南松浦郡新上五島町奈摩郷1241
「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」を構成する教会堂のひとつ。
五島列島の中通島北部、奈摩湾を望む高台に建つレンガ造りの教会堂。明治43(1910)年に教会堂建築士として
-
あ 淡島神社
- [ 神社 | 桜 | パワースポット | 珍スポット B級スポット ]
-
雲仙市南高来郡国見町神代西里
神代西里地区にあり、縁結び、安産、子育てに霊験があるとされる。
文化9年(1812年)神代藩主10代鍋島茂體公の時代に、亀川出羽守忠英という人によって建立されました。淡島
-
い 岩戸神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
雲仙市瑞穂町西郷丁2322
古くから「岩戸さん」の愛称で地元の人々に親しまれている神社
縄文人が住んでいたと言われている洞窟が御神体。水源の森に静かに佇む。
-
い 壱岐風土記の丘
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
壱岐市勝本町布気触324-1
古墳館も整備され、壱岐の古墳群散策を楽しむ玄関口
掛木古墳をはじめ点在する古墳をめぐりながら散策できる歴史公園。古民家園には壱岐独特の百姓武家建築を移築復元
-
い 壱岐文化村
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
壱岐市郷ノ浦町片原触410
江戸時代からの民具を集めた民芸美術館。
民芸美術品や失われてしまった暮らしの中の道具など、壱岐の昔の暮らしを実感できる。隣接して湯川温泉・壱州本陣
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
大村市今富町586-1
大村市郊外にあるキリシタンの墓碑。
大村藩主純忠とともに洗礼を受けた重臣、一瀬越智相模栄正(おちさがみえしょう)の墓碑で、戒名が刻んであります
-
い 一覧橋
- [ 歴史的建造物 | 橋 ]
-
長崎市桶屋町
現在はコンクリートアーチ橋となってしまった。
長崎市内に数ある石橋の一つで、明暦3(1657)年に高一覧が架橋。1795年流出し1801年再架設。198
-
い 生月大魚籃観音
- [ 観音 B級スポット ]
-
平戸市生月町山田免570-1
ブロンズ像としては日本一の大きさです。
生月大橋から見える舘浦の小高い丘にそびえる大魚籃観音(生月観音堂‎)。ブロンズ像では日本屈指の
-
い 井持浦教会
- [ 教会 | 歴史的建造物 ]

-
五島市玉之浦町玉之浦1243
明治28年(1895年)にフランス人宣教師ペルー神父によって建てられたロマネスク様式の教会。ここには、聖母
-
う 梅ヶ谷津偕楽園
- [ 歴史的建造物 | 歴史 | 展望台 ]
-
平戸市明の川内町348
平戸藩主第35代松浦熈公の別邸
当時の建物や庭園、熈直筆の書、食器等を展示しています。御用窯の中野焼と三川内焼の茶碗や皿など200点ほどが
-
う 上野彦馬宅跡
- [ 歴史 ]
-
長崎市伊勢町4-14
彦馬はここで坂本龍馬を撮影したといわれる。
日本初のプロカメラマンとして知られる上野彦馬。この場所は、文久2(1862)年に創設した上野撮影局があった
-
う 梅園身代り天満宮
- [ 神社 ]
-
長崎市丸山町2
元禄13年(1700)創建の丸山町の氏神様。
昔から“身代り天神”と呼ばれ親しまれてきた天満宮。名妓愛八をはじめ、多くの遊女が訪れたという料亭花月の裏門
-
う 浦上天主堂
- [ 教会 ]

-
長崎市本尾町1-79
宣教する教会をめざして
キリシタン弾圧に苦しんだ信徒たちによって建てられました。現在の建物は1959年に鉄筋コンクリートで再建され
-
え 江上教会
- [ 教会 ]
-
五島市奈留町大串1131
大正6(1917)年、御堂造りの名人鉄川与助により建立されたロマネスク様式の教会。コウモリ天井とステンドグ
-
お 大浦教会
- [ 教会 ]

-
長崎市南山手町2-18
長崎大司教区が大浦天主堂の隣接地に建立した教会
国宝大浦天主堂が、観光客の増加に伴い、司牧のためには不都合となってきたため、昭和50年(1975)11月、
-
お 男嶽神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
壱岐市芦辺町箱崎諸津触
御祭神は猿田彦命(さるたひこのみこと)。石猿群で知られる。拝殿横の石段に200体を超す石猿が並んでいる。か
-
お 大曽教会
- [ 教会 ]
-
南松浦郡新上五島町青方郷2151-2
豊かな緑に囲まれた美しいレンガ造りの教会。
1879年(明治12)に建造され、現在の建物は1916年(大正5)に鉄川与助の設計施工で再建されたもの。ス
-
お 男獄神社
- [ 神社 | 珍スポット ]
-
壱岐市芦辺町箱崎本村触
標高約150mの深く険しい男岳山頂にある神社。
昔は、牛を奉納していたが、現在は200体以上の石猿が並ぶ。この地区で習慣がある子孫繁栄、商売繁盛などを願っ
-
お 鬼の岩屋
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 自然地形 ]
-
壱岐市芦辺町国分本村触
石室は壱岐の島・島内最大のもの。
壱岐では、古墳内部の石室のことを「鬼の窟」と呼んでいる。芦辺地区に現存する壱岐最大の円墳(直径45メートル
-
お 御橋観音寺
- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 ]

-
佐世保市吉井町直谷94
 [ 紅葉時期 11月中旬~11下旬 ]
[ 紅葉時期 11月中旬~11下旬 ]平戸八景の一つに数えられる。
境内の北部にかかる天然の石橋は平戸八景の一つ。高さ約20m、幅約4m、厚さ約2mの二条の大橋は、天下の奇勝
-
お 温泉神社
- [ 神社 ]
-
雲仙市小浜町雲仙319
島原半島に点在する温泉神社の総本山。
雲仙温泉郷の真ん中に鎮座する島原半島一帯の温泉神社の総本山。701(大宝元)年、奈良時代の名僧行基が建立し
-
お 大村純忠史跡公園
- [ 歴史 | 公園 ]
-
大村市荒瀬町1116
大村純忠終焉の居館跡を中心とした歴史公園。
藩主の座を退いた大村純忠が、晩年信仰生活を送った「坂口館」跡を整備。入口には中世の武家屋敷に広く用いられた
-
お 大浦国際墓地
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
長崎市川上町
1861年に開かれた国際墓地。
文久元(1861)年、安政の開国後に設けられた川上町の丘に墓碑が並ぶ。アメリカ人水兵の墓や、丸山花月の門前
-
お オランダ坂
- [ 歴史 ]

-
長崎市東山手町
外国人が闊歩した居留地にある坂
昔、長崎の人は東洋人以外の外国人をオランダさんと呼び、居留地の坂をすべてオランダ坂と呼んだ。オランダ坂の中
-
お 沖之島天主堂
- [ 歴史的建造物 ]

-
長崎市伊王島町2-617
沖之島の高台に立つゴシック様式の白亜の天主堂。島民の願いで明治23年(1890年)に本聖堂が建立された。そ
-
お 大浦天主堂

- [ 教会 ]

-
長崎市南山手町5-3
現存する日本最古の天主堂(国宝)。
元治元年(1864年)、フランス人プチジャン神父の尽力によって完成した。現存するものでは日本最古の木造ゴシ
-
か 金田城跡
- [ 城 | 歴史 ]
-
対馬市美津島町黒瀬城山515-2
667(天智6)年、大陸からの侵略にそなえて大和朝廷が築いた朝鮮式山城の金田城。高さ2m以上の城壁と城門、
-
か 勝本城跡
- [ 城 | 歴史 ]
-
壱岐市勝本町坂本触城ノ越757
豊臣秀吉の秀吉の朝鮮出兵(文禄の役)に際して急造された武末城の城跡公園。現在は石垣の遺が残るのみ。展望台か