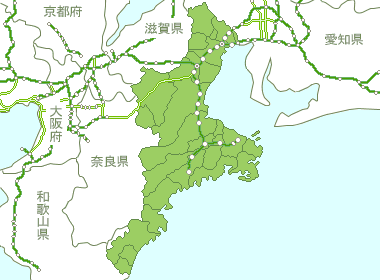神社・寺院・歴史 一覧

-
う 上野天神宮
- [ 神社 ]
-
伊賀市上野東町2929
別名を上野天神宮と呼ばれ(通称お天神さん)学問の神様・菅原道真公を主神とする神社。松尾芭蕉が29歳の時に俳
-
あ 飛鳥神社
- [ 神社 ]
-
尾鷲市曽根町
江戸期までは「阿須賀大明神」と呼ばれ、過去には和歌山県新宮市の阿須賀神社の末社で1000年以上の歴史をもつ
-
か 亀山市歴史博物館
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
亀山市若山町7-30
亀山市の歴史がわかる博物館。常設展示室では「モノとの対話」をテーマに展示を行っている。企画展示室では年2回
-
し 照源寺
- [ 寺院 ]
-
桑名市東方1308
寛永元年(1624年)桑名藩主松平隠岐守定勝公(徳川家康公の異父弟)のご逝去に際し二代将軍徳川秀忠公の台命
-
な 夏見廃寺展示館
- [ 寺院 | 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
名張市夏見2759
7世紀末から8世紀前半に建てられたと推定され古代寺院跡。大来皇女が父、天武天皇のために建てた昌福寺とする説
-
は 花窟神社
- [ 神社 ]

-
熊野市有馬町
日本書紀にも登場する日本最古の神社といわれる。ご神体は45mの巨大な岩でイザナミノミコトを祀る。毎年2・1
-
ま 松阪商人の館
- [ 歴史的建造物 ]
-
松阪市本町2195
江戸で紙や木綿を手びろく商いしていた松阪商人・小津清左衛門の屋敷跡を公開。建物は17世紀末から18世紀初め
-
と 東林寺
- [ 寺院 ]
-
いなべ市北勢町川原2913-1
奈良時代の行基の開山といわれる古刹。境内に「養老の裏滝」と呼ばれる白滝がある。
- [ 不動 | 花 ]
-
松阪市飯高町赤桶1076-3
数千株のつつじが一帯に咲き誇る。
香肌峡県立公園内にある荒滝不動尊付近には数千本のツツジがあり、4月中旬から下旬にかけて山全体が真紅の花でお
-
あ 敢國神社
- [ 神社 ]
-
伊賀市一ノ宮877
斉明天皇4年(658年)の創建と伝えられる古社で、御祭神は四道将軍の一人として活躍した大彦命ほか二柱(少彦
-
な 長野氏城跡
- [ 城 | 歴史 ]
-
津市美里町桂畑
南北朝期の国人領主である長野氏の居城跡として昭和57年に国指定史跡に認定されている。
-
い 伊勢上野城跡
- [ 城 | 歴史 ]

-
津市河芸町上野
織田信長の弟、信包が永禄12(1569)年に城手となり津城の仮城として改修築城した伊勢上野城。信長に攻めら
-
お 尾鷲神社
- [ 神社 ]
-
尾鷲市北浦町12-5
鳥居の横に大きな夫婦の楠の木(樹齢1000年以上)がそびえる神社で、スサノオノミコトを祀っている。この神社
-
ふ 古市の町並み
- [ 歴史 ]
-
伊勢市古市
伊勢神宮の外宮と内宮を結ぶ伊勢街道沿いの町で、参宮帰りの精進落としで賑わった遊里(歓楽街)、芝居小屋、旅籠
-
つ 津城跡
- [ 城 | 歴史 ]
-
津市丸之内
織田信包が天正8(1580)年に津城を創築。別名・安濃津城(あのつじょう)。本丸を中心に出丸を置き、北は安
-
ふ 福王神社
- [ 神社 ]
-
三重郡菰野町田口2404
聖徳太子が1200年前に奉じたと伝えられる毘沙門天を安置したといわれる歴史ある神社。毘沙門天は、日本では福
-
か 観菩提寺 正月堂
- [ 寺院 ]
-
伊賀市島ケ原1349
天平勝宝3(751)年、奈良東大寺の実忠和尚創建の古刹。楼門、本堂、そして33年に一度しかご開帳されない本
-
き 北畠神社
- [ 神社 | 庭園 ]
-
津市美杉町上多気1148
寛永20年(1643年)、北畠一族の末裔・鈴木孫兵衛家次が、耕地となっていた当地(北畠氏居館跡)に小祠を設
-
よ 夜泣き地蔵
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
北牟婁郡紀北町海山区 馬越峠
熊野古道の馬越峠にある祠で、元々は旅人の無事を祈る石地蔵だったと言われるが、やがて子供の夜泣き封じを祈る「
-
せ 関地蔵院
- [ 寺院 ]
-
亀山市関町新所1173-2
天平13(741)年、行基によって開創と伝えられる古刹で、本尊地蔵菩薩座像は日本最古の地蔵菩薩といわれる。
-
い 伊賀上野の町並み
- [ 歴史 ]
-
伊賀市上野中町
藤堂高虎が築城した上野城を中心に開けた伊賀上野の町は、城下町独特の碁盤の目になっていて、武家屋敷や古い町家
-
き 霧山城跡
- [ 城 | 歴史 | 展望台 ]
-
津市美杉町上多気
南北朝時代興国4年(1343)年に北畠顕能(あきよし)が築いた標高560mの山城跡。天正4(1576)年、