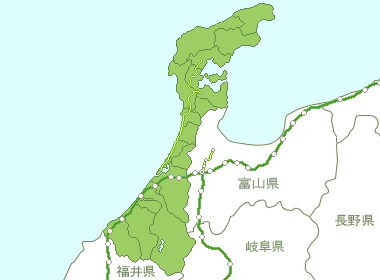神社・寺院・歴史 一覧

- [ 寺院 | 川・滝・渓谷 | 紅葉 | 乗り物 ]

-
加賀市大聖寺八間道87
加賀百万石の支藩として栄えた城下町・大聖寺地区にある川下りが体験できる。夜間特別運行に加え、春は花見、秋は
-
き 金剱宮
- [ 神社 | パワースポット ]
-
白山市鶴来日詰町巳118-5
崇神天皇3年に創建とされる古社。白山七社のうちの一つで、そのうち白山本宮(白山比�盗_社)・三宮・岩本とと
-
み 妙鏡寺つつじ園
- [ 寺院 | 花 ]
-
かほく市多田ホ49
5月初めから中旬頃、寺の裏手一面に、キリシマ、オオムラサキ、リュウキュウなどさまざまなツツジが一斉に花開く
-
し 白山比め神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
白山市三宮町ニ105-1
霊峰白山を神体山とするパワースポット。
北陸鎮護の大社。全国に2,000社以上ある白山神社の総本宮として白山信仰の中心となっている。また、「加賀一
-
ほ 本家上時国家
- [ 歴史的建造物 ]
-
輪島市町野町南時国13-4
平時忠の血を引く21代当主が天保2(1831)年に建てた入母屋茅葺き、最大級の近世木造民家。総欅の玄関や書
-
が 岩壁の母碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
羽咋郡志賀町富来領家町
増穂浦海岸の砂丘地に建つ碑。有名な「岸壁の母」のエピソードのモデルとなった女性を記念する碑だ。異国の地にと
-
せ 専光寺
- [ 寺院 ]
-
加賀市山代温泉17-225
室町時代に京都から北陸へ逃れてきた蓮如が立ち寄ったことで知られる寺。蓮如が数珠と袈裟を掛けたと伝えられる袈
-
し 聖興寺
- [ 寺院 ]
-
白山市中町56-1
加賀の千代女(江戸時代の女流俳人)の史跡。境内には千代女愛用品を展示する加賀の千代女の記念館「遺芳館」や、
-
だ 大本山總持寺祖院
- [ 寺院 ]

-
輪島市門前町門前1-18甲
元亨元(1321)年建立の歴史を持つ曹洞宗の大本山。通称、能山あるいは岳山とも呼ばれる。明治31(1898
-
ま 真脇遺跡縄文館
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 博物館・資料館 ]

-
鳳珠郡能登町真脇48-100
真脇縄文遺跡から出土した土器、石器、木柱、装飾品などを展示する博物館。縄文土器づくりなどの体験が出来る体験
-
く 倶利迦羅不動寺
- [ 寺院 | 不動 | 桜 ]
-
河北郡津幡町倶利伽羅リ2
718(養老2)年に元正天皇の勅願により、中国から渡来したインドの高僧、善無畏三蔵(ぜんむいさんぞう)法師
-
げ 源平古戦場
- [ 歴史 ]
-
河北郡津幡町倶利伽羅
石川、富山両県の県境にある古戦場。木曽義仲と平維盛が戦った。義仲は牛の角に松明をつけ、あたかも軍勢に見立て
-
た 平家
- [ 歴史的建造物 | 庭園 ]
-
羽咋郡志賀町町30-63
平維盛の重臣平式部太夫は、倶利伽羅の戦いで大敗して以降、能登の守護畠山氏にその由緒と武名をかわれて七尾城に
-
こ 小立野寺院群
- [ 寺院 ]
-
金沢市小立野
石引周辺にある寺院の総称。藩政期そのままの狭く複雑に入り組んだ小路や趣の異なるいくつもの坂道が生活空間の一
-
な 那谷寺
- [ 寺院 | 庭園 | 紅葉 | パワースポット ]

-
小松市那谷町ユ122
 [ 紅葉時期 11月上旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 11月上旬~11月下旬 ]奇岩遊仙境と称される自然境で、重要文化財の堂宇が点在する。
北陸屈指の真言宗の古刹。717年(養老元)、泰澄大師が岩窟に千手観音を安置したのが始まりという。その後寛和
-
や 薬王院温泉寺
- [ 寺院 | 浸かる ]
-
加賀市山代温泉18-40甲
山代温泉を発見した行基が開いた古刹。明覚上人の墓とされる五輪塔は国の重要文化財に指定されている。
-
よ 永光寺
- [ 寺院 ]
-
羽咋市酒井町イ11
瑩山禅師が1312年に開創され、鎌倉末時代の仏像を10体所蔵していることで有名。
-
ら 来教寺
- [ 寺院 ]
-
金沢市東山2-14-22
金沢の卯辰山山麓寺院群にある天台真盛宗の寺院。本堂内陣の様式は珍しい神仏混淆で、左側内陣に金比羅宮、右側内
-
り 龍渕寺
- [ 寺院 ]
-
金沢市野町3-19-60
金沢の寺町寺院群にある曹洞宗の寺院。天正10(1582)年に尾張の国で創建され、正保2(1645)年に現在
-
す 須曽蝦夷穴古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
七尾市能登島須曽町タ部21-5
7世紀中頃に築かれた有力者の墳墓を修復整備し一般公開している。隣接の蝦夷穴歴史センターでは、古墳の出土品を
-
り 立像寺
- [ 寺院 ]
-
金沢市寺町4-1-2
金沢市最古のお寺と伝わる。境内には、キリシタン灯ろうや、横綱阿武松録之助の墓がある。立像寺には飴買い幽霊伝
-
ぶ 豊財院
- [ 寺院 ]
-
羽咋市白瀬町ル-8
14世紀初頭、總持寺を開山した瑩山紹瑾禅師が能登で一番最初に開いた寺。宝物館には木造の馬頭観音像、聖観音像
-
お 大野日吉神社
- [ 神社 ]
-
金沢市大野町5-81
天平5(733)年の創始と伝わり、義経伝説も残る由緒ある古社。7月の第4土・日曜日に山王祭に行なわれる例祭
-
せ 千体地蔵
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 遊歩道 ]
-
輪島市町野町曽々木
岩倉山自然遊歩道の途中にあり、日本海の荒波と風に浸食された岩肌が、まるでお地蔵様がずらりと並んだように見え
- [ 神社 ]
-
加賀市山代温泉18-7
和銅年間(708~14)創建と伝わる。御祭神は、天羽鎚雄神、菊理媛神、山代日子命(山代温泉の守り神)。平成
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 公園 ]
-
能美市和田町・末寺町地内
3~7世紀にわたって各種の古墳が相次いで造られた石川県の最大の古墳群。出土した副葬品などは史跡公園入口の歴
-
じ 実性院
- [ 寺院 ]

-
加賀市大聖寺下屋敷町29
大聖寺藩の藩主前田氏の菩提寺。藩主をまつった五輪塔や藩士たちの墓が苔むしている。萩の名所としても有名で萩の
- [ 寺院 | 花 ]
-
輪島市町野町徳成谷内ヲ12
能登石楠花寺の名で知られているお寺。高野山から移植されたシャクナゲが、献木2000本とともに、境内をピンク
-
お 大堰宮
- [ 神社 | 桜 ]
-
加賀市山代温泉
貞観18年(876)、正六位から従五位下に進階し、御祭神は大堰神。その後廃絶したが、天保14年(1843)
-
こ 小松天満宮
- [ 神社 | 梅 ]
-
小松市天神町1
寛永十六年(1639)に加賀藩三代前田利常公の発願により、菅原道真公を祀る社として、明暦三年(1657)に