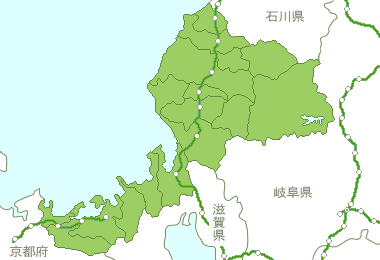神社・寺院・歴史 一覧

-
だ 大善寺
- [ 寺院 ]
-
坂井市坂井町下兵庫93-11
寛弘8(1011)年に恵心僧都(えしんそうづ)が開いたとされる古刹。寺宝の「金銅孔雀文磬」(こんどうくじゃ
-
な 中山寺
- [ 寺院 ]

-
大飯郡高浜町中山27-2
奈良時代に聖武天皇の勅願により泰澄大師が創建されたと伝わる。本堂は重要文化財に指定されている。本尊の馬頭観
-
お 大野市民俗資料館
- [ 歴史的建造物 | 博物館・資料館 ]
-
大野市城町2-13
明治時代に建てられた大野治安裁判所を移築、利用している民俗資料館。建物は入母屋造りの屋根を持つ和風構造に西
-
い 出雲大社福井分院
- [ 神社 | パワースポット ]
-
福井市渕2丁目2001番地
島根県出雲大社の北陸唯一の分院
昭和29年10月12日に出雲大社から大国主大神の分霊を勧請し設立されました。出雲大社同様、大国主大神が御祭
-
さ 西光寺
- [ 寺院 ]
-
福井市左内町8-21
柴田勝家とその妻・お市の方が祀られ柴田勝家の菩提所として著名。資料館には勝家の自筆の書や刀剣、金の御幣の馬
-
み 妙楽寺
- [ 寺院 ]
-
小浜市野代28-13
本堂は鎌倉時代初期に建立されたもので若狭最古の建造物。本堂には、頭上に24面の顔と1000本の手を持つ珍し
-
わ 若狭町歴史文化館
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
三方上中郡若狭町市場20-17
若狭町内で出土した金製耳飾、金銅製の馬具、鏡、鉄製の武器、武具などを展示。
-
え 恵比須神社
- [ 神社 ]
-
三方上中郡若狭町末野36-11
恵比須大神を祭神とし、商売・漁業・子供の守り神として、全国から信仰を集めている。御利益がさずかる「えびす飴
-
い 板取宿
- [ 歴史的建造物 ]
-
南条郡南越前町板取
越前南端の重要な関門の地として板取宿が置かれた
天正6(1578)年、柴田勝家が栃ノ木峠越えの北国街道を大改修してから人馬の往来が増えた。板取宿は北国街道
-
う 宇波西神社
- [ 神社 ]
-
三方上中郡若狭町気山129-3
飛鳥時代に今の宮崎県日向から若狭町気山に移ってきたと言われ、「王の舞」が奉納される神社
創建が701年とかなり古く、806年に現在地に移った。海漁と安産の神様が鎮座し、毎年4月8日に行なわれる「
-
け 毛谷黒龍神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
福井市毛矢3丁目8−1
足羽山の東麓にある黒龍大明神に所縁がある神社。地元で「くろたつさん」と呼ばれ親しまれています。九頭龍川の守
-
わ 若狭鯖街道
- [ 歴史街道 ]
-
三方上中郡若狭町熊川
北前船から陸揚げされたサバなどの海産物を運んだ道。
主に魚介類を京都へ運搬するための物流ルートとなっており、その中でも特に鯖が多かったためこの名で呼ばれるよう
- [ 歴史的建造物 ]
-
南条郡南越前町河野2-15
北前船で栄えた右近家。重厚な本屋敷などをめぐると、隆盛を極めた当時の様子をうかがい知ることができる。
-
わ 和田八幡宮
- [ 神社 | パワースポット ]
-
福井市和田3丁目1113
天徳3年(平安時代中期)国主、源義仲より創建。神功皇后、応神天皇、伸哀天皇を祭り、親子神として八幡大神と称
-
え 越前大野城
- [ 歴史 | 城 ]

-
大野市城町3-109
明治までは大野藩の藩庁が置かれた。
織田信長の重臣・金森長近が天正4(1576)年に築城した。城は1775年(安永4年)に焼失し、1795年(
-
お 岡津製塩遺跡
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
小浜市岡津
小浜湾・青戸の入り江に面したところにある、古墳時代後期から奈良時代にかけての製塩遺跡。若狭は塩づくりは盛ん
-
き 虚子愛子柏翠句碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
坂井市三国町安島
若くして病死した三国出身の森田愛子を偲んで、師匠の高浜虚子と兄弟子の伊藤柏翠が詠った句と、愛子自らが病床に
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 峠 ]
-
南条郡南越前町二ツ屋
お地蔵さまは弘法大師の化身であるともいわれる。権六が旅人を殺し金を奪い、一部始終を見ていた地蔵さまに「人に
- [ 歴史 ]
-
福井市城東1-18-21
福井県にゆかりの人物を通して、歴史や文化など楽しく学べる施設。土曜・日曜には、体験型のワークショップやイベ
-
じ 常高寺
- [ 寺院 ]
-
小浜市小浜浅間1
創建は寛永7(1630)年、浅井三姉妹の次女「初」、京極高次の正室(常高院)の祈願により建立。織田信長の妹
-
ま 松木神社
- [ 神社 ]
-
三方上中郡若狭町熊川
昭和8年、岡本一雄氏を始めとする篤志家たちの尽力と、多くの崇拝者たちの協力によって、創建された神社。江戸時
-
か 金ヶ崎城跡
- [ 城 | 歴史 ]
-
敦賀市金ヶ崎町
延元元年(1336年)恒良、尊良両親王を守護した新田義貞が足利軍と戦い、戦国時代は織田信長の朝倉攻めの舞台
-
だ 大成寺
- [ 寺院 ]
-
大飯郡高浜町日置31-3
観応2年(1351)足利尊氏の二男・基氏が開祖、華陽禅師が開山したと伝えられる。応永元年(1394)小浜領
-
え 栄久寺
- [ 寺院 ]

-
越前市京町3-4-34
1525年に創建された京都本山妙覚寺直末。秘伝「九識霊断」によって真相を解明し、悩み・迷いを晴らして運命を
-
じ 自性院
- [ 寺院 ]
-
福井市西木田2-10-21
奈良朝時代には紫雲山仏光寺と称して、越前東郷赤坂岡山に開創され、慶長10(1605)年に現在の場所に移され
-
い 銀杏観音
- [ 観音 ]
-
三方上中郡若狭町安賀里33-1
樹齢450年のイチョウの大木のお腹に彫られた十一面観音立像
諦応寺の山門近くにそびえ立つ大きなイチョウに彫られた十一面観音像。江戸末期に諦応寺第三十世住職が、幕末の混
-
き 旧瓜生家住宅
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]

-
鯖江市水落町4-7 神明社境内
元禄年間に建てられたとされる住宅で、現存する民家の中では福井最古のもの。開館時には、いろりに火がくべられ、
-
と 灯明寺畷
- [ 寺院 ]
-
福井市新田塚町604 新田塚公園内
暦応元年(1338)新田義貞が戦死した古戦場。田から明暦2(1956)年義貞のものと思われる兜を発見。当時
-
き 吉峰寺
- [ 寺院 ]
-
吉田郡永平寺町吉峰35-13-2
創建は寛元元年(1243)、波多野義重が道元禅師を招いて開山したのが始まりと伝えられる。寺宝として、道元禅
-
ふ 福井城址
- [ 城 | 桜 ]
-
福井市大手3
徳川家康の次男初代藩主結城秀康が1606年に築城。越前松平家の繁栄の舞台。石垣と堀の一部だけが残されている