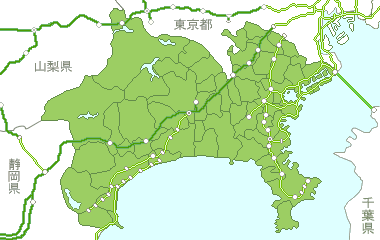神社・寺院・歴史 一覧

-
は 白秋詩碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
三浦市三崎町城ヶ島374-1
白秋記念館の近く、城ヶ島大橋のたもとに建つ詩碑。大正2年、三崎に住んだ白秋が28歳のときに作った「城ヶ島の
-
は 畑宿一里塚
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-
足柄下郡箱根町畑宿172
箱根旧街道のスタート地点。
箱根旧街道石畳の両側に残る畑宿の一里塚は、江戸日本橋から数えて23里目に当たり、箱根町の中では、湯本茶屋、
-
ほ 本覺寺
- [ 寺院 ]

-
横浜市神奈川区高島台1-2
鎌倉時代に創建された古刹。
1226年に宗祖栄西により創建されたと伝わる。境内には神奈川区指定の6本の名木・古木がある。幕末の横浜開港
- [ 神社 | デート ]

-
藤沢市江の島
江島神社の境内社。
毎年7月中旬に行われる江の島天王祭は夫婦神である八坂神社と腰越の小動神社が年一回海上渡御にて会いに行く勇壮
- [ 寺院 | 桜 ]
-
海老名市国分北2-13-40
臨済宗建長寺派の禅寺として、1340(興国元)年開山円光大照禅師によって創建。1928(昭和3)年現在の地
-
ろ 六道地蔵
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]

-
足柄下郡箱根町元箱根103
国の史跡および重要文化財に指定。
地蔵菩薩像「六道地蔵」は高さが約3.5mもあり、鎌倉時代の磨崖仏としては関東一の大きさを誇っている。木造の
-
あ 甘縄神明宮
- [ 神社 ]
-
鎌倉市長谷1-12-1
鎌倉最古の神社。
和銅3年己酉年(西暦710年)染屋太郎大夫時忠の創建といわれる。境内からは、由比ヶ浜が一望でき、石段下には
-
い 一遍上人成就水道
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]

-
藤沢市江の島
飲料水に窮する島民を助ける為に一遍上人が掘り当てた井戸と伝えられ、今も水をたたえています。(現在は周辺が民
-
う 姥子石仏群
- [ 歴史 | 珍スポット | 碑・像・塚・石仏群 ]
-
足柄下郡箱根町仙石原
2つの向かい合った祠と6体のお地蔵様が安置。
大涌谷から姥子周辺にはかつて多数の石仏が点在していたものを、秀明館という日帰りの湯場の裏に集められた。
-
お 小田原城天守閣
- [ 城 | 展望台 ]

-
小田原市城内6-1
標高約60mの最上階からは相模湾が一望できる。
昭和35(1960)年に復興した天守閣の内部は古文書、武具、刀剣などが展示されている。
-
き 旧華頂宮邸
- [ 歴史的建造物 | 庭園 ]

-
鎌倉市浄明寺2-6-37
昭和4(1929)年に華頂博信侯爵邸として建てられた貴重な洋館。
通常はフランス式庭園のみ見学でき、内部は春・秋に公開。公開日はホームページで発表される。日本の歴史公園10
- [ 神社 ]

-
足柄下郡真鶴町真鶴1117
町の鎮守として親しまれています。
真鶴半島のほぼ中央に位置し真鶴港を見渡す高台にあります。平成8年に国の重要無形民俗文化財の指定を受けていま
-
こ 小動神社
- [ 神社 ]
-
鎌倉市腰越2-9-12
小動岬にある神社。
文治年間(1185年-1189年)の源平合戦の際、佐々木盛綱が父祖の領国であった近江国の八王子宮を勧請した
-
こ 光触寺
- [ 寺院 ]
-
鎌倉市十二所793
一遍上人ゆかりの寺
四季の花と苔むした石仏群が迎える寺院。供物の塩をなめたという塩嘗地蔵や、法師に代わって頬に焼印を受けたとい
-
ご 極楽寺(鎌倉市)
- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 ]

-
鎌倉市極楽寺3-6-7
鎌倉唯一の真言律宗の寺。
鎌倉七口の1つである極楽寺坂切通しの近くにある、鎌倉では珍しい真言律宗の寺院である。僧忍性が実質的な開祖で
-
じ 地蔵王廟
- [ 寺院 | 歴史的建造物 ]
-
横浜市中区大芝台7
1874年(明治7)に設けられた中国人の寺。
中国人墓地はかつて山手の外国人墓地にあったが、明治6(1873)年に現在の場所に移された。廟は中庭を中心に
-
じ 定泉寺
- [ 寺院 ]
-
横浜市栄区田谷町1501
境内にある人工洞窟、瑜伽洞が有名寺。
建立は天文元(1532)年で、鎌倉時代に作られた瑜伽洞よりも寺の歴史の方が新しい。真言密教僧の修行の場とし
-
だ 大巧寺
- [ 寺院 ]

-
鎌倉市小町1-9-28
安産の神として「おんめ様」の通称で親しまれている。
鎌倉駅から若宮大路に出てすぐのところにある小さな寺。安産の神様とされる産女霊神、通称おんめさまで知られる。
- [ 寺院 | 紅葉 ]

-
足柄下郡箱根町仙石原82
 [ 紅葉時期 10月下旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 10月下旬~11月下旬 ]「東国花の寺百ヶ寺」として知られる名刹。
自然に囲まれ、特に紅葉の名所として知られる、曹洞宗の寺院。境内には一体一体の表情豊かで人間味のある五百羅漢
-
て 天長門
- [ 歴史的建造物 | その他 ]
-
横浜市中区山下町
商売の神様「横浜中華街關帝廟」がある通りを象徴する門。関帝廟通りの東端、南門シルクロードに面して建つ。天の
-
で 伝上杉憲方の墓
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
鎌倉市極楽寺1-2
室町幕府初期の武将で関東管領であった上杉憲方の墓と伝えられる。
極楽寺切通沿いに並ぶ石塔のうち、七層塔が憲方の墓で隣の五層塔が妻のものとされている。極楽寺の支院西方寺跡の
-
と 等覚寺
- [ 寺院 ]

-
鎌倉市梶原1-9-2
出世子育て地蔵で有名なお寺。
室町時代創建の古義真言宗の寺。堂内安置の地蔵菩薩が有名で、参拝すると、子のない人は子を授かり、子のある人は
-
は 箱根神社宝物殿
- [ 神社 | 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
足柄下郡箱根町元箱根80-1
箱根神社に伝わる宝物類を展示。
万巻上人坐像や鉄湯釜、浴堂釜、箱根権現縁起絵巻などを常設展示。
-
み 妙本寺
- [ 寺院 ]

-
鎌倉市大町1-15-1
山号は長興山(ちょうこうざん)で文応元年(1260年)の創建。
日蓮聖人を開山に仰ぐ、日蓮宗最古の寺院。北条氏に滅ぼされた比企一族の供養寺として、日蓮を開山に創建された日
-
も モース記念碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-
藤沢市江の島
陶器、民具、着色ガラス写真の収集などを通じ、日本文化を海外に紹介した博士の記念碑。
江の島に入ってすぐ左にり、東京の大森貝塚の発見者として知られるエドワード・S・モース博士を記念した記念碑。
-
や 山手資料館
- [ 歴史的建造物 | 博物館・資料館 ]
-
横浜市中区山手町247
横浜内では最古の木造建築物に歴史的資料を集めた。
明治42(1909)年に建造された木造西洋館で、オルガンや西洋瓦など当時の品々、山手の歴史に関する資料、外
-
り 龍口寺
- [ 寺院 ]

-
藤沢市片瀬3-13-37
厄除けの霊場として有名。
日蓮宗霊跡本山のひとつ。龍ノ口刑場跡に建てられた寺で、神奈川県唯一の木造五重塔のほか、大阪雷雲寺の発願で竣
-
れ 霊光寺
- [ 寺院 ]
-
鎌倉市七里ガ浜1-14-5
雨乞い伝説が残る霊光寺。
日蓮の雨乞いの霊験をまつるために建てられた霊光寺。1271年(文永8)の干ばつの際、日蓮上人が極楽寺の忍性
-
あ 吾妻神社
- [ 神社 ]
-
中郡二宮町山西1117
吾妻山公園にある神社。
日本武尊の妻・弟橘姫命が、夫のために嵐おさめるため海へ入水した伝説にまつわる神社。良縁成就の御利益がある。
- [ 歴史的建造物 ]
-
足柄上郡開成町金井島1336
開成町北部、金井島に所在し江戸時代、旧金井島の名主を代々つとめた瀬戸家が、家屋を構えてきた約1800坪の大