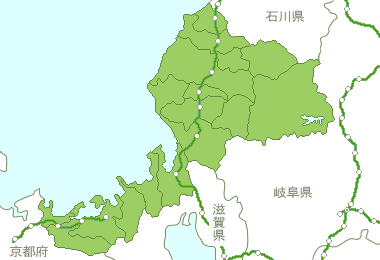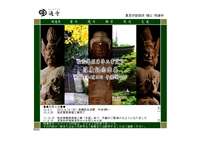神社・寺院・歴史 一覧

- [ 神社 ]
-
越前市大滝町23-10
推古天皇の御代(592ー638)に大伴連大瀧の勧請によって創祀。大瀧神社では國常立尊・伊弉諾尊、岡太神社で
-
に 二本松山古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
吉田郡永平寺町松岡吉野堺~諏訪間
5世紀後半頃のものと思われる前方後円墳。全長約90m。2基の石棺が発掘され、多くの財宝が見つかった。
-
ふ 復原町並
- [ 歴史街道 ]
-
福井市城戸ノ内町
城下町の町並みをほぼ完全な姿で再現。
町屋、商家、武家屋敷など200mにわたり立体復原された町並み。武家屋敷が道路に面し、周囲に土塁をめぐらせて
-
み 明通寺
- [ 寺院 ]

-
小浜市門前5-21
平安京の大同元(806)年に征夷大将軍・坂上田村麻呂が創建したと伝えられる古刹。本尊は薬師如来。国宝に指定
-
わ 若狭姫神社
- [ 神社 ]
-
小浜市遠敷65-41
和銅7年(714年)白石の里に上社・若狭彦神社が創建され、翌霊亀元年(715年)に現在地に遷座し、下社・若
-
あ 赤レンガ倉庫
- [ 歴史的建造物 ]
-
敦賀市金ヶ崎町4
明治から昭和初期にかけて港を中心に国際的な都市として発展した敦賀。その当時の面影を今もとどめる建造物
国際貿易の拠点として繁栄した敦賀港。その面影が残る景色の中にあって、ひときわ目立つのが「赤レンガ倉庫」。海
-
た 武田耕雲斎等の墓
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
敦賀市松島町2
武田耕雲斎等墓は昭和9年に国指定史跡に指定されている
挙兵するも、捕らえられ斬首された水戸天狗党を率いていた武田耕雲斎の墓。来迎寺境内で武田耕雲斎をはじめ藤田小
-
お 越知山大谷寺
- [ 寺院 ]
-
丹生郡越前町大谷寺42-4-1
三所大権現の別当寺として金毘羅山のふもとに建立されたとされる。本尊は十一面観音、阿弥陀如来および聖観音。山
-
わ 若狭彦神社
- [ 神社 ]
-
小浜市龍前
霊亀元(715)年に創建された若狭一の宮。上社(若狭彦神社)と下社(若狭姫神社)に分かれ、2社合わせて若狭
-
き 旧逸見勘兵衛家
- [ 歴史的建造物 ]
-
三方上中郡若狭町熊川30-3-1
熊川を代表する町家の一つで、町指定の文化財。町並み保存と住民の生活を両立させるため、外観は典型的な町家の造
-
お 大塩八幡宮
- [ 神社 ]
-
越前市国兼町22-2
寛平3年(891年)越前に流された中納言紀友仲が都に戻されたのを感謝して建立、石清水八幡宮の神霊を勧請。武
-
す 須波阿須疑神社
- [ 神社 ]
-
今立郡池田町稲荷13-1
延徳三年(1491)に再建された本殿は500年以上の歴史を持ち、国の重要文化財。6月には池田大祭が行われ、
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
坂井市三国町東尋坊
「わが心のふるさと」と言い切るほど三国を愛した漂泊の詩人、三好達治の詩が刻まれた石碑。その他にも荒磯遊歩道
-
あ 朝倉館跡唐門
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
福井市城戸ノ内町10-48
5代目義景が住んでいた館跡で、三方は土塁と壕で囲まれている。三方の土塁にはそれぞれ隅櫓や門があった。西方に
-
み 妙泰寺
- [ 寺院 ]
-
南条郡南越前町西大道10-8
永仁2年、日蓮大聖人の法孫日像菩薩によって開山。越前の日蓮宗の寺の中で最も古い。日蓮と日像筆の曼荼羅各一幅
-
い 一乗谷の石仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
福井市安波賀町
朝倉時代には40を超す寺院が造られ、西山光照寺・盛源寺・法蔵寺・極楽寺・最腸寺の参道や境内にはその名残の石
-
み 三國神社
- [ 神社 ]
-
坂井市三国町山王6-2-80
地元では「おさんのさん(お山王さん)」と呼ばれている。北陸三大祭の一つにもなっている「三国祭」が行われる由
-
ば 萬慶寺
- [ 寺院 ]
-
鯖江市深江町6-14
1720年(享保5年)陽光により万松庵として創建されたと伝わり、後1725年に現在地に移った。市指定文化財
-
ほ 宝慶寺
- [ 寺院 ]
-
大野市宝慶寺1-2
中国南宋時代の高僧・寂円禅師が弘安元(1261)年に開いた、日本曹洞第二道場。道元禅師図像など多数の県指定
- [ 道・通り・街 | 歴史 ]
-
大野市錦町
天正年間に城下町づくりの一環として、京の都に模して碁盤の目のように整然と区画された町づくりがなされた。真宗
-
ほ 堀口家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
今立郡池田町稲荷17
江戸時代初期に建てられた民家を1972(昭和47)年に解体、復元したもので、国の重要文化財。入母屋茅葺土座
-
し 称名寺(福井市)
- [ 寺院 ]
-
福井市折立町17-8
佐々木三郎盛綱が開いた浄土真宗高田派の寺院。越前一向一揆に関する資料を所蔵。