円覚寺 えんがくじ

弘安5年(1282)鎌倉時代後期、北条時宗が宋(中国)から招いた無学祖元(むがくそげん)を開山として創建された臨済宗の寺。 鎌倉五山第二位。
JR北鎌倉駅の駅前に円覚寺の総門があり、境内には現在も禅僧が修行をしている道場がある。
毎週土曜・日曜日には、一般の人も参加できる土日坐禅会が実施されている。かつて夏目漱石や島崎藤村も参禅したことでも知られている。
| 住所 | 鎌倉市山ノ内409 |
| 営業時間 | 拝観時間 8時~17時(4月~10月)8時~16時(11月~3月) |
| 料金 | 拝観料 300円 |
| 駐車場 | 駐車場 25台 |
| アクセス 公共交通 | 最寄駅 > 北鎌倉駅(JR)~707m |
| アクセス 車 | 最寄IC > 朝比奈IC(横浜横須賀道路)~7.108km 釜利谷JCT(横浜横須賀道路) |
| ご朱印 御朱印帳 |
御朱印を頂く場所 御朱印所 頂ける御朱印の種類 宝冠釈迦如来・南無延命地蔵・南無十一面観世音・北条時宗廟(佛日庵にあるご朱印受付所・期間は通年)・功徳林 (大方丈前の特設会場で期間は11月に開催される円覚寺宝物風入れ期間中:例年3日間)・舎利膽 (禮舎利殿入り口の特設会場 舎利殿の特別公開期間中のみ:例年GW中と11月中の3日間) 書いてくれる方の人数 2~3名 初穂料・寸志:300円 混雑しているときは御朱印帳を預けます。番号札を受け取り、後に番号札で受取ります。 |
| 御朱印 | |
| 公開サイト | www.engakuji.or.jp |
閲覧履歴
履歴の更新
レポート
春の円覚寺。山門。
境内案内図。開基廟。
黄梅院の境内「聖観音堂」。境内の桜。桜と唐門。
仏日庵内に植えられた多羅葉。御朱印「仏日庵」「円覚寺」
建長寺とともに鎌倉禅宗を代表する存在で鎌倉最大級の寺院です。山門、仏殿、方丈、洪鐘(国宝)等々見所も多い寺院でした。
円覚寺入口。総門へ続く石段付近の紅葉が綺麗!
総門から振り返った風景。拝観券 料金は大人一人300円。円覚寺の案内図。
入って直ぐ左手にある桂昌庵。正面には立派な山門。山門(三門)の説明板。この三門は、明治時代の文豪・夏目漱石の小説「門」にも登場しています。
山門をくぐると仏殿が見えてきました。この中に本尊さまが安座されています。仏殿の説明板。大正12年(1923)の関東大震災で倒壊、のち昭和39年(1964)に再建されたそうです。
仏殿内の様子。天井には白龍の図(前田青邨監修、守屋多々志揮毫)が描かれています。宝冠釈迦如来坐像。丈六の釈迦如来像は、廬舎那仏ともいわれ、頭の部分だけが鎌倉時代に作られたものとのことです。脇侍は梵天と帝釈天といわれています。
境内(山門の右手方向奥)には国宝に指定された「洪鐘」(おおがね)があります。
この石鳥居をくぐり石段を登って行きます。「洪鐘」は鎌倉で最大の梵鐘(総高259.4センチメートル、口径142センチメートル)で建長寺の梵鐘とともに国宝に指定されています。
洪鐘は円覚寺の開基である北条時宗の子である貞時が正安3年(1301)、国家安泰を祈願して寄進したものだそうです。洪鐘の隣には弁財天を祀るお堂がありました。江ノ島弁財天の加護によって洪鐘の鋳造が完成したと伝えられているそうです。
仏殿付近の紅葉風景。参道風景。
仏殿の右手の先方向に方丈の正門(唐門)があります。唐門は天保十年 (1839) の建立。方丈に安置されている石仏「百観音」。
方丈(本来は住職が居住する建物、現在は各種法要の他、坐禅会などに利用されているそうです)
ご本尊さま・釈迦牟尼坐像。廊下から外の庭を眺めた風景。外から庭を眺めた風景。
妙香池と紅葉。正続院入口。正続院入口から正続院 唐門を望む。通常は非公開されているの「仏舎利殿」屋根が見えます。仏舎利殿には、お釈迦様のお歯をお祀り「佛牙舎利」してあるそうです。
北条時宗の廟所「仏日庵」。この白鹿洞から白鹿が群れをなして出てきて、無学祖元の法話を聞いたと伝わる。白鹿洞の説明。
境内の一番奥にある黄梅院(おうばいいん)入口。黄梅院は観応2年(1351年)に示寂した第15世夢窓疎石の塔所で、文和3年(1354年)に弟子の方外宏遠によって創設。
黄梅院の掲示板「じぶんにはきびしく ひとにはやさしく この二つを丹田に打ち込むのだ」揮毫されたものを月初めに貼り替えているようです。
黄梅院の境内にある聖観音堂。天気に恵まれ紅葉も綺麗・・・拝観日和でした!





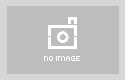





 評価 4点 2019/03/16
評価 4点 2019/03/16

 評価 3点 2010/07/01
評価 3点 2010/07/01







