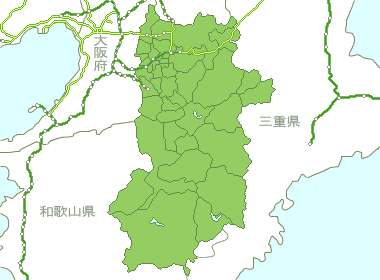観光スポット 一覧

-
あ アトンおもちゃ館
- [ 博物館・資料館 ]

-
高市郡明日香村小山336
昭和時代のおもちゃを中心に展示。
館内には昭和の時代を中心としたおもちゃや文房具、生活雑貨など3万点以上を常設展示。年に数回、期間限定で開か
-
あ 飛鳥坐神社
- [ 神社 ]
-
高市郡明日香村飛鳥707-1
鳥形山の森に鎮座する古社。
境内には、江戸時代に式内小社飛鳥山口坐神社(あすかやまぐちにますじんじゃ)が遷座している。大山津見命、久久
-
あ 安楽寺廃寺跡
- [ 寺院 | 歴史 ]
-
宇陀市菟田野駒帰
昭和45-46年遺構が発見され、現在は史跡公園。
多武峰の談山神社に伝わる「宇陀旧事・写本」の記述からその存在が知られ発掘された。創建時の瓦窯跡が発見され、
-
い 入鹿神社
- [ 神社 ]
-
橿原市小綱町
素戔鳴尊と蘇我入鹿を祭神とし、合祀している。境内には神宮寺として明治時代まで仏起山普賢寺があり大日如来が祀
-
い 石床神社 旧社地
- [ 神社 ]
-
生駒郡平群町越木塚石床783
越木塚の集落内にある石が御神体。
越木塚集落の南東部、伊文字川流域を見おろす位置にあり、本殿や拝殿は当初からなく、鳥居と社務所があっただけで
-
う 宇太水分神社
- [ 神社 ]
-
宇陀市菟田野古市場245
水分三座を祀る延喜式にもある大社。
国宝の本殿3棟は鎌倉時代の建物。3棟とも同形同大の一間社春日造りで、隅木入春日造で建立年代の明らかなものと
-
お おふさ観音
- [ 観音 | 花 ]
-
橿原市小房町6-22
バラが境内に所狭しとあふれる寺院として知られている。
18世紀後半の天明年間に妙円尼が開基したと伝えられる。イングリッシュローズを中心に約1800種およそ200
-
か 葛城一言主神社
- [ 神社 ]
-
御所市森脇432
願い事を一言のみ叶えてくれると信仰を集めて「いちごん(じ)さん」と呼ばれ親しまれている。神宮寺として一言寺
-
か 柿博物館
- [ 博物館・資料館 ]

-
五條市西吉野町湯塩1345
柿をテーマに公的な博物館。
柿ドームとも呼ばれる外観は目を引く。館内ではビデオ上映のほか、柿渋染め、柿の実の模型、柿加工品等の展示があ
-
か 葛城高原のツツジ
- [ 自然 | 花 | 遊歩道 ]
-
御所市櫛羅
葛城高原の自然ツツジ園。
城高原は金剛生駒紀泉国定公園にある、標高960mのなだらかな高原。5月には一目百万本といわれるツツジで斜面
-
き 吉祥草寺
- [ 寺院 ]
-
御所市茅原279
4代舒明天皇の頃に山伏修験道の開祖ともいわれる役小角創建の寺。不動明王を所蔵し、小角自らの作といわれる32
-
き 吉田寺
- [ 寺院 ]
-
生駒郡斑鳩町小吉田1-1-23
天智天皇の勅願により創建されたとされ、近くには妹・間人皇女を葬る古墳がある。平安時代の永延元年(987年)
-
く 百済寺
- [ 寺院 ]
-
北葛城郡広陵町百済1411-2
聖徳太子が創建した熊凝精舎を継いで、舒明天皇11年(639年)に百済大寺を創建したと伝えられる。本尊は十一
-
こ 荒神社
- [ 神社 | 日の出 ]
-
吉野郡野迫川村池津川347
荒神岳の頂上(1260m)にある高野山の奥社。
弘法大師も修行した古い社であり、火の神として知られている。三宝大荒神のひとつとして高野山信奉者のほか、全国
- [ 神社 ]
-
奈良市薬師堂町24
元興寺五重塔跡の南西に鎮座する。
桓武天皇の御代、延暦十九年(800)に宇智郡霊安寺から勧請したもの。本殿には井上皇后(井上内親王)・橘逸勢
-
さ 讃岐神社
- [ 神社 ]
-
北葛城郡広陵町三吉
一帯は讃岐国の斎部氏が移り住んだ地で、讃岐の故郷の神を勧請し創建したものとみられる神社。大国魂命・若宇加能
-
さ 狭井神社
- [ 神社 ]

-
桜井市三輪
第十一代垂仁天皇の御世(約二千年前)に創祀。荒魂をお祀りしている。正式名称は、狭井坐大神荒魂神社(さいにま
-
桜井市芝58-2
文化遺産の保護および調査・研究を行う施設。
纒向遺跡、茶臼山古墳、上之宮遺跡などの発掘資料を中心に展示。3~4世紀の大集落の跡、纏向遺跡のコーナーには
-
し 志賀直哉旧居
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]

-
奈良市高畑大道町1237-2
志賀直哉自身が設計し、1929(昭和4)年から9年間住んだ家。
書斎やサンルーム、娯楽室などがあり、武者小路実篤や小林秀雄ら文化人が集い「高畑サロン」と呼ばれていた。
-
じ 浄安寺
- [ 寺院 ]
-
北葛城郡上牧町上牧335
開山は万治元年(1658)遷化の楽誉浄安大徳で、本堂は宝永5年(1708)に建立され、天保12年(1841
-
す 菅原天満宮
- [ 神社 ]
-
奈良市菅原町518
菅家の祖廟であり、菅原家発祥の地。
祭神は天穂日命・野見宿禰・菅原道真。菅原道真が牛に乗って大宰府に流されたという故事にちなみ、境内には牛の像
-
す 相撲神社
- [ 神社 ]
-
桜井市穴師
相撲の発祥地として知られる。
相撲の元祖、野見宿禰が當麻蹴速と力比べをしたという伝承から、相撲発祥の地といわれ、二人が勝負したと伝わる土
-
た 高天寺橋本院
- [ 寺院 ]

-
御所市高天350
元正天皇(715~724年)に行基が開いたと伝わる。
鑑真和上(753年来日)を住職に任命されるなど、孝謙天皇(749~758年)も深く帰依され高天千軒と呼ばれ
-
た 高天彦神社
- [ 神社 ]
-
御所市北窪
金剛山の東麓にあり、葛城氏の祖神である高皇産霊神に、市杵島姫命、菅原道真を加えた三神を祀る。社殿後方の白雲
-
だ 大日寺(吉野郡)
- [ 寺院 ]
-
吉野郡吉野町吉野山2357
大海人皇子(後の天武天皇)ゆかりの法城。
吉野山で最古の寺院と云われ、役行者の高弟日雄角乗を初代とする日雄寺が在った跡と伝えられている。1333年(
- [ 寺院 ]
-
北葛城郡広陵町的場80
聖徳太子によって開創されたと伝えられる。
本堂には本尊薬師如来座像のほか、県指定文化財として両界板絵曼荼羅(1422~24年)、長谷寺式十一面観音(
-
だ 大願寺(宇陀市)
- [ 寺院 ]
-
宇陀市拾生736
聖徳太子が蘇我馬子に命じて建立したとも伝わる古寺。
創建は推古時代と伝えられる古刹で真言宗御室派、本尊は十一面観音菩薩像(焼けずの観音)。別名「七福寺」。十薬
- [ 寺院 | 花 ]

-
高市郡高取町壺阪3
創建は大宝3年に元興寺の弁基上人により開かれたとされる。
京都の清水寺の北法華寺に対し南法華寺といい、長谷寺とともに古くから観音霊場として栄えた。本尊の十一面観音は
-
と 洞泉寺
- [ 寺院 ]
-
大和郡山市洞泉寺町15
1585(天正13)年に、豊臣秀吉の弟で、郡山城主の秀長が創建。
本堂には鎌倉時代に快慶作と伝わる阿弥陀如来立像(重要文化財)が安置されている。寺の周辺は大和格子の古い街並
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
吉野郡十津川村小原225-1
十津川の水害の歴史や村人の暮らしぶりを、パネルを使って紹介。
皇室と深くかかわった村の歴史も知ることができる。近くに伝習館「十津川郷」がある。