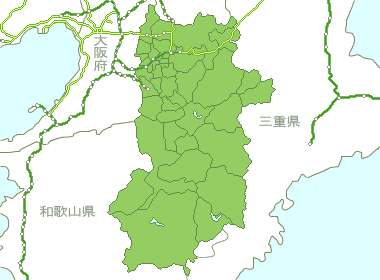神社・寺院・歴史 一覧
-
神社・寺院・歴史

-
す 菅原天満宮
- [ 神社 ]
-
奈良市菅原町518
菅家の祖廟であり、菅原家発祥の地。
祭神は天穂日命・野見宿禰・菅原道真。菅原道真が牛に乗って大宰府に流されたという故事にちなみ、境内には牛の像
-
す 巣山古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
北葛城郡広陵町三吉
馬見丘陵の中央部に位置する大型の前方後円墳。
古墳時代前期から中期への過渡期(4世紀末から5世紀初め)の前方後円墳。出土遺物は勾玉、管玉玉籠形土器など。
-
す 相撲神社
- [ 神社 ]
-
桜井市穴師
相撲の発祥地として知られる。
相撲の元祖、野見宿禰が當麻蹴速と力比べをしたという伝承から、相撲発祥の地といわれ、二人が勝負したと伝わる土
-
た 高天寺橋本院
- [ 寺院 ]

-
御所市高天350
元正天皇(715~724年)に行基が開いたと伝わる。
鑑真和上(753年来日)を住職に任命されるなど、孝謙天皇(749~758年)も深く帰依され高天千軒と呼ばれ
-
た 高天彦神社
- [ 神社 ]
-
御所市北窪
金剛山の東麓にあり、葛城氏の祖神である高皇産霊神に、市杵島姫命、菅原道真を加えた三神を祀る。社殿後方の白雲
-
だ 大日寺(吉野郡)
- [ 寺院 ]
-
吉野郡吉野町吉野山2357
大海人皇子(後の天武天皇)ゆかりの法城。
吉野山で最古の寺院と云われ、役行者の高弟日雄角乗を初代とする日雄寺が在った跡と伝えられている。1333年(
- [ 寺院 ]
-
北葛城郡広陵町的場80
聖徳太子によって開創されたと伝えられる。
本堂には本尊薬師如来座像のほか、県指定文化財として両界板絵曼荼羅(1422~24年)、長谷寺式十一面観音(
-
だ 大願寺(宇陀市)
- [ 寺院 ]
-
宇陀市拾生736
聖徳太子が蘇我馬子に命じて建立したとも伝わる古寺。
創建は推古時代と伝えられる古刹で真言宗御室派、本尊は十一面観音菩薩像(焼けずの観音)。別名「七福寺」。十薬
- [ 寺院 | 花 ]

-
高市郡高取町壺阪3
創建は大宝3年に元興寺の弁基上人により開かれたとされる。
京都の清水寺の北法華寺に対し南法華寺といい、長谷寺とともに古くから観音霊場として栄えた。本尊の十一面観音は
-
と 洞泉寺
- [ 寺院 ]
-
大和郡山市洞泉寺町15
1585(天正13)年に、豊臣秀吉の弟で、郡山城主の秀長が創建。
本堂には鎌倉時代に快慶作と伝わる阿弥陀如来立像(重要文化財)が安置されている。寺の周辺は大和格子の古い街並
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
吉野郡十津川村小原225-1
十津川の水害の歴史や村人の暮らしぶりを、パネルを使って紹介。
皇室と深くかかわった村の歴史も知ることができる。近くに伝習館「十津川郷」がある。
-
な 奈良豆比古神社
- [ 神社 ]
-
奈良市奈良阪町2489
中殿に平城津比古大神(当地の産土神。奈良豆比古神とも)、左殿に春日宮天皇(施基親王、志貴皇子、田原天皇とも
-
な 中家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
生駒郡安堵町窪田133
中世武士の居館形式を伝える環濠屋敷。
10,477�uの広大な敷地には二重に濠が巡り、瓦の載った塀や入母屋造り。大和屋根の主屋、米
-
に 丹生川上神社中社
- [ 神社 ]
-
吉野郡東吉野村小968
水を司る罔象女神を祀っている。
白鳳4年(675年)に罔象女神(相殿伊邪奈岐命・伊邪奈美命)を御手濯(みたらし)川(高見川)南岸の現摂社丹
-
に 如意輪寺
- [ 寺院 ]
-
吉野郡吉野町吉野山1024
延喜年間(901年-922年)に日蔵上人により開かれたと伝わる。
南北朝時代、後醍醐天皇の勅願寺となった。裏山の松林には無念の思いで崩御した天皇の御陵が、京都に向かって築か
-
は 博西神社
- [ 神社 ]
-
葛城市寺口1231
延喜式名帳の載る古社。
祭神は北殿が下照姫命、南殿が菅原道真。社殿は一間社春日造りで、障塀で結ばれて南北に二社並立した類例の少ない
-
ほ 疱瘡地蔵
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
奈良市柳生町
3m近い岩に彫られた大磨崖仏で、正長の土一揆により徳政を勝ち取った百姓らが疱瘡よけを祈願して彫った物とされ
-
だ 達磨寺
- [ 寺院 ]
-
北葛城郡王寺町本町2-1-40
聖徳太子が達磨像を刻み、祀ったのが始まると伝わる。
達磨寺の境内には達磨寺1号墳・2号墳・3号墳と称される3基の古墳(6世紀頃の築造)が存在し、このうちの3号
-
ひ 檜原神社
- [ 神社 ]

-
桜井市三輪
大神神社の摂社で元伊勢の一つ、天照大御神を祀る。
御神体は磐座と神籬で本殿や拝殿はなく、独特の形をした三輪鳥居だけが立っている。香具山、畝傍山、耳成山をはじ
-
ひ 一針薬師笠石仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
生駒郡三郷町勢野東6-7-27
鎌倉時代に快慶が彫ったと伝わる。
俗に「一針薬師」と呼ばれ、針で刻んだような線刻の薬師如来像をあらわしている。薬師如来像には日光・月光両菩薩
-
び 白毫寺(奈良市)
- [ 寺院 | 花 ]
-
奈良市白毫寺町392
開基(創立者)は勤操(ごんそう)と伝える。
境内から奈良盆地が一望できる景勝地に建つ寺。本尊は阿弥陀如来。天智天皇の皇子、志貴親王の離宮跡といわれ、阿
- [ 不動 ]
-
大和高田市本郷町8-15
聖徳太子の建立、光明皇后が再建と伝わる。
本堂は、大和高田市唯一の国の重要文化財。この堂は1483(文明15)年に高田城主当麻為長が建立したもの。本
-
ほ 法楽寺
- [ 寺院 ]
-
磯城郡田原本町黒田360
孝霊天皇黒田廬戸宮跡に聖徳太子によって開創されたと伝えられている。
桃太郎のモデルと伝えられている、吉備津彦命は孝霊天皇の第3皇子としてここ黒田廬戸宮で生まれ、その後山陽道を
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]

-
御所市古瀬
巨勢道に面して2基並んでいる円墳。
丘陵の東斜面に横穴式石室の水泥古墳があり、南側の水泥古墳には玄室と羨道に石棺があり、羨道の棺には蓮華文が刻
-
め メスリ山古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
桜井市高田
古墳時代前期に築造されたと思われる全長224mの巨大な前方後円墳。別称は鉢巻山古墳、東出塚古墳などと呼称さ
-
も 本薬師寺跡
- [ 寺院 | 歴史 ]
-
橿原市城殿町
天武天皇が皇后の病気平癒祈願のために建て、698(文武天皇2)年に完成したと伝えられる。平城京遷都の際に移
-
や 矢田寺
- [ 寺院 | 花 ]
-
大和郡山市矢田町3549
正式の寺号を金剛山寺(こんごうせんじ)。
天武天皇の勅願により天武天皇8年(679年)に智通が開基と伝わる。別名「あじさい寺」とも呼ばれ、境内には約
-
や 山田寺跡
- [ 寺院 | 歴史 ]
-
桜井市山田
蘇我石川麻呂がの発願により7世紀半ばに建て始められ、石川麻呂の自害(649年)の後に創建した。昭和57(1
-
へ 平城京

- [ 歴史 ]
-
奈良市二条町
現在、平城宮跡には朱雀門、東院庭園、宮内省などが復元されている。
平城宮跡にあり、平城宮の正門。門をくぐって北へ行けば平城宮内、南へは平城京のメインストリートである朱雀大路
-
ほ 宝山寺
- [ 寺院 ]
-
生駒市門前町1番1号
真言律宗大本山の寺院。生駒聖天(いこましょうてん)とも呼ばれる。
1678(延宝6)年に宝山湛海が中興した。商売繁盛の現世利益と、禁酒など断ちものを祈願する庶民信仰の寺。生